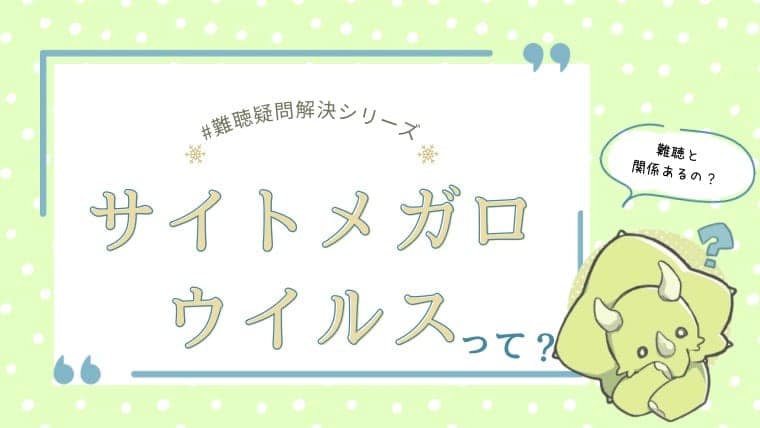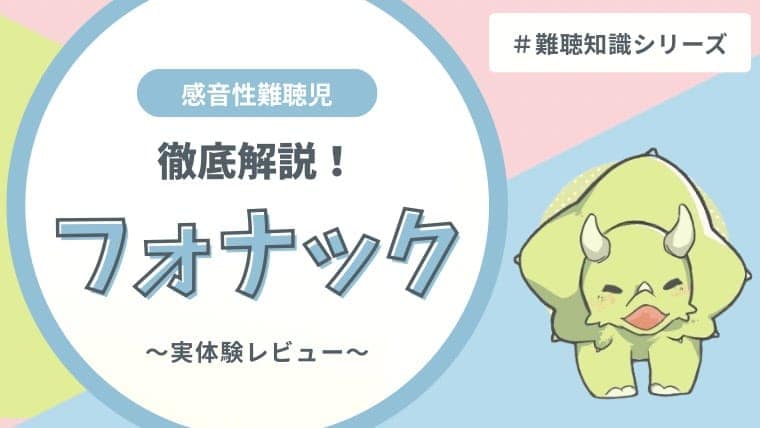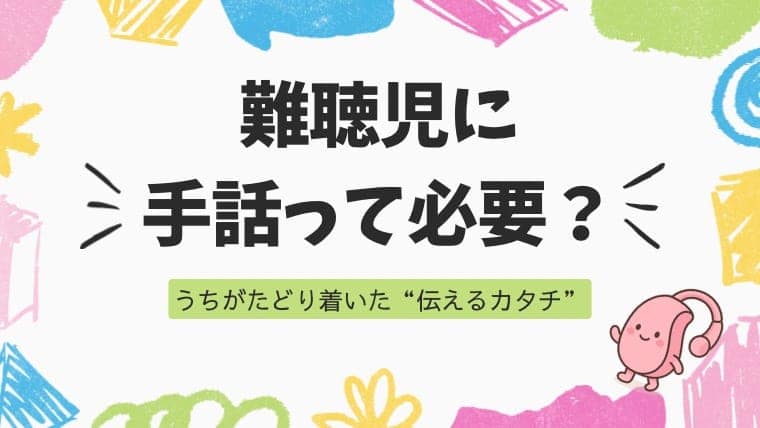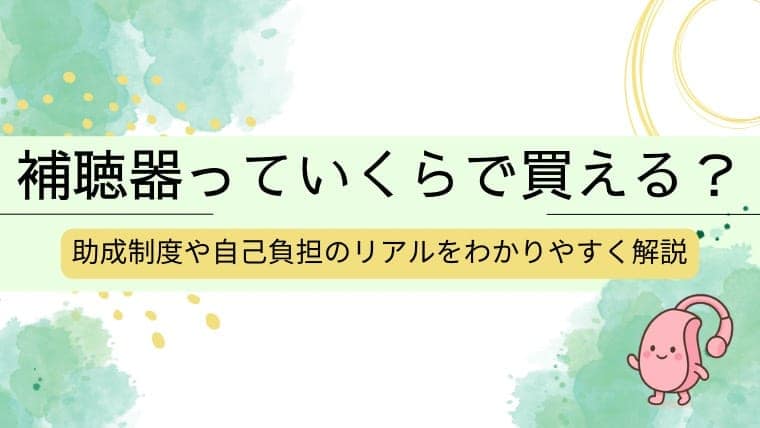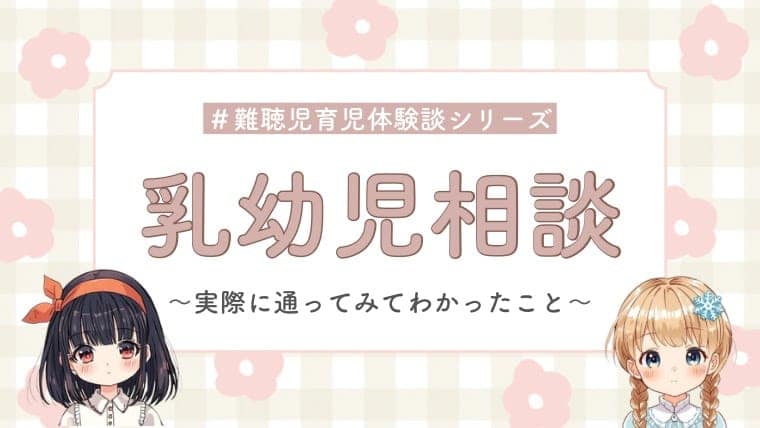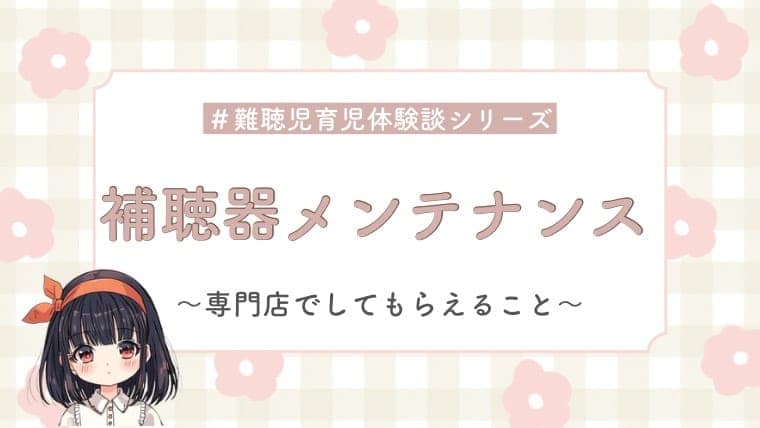ヘルツ(Hz)とは?音の“高さ”を理解するための基礎知識
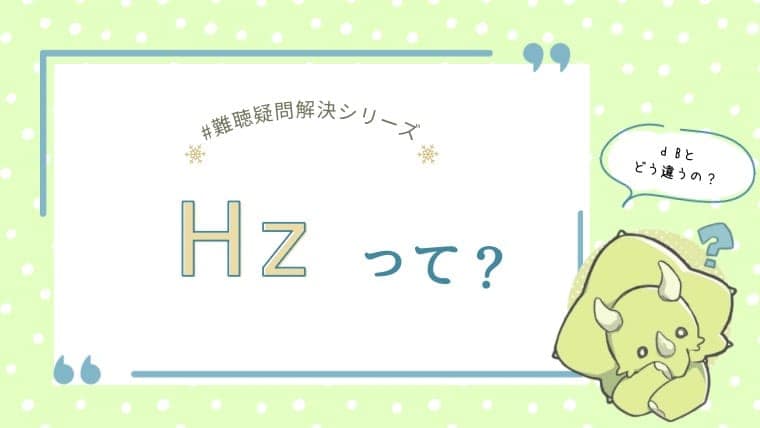
聴力検査やオージオグラムの説明で必ず出てくる「Hz(ヘルツ)」。
耳の聞こえを理解するうえで欠かせない概念ですが、「音の大きさ(dB)はなんとなく分かるけれど、ヘルツって何?」という方は多いものです。
この記事では、ヘルツの基本から、ヒトの聞こえにとって重要な周波数帯、そしてスピーチバナナとの関係までを、専門的な視点で整理します。
- ヘルツ(Hz)は音の“高さ”を示す単位で、1秒間の振動回数を表す
- 数値が小さいほど低音、大きいほど高音になる
- 聴力検査では主に250〜4000Hzを測定し、どの高さの音が聞こえにくいかを詳細に把握する
- 会話音は500〜4000Hzに集中し、この周波数帯をどれだけ聞き取れるかが言語発達において不可欠
難聴の基本的な仕組みを先に知りたい方は、こちらも記事も参考になります。

ヘルツ(Hz)とは?
ヘルツ(Hz)とは、音が1秒間に何回振動しているかを表す“周波数”の単位です。
振動回数が多いほど音は高く、少ないほど低く聞こえます。
- 250Hz … 太鼓のような低い音
- 1000Hz … 会話の中心
- 4000Hz以上 … サ行など明瞭度に関わる高い音
ヒトが感じ取れるのは 約20〜20,000Hz の範囲。
ただし、言葉の理解に必要なのはその一部だけです。
音の高さ(Hz)とあわせて、音の大きさ(dB)について理解しておくと、聴力検査の見方がより分かりやすくなります。
音の大きさ(dB)について、詳しくはこちらの記事を参照してください。
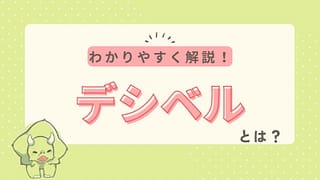
聴力検査ではなぜヘルツを見るの?
聴力検査では、音の大きさ(dB)だけでなく、音の高さ(Hz)ごとの聞こえ方を確認することが重要です。
それは、聞こえにくさは高さによって異なることが多いためです。
- 低音は聞こえるのに高音だけ弱い
- 高音は聞こえるのに低音が落ちている
など、周波数ごとに特徴が違います。
会話音が多く分布する帯域
ヒトの会話は 500〜4000Hz に集中しており、この帯域が落ちると意味の理解に影響します。
赤ちゃんや子どもの“聞こえのサイン”については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
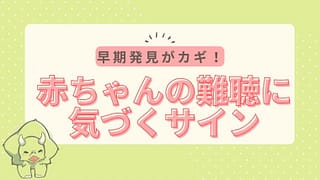
難聴の種類との関係
- 感音難聴 → 高音(2000〜4000Hz)が落ちやすい
- 伝音難聴 → 低音域が弱くなりやすい
そのため、検査では125〜8000Hzの幅を測り、どの高さが弱いかを可視化します。
周波数をイメージしやすくするために
聞き取れる高さの範囲は、生き物によって大きく異なります。
- 人間:約20〜20,000Hz
- 犬:〜40,000Hz
- 猫:〜60,000Hz
- イルカ:100,000Hz以上で会話
- コウモリ:100,000〜150,000Hzの超音波で定位
この違いを見ると、音の“高さ”には大きな個性があることが理解しやすくなります。
スピーチバナナとは?
人の会話音は、低い母音から高い子音まで幅広く分布していますが、実際には 500〜4000Hz の範囲に多く集中しています。
この“会話に必要な音の高さと大きさ”を地図のように示したものが下の写真の「スピーチバナナ」です。
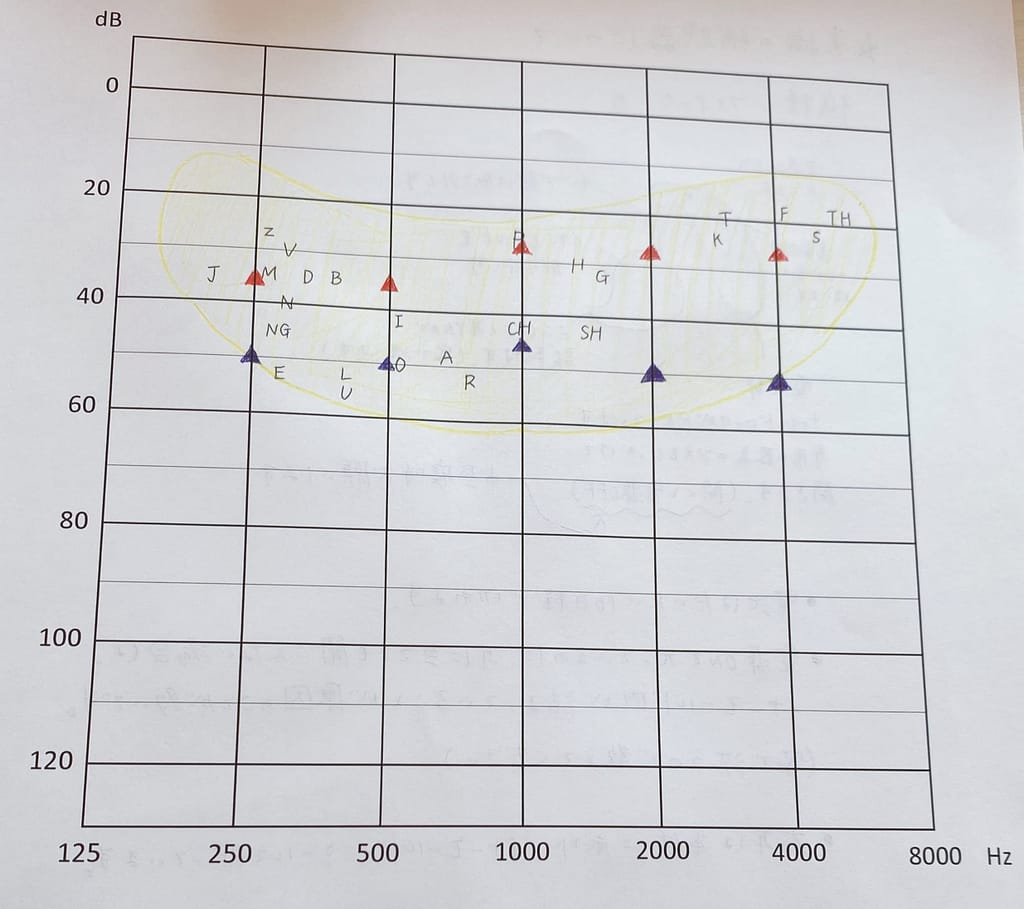
スピーチバナナについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
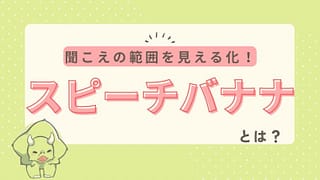
スピーチバナナの解説
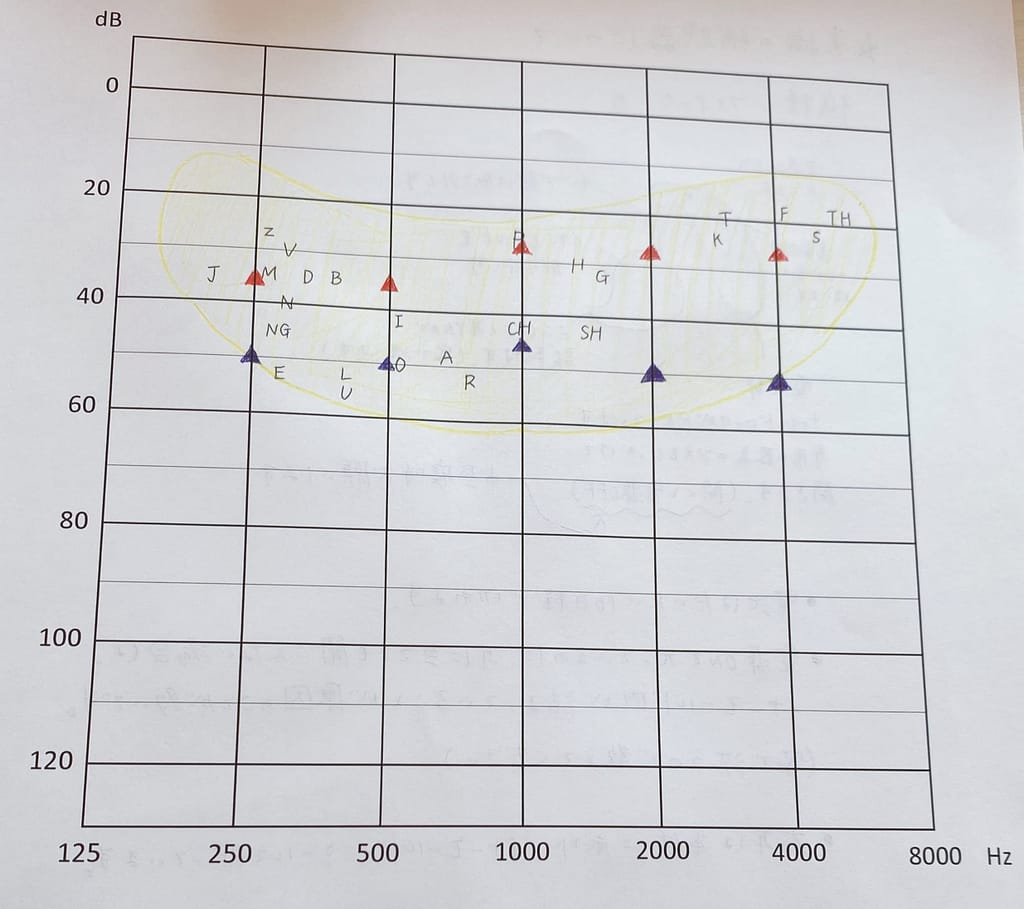
黄色い領域が、会話に使われる母音・子音が分布する部分です。
- 250〜500Hz(低音):母音「あ・う・お」
- 1000〜4000Hz(中〜高音):子音(サ行・タ行・カ行)が集中
- 4000Hz以上(高音域):明瞭度を左右する重要な音
このため、高音域が落ちると、言葉がぼやけたり聞き違いが増えることがあります。
写真の中の▲マークは、次女そらの聴力(補聴器装用時・裸耳)です。
このように聴力検査による聴力をスピーチバナナに重ねると、本人がどの音が聞こえていて、どの音が聞こえにくい(聞こえていない)のか一目で分かります。
実例:高音域が落ちている場合の聞こえ
トリケラ家の長女とうこ・次女そらの聴力では、2000〜4000Hzを中心とした高音域に低下が見られます。
この帯域は子音が多いため、
- 「さ」「た」などの区別がつきにくい
- 語尾が聞き取りにくい
- 雑音環境で特に聞こえの負担が大きくなる
といった特徴があります。
補聴器装用で20〜40dBまで改善しても、周波数ごとに改善度が異なるため、高音域には課題が残りやすいことがあります。
まとめ
ヘルツ(Hz)は、音の“高さ”を理解するうえで欠かせない指標です。
聴力検査ではどの高さが聞こえにくいかを丁寧に評価することで、言語発達や日常生活の聞き取りへの影響を正確に把握できます。
スピーチバナナは、会話音の高さと大きさを視覚的に整理した重要なツールであり、周波数ごとの聞こえ方を理解するのに非常に有効です。
お子さんがどの音域が苦手なのかを把握して、ことばの発達の手助けをしていきましょう。