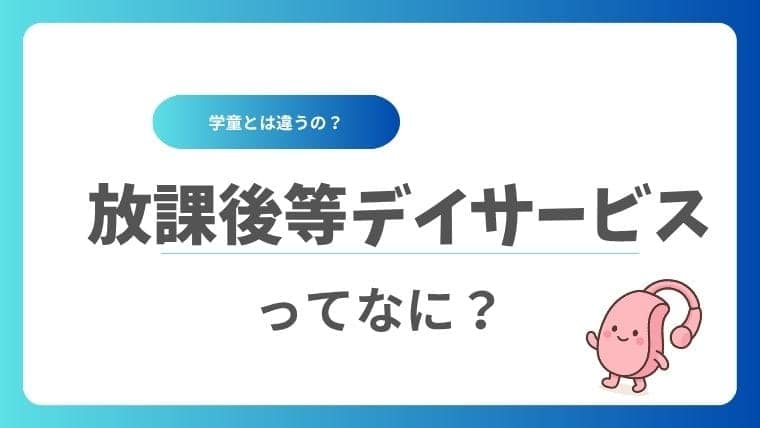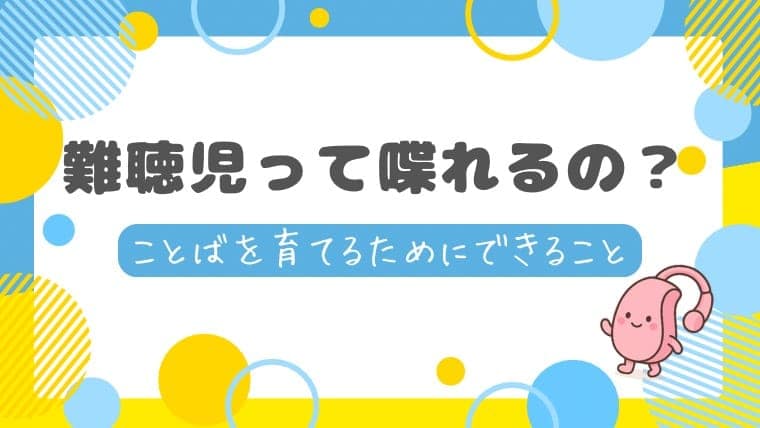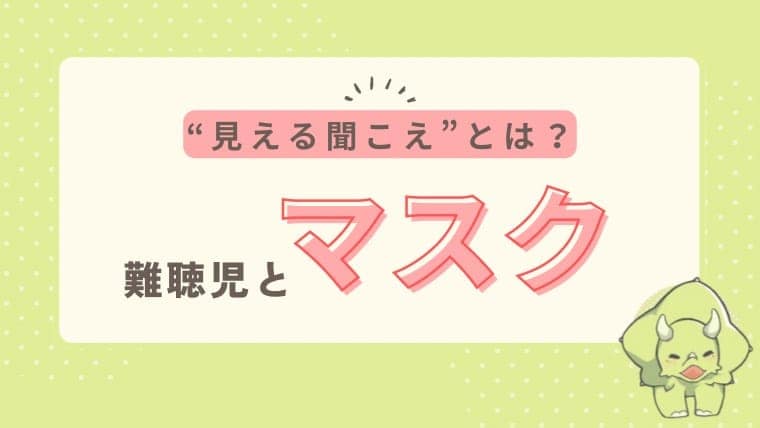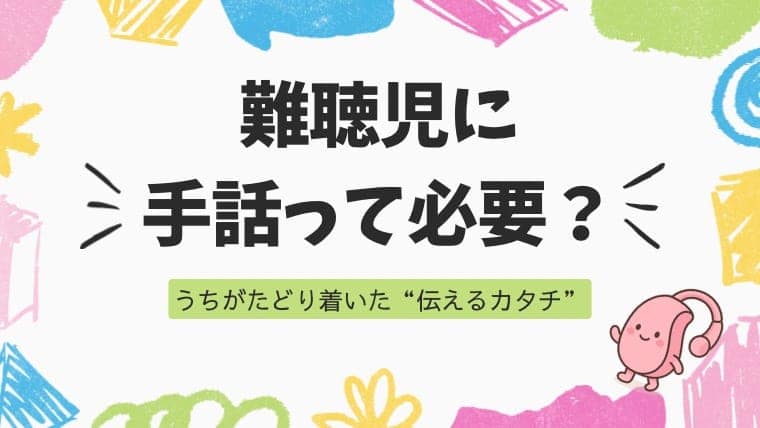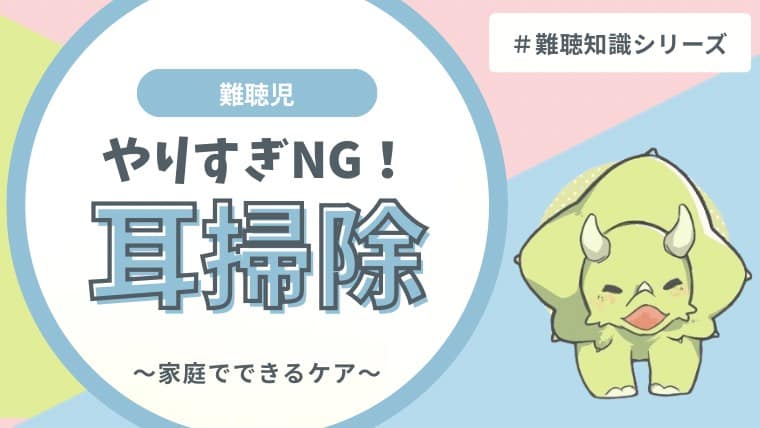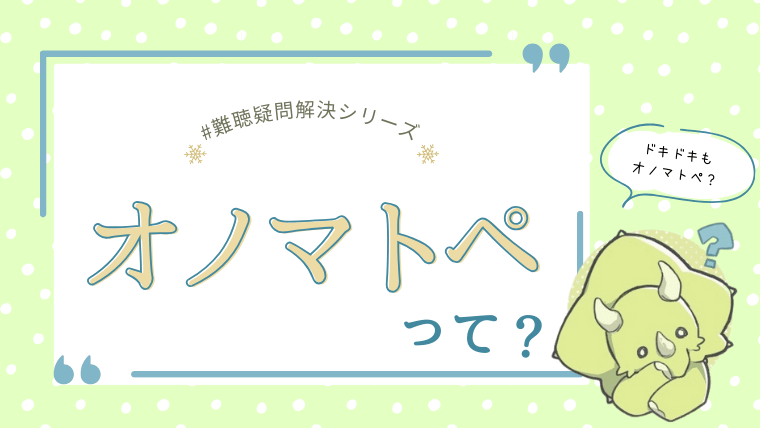難聴児の寝かしつけはどうする?|補聴器の外すタイミングと安心して眠るための工夫

難聴児の寝かしつけって何か工夫をした方がいいのかな?
難聴のある子どもの寝かしつけ。
「補聴器はいつ外すの?」
「寝室での声かけはどうしたらいい?」
など、初めての育児では不安になるポイントも多いですよね。
わたし自身、長女とうこの小さい頃は、寝る前の補聴器の扱いに悩んだ時期もありました。
この記事では、トリケラ家のリアルな寝かしつけの流れと、同級生ママたちのケースも交えながら、安心して眠るための工夫をまとめます。
- 補聴器は「お風呂の前に外して翌朝まで」の流れで無理なく定着
- 寝室は静かなので、補聴器を外しても会話は十分にできる
- 寝かしつけのスタイルは子どもによって違うため、家庭に合うリズムを大切に
寝る前の補聴器はどうする?
トリケラ家では、お風呂の前に補聴器を外し、そのまま翌朝まで外したままというリズムが自然に定着しました。
1日頑張って音を聞き続けた耳を、しっかり休ませるイメージです。
寝室に移動するととても静かなので、補聴器を外していても落ち着いた声での会話なら問題なく通じます。
とうこ・そらは中〜高程度の難聴ですが、「補聴器=ないと全く聞こえない」というわけではなく、静かな環境なら必要なやりとりはできます。
一方で、療育で会う同級生のママの中には「寝入るまで補聴器を外したくないタイプ」の子もいて、子どもが完全に寝たあとに親がそっと外しているケースもありました。
寝る前の補聴器の扱いは、子どもの性格や安心度によって変わるというのが実感です。
寝室での声かけの工夫
トリケラ家の場合、寝室がとても静かなので「聞こえにくい」と感じたことはあまりありませんでした。
そのため、特別な声かけの工夫はせず、いつも通り絵本を読むスタイルで自然に眠りにつくことができました。
補聴器を外すと、会話の聞き返しが少し増えることはありますが、寝る前は落ち着いた時間なので大きな困りごとはありません。
普段の声掛けの工夫については、こちらの記事にも紹介しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児への声かけの工夫5選|家庭でできる“伝わる”コミュニケーション
https://www.triceratops-family.com/communication/456/明かりの工夫は必要?
絵本を読み終えたら部屋の電気を消して、特別なライトを用意するなどの工夫はしていませんでした。
暗闇でも寝るまでに大きな不便はなく、いつものルーティンのまま自然に眠りについていました。
ただ、補聴器を外すと環境音がかなり減るため、一度寝入ると、多少の物音では起きにくいという特徴は感じました。
子どもによって違う「安心スタイル」
難聴児の寝かしつけで印象深いのは、子どもごとに安心するポイントが違うということ。
- 寝る前に補聴器を外してリラックスしたい子
- 逆に、ギリギリまで補聴器をつけていたい子
どちらも間違いではなく、「その子が安心して眠りに入れる形を選ぶ」のが一番大切だと感じます。
まとめ
難聴児の寝かしつけは、家ごとの“聞こえ方”や“性格”によってスタイルが大きく変わります。
トリケラ家のように、お風呂の前に補聴器を外してリラックスモードに入る子もいれば、寝る直前まで補聴器を外したくないという子もいます。
どちらが正解というわけではなく、その子が安心して眠れる方法を見つけることがいちばん大切です。
静かな寝室なら、補聴器を外していても必要な会話は十分にできますし、一度寝入れば物音で起きにくいという特徴もあります。
無理に一般化せず、家庭と子どものペースに合わせた“その子に合う寝かしつけ”を見つけていく。
それが、難聴児の毎日の安心につながっていきます。
静かな寝室でお話しするとことばも伝わりやすいね!