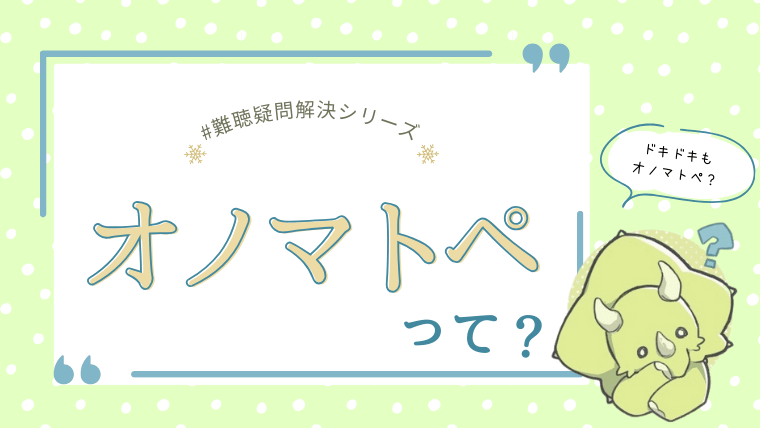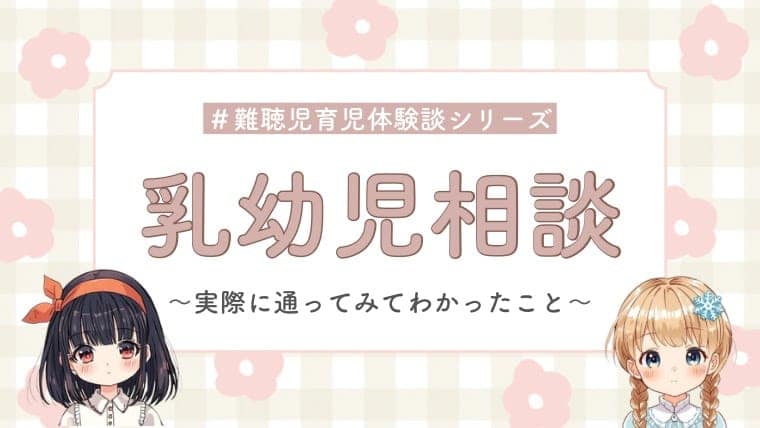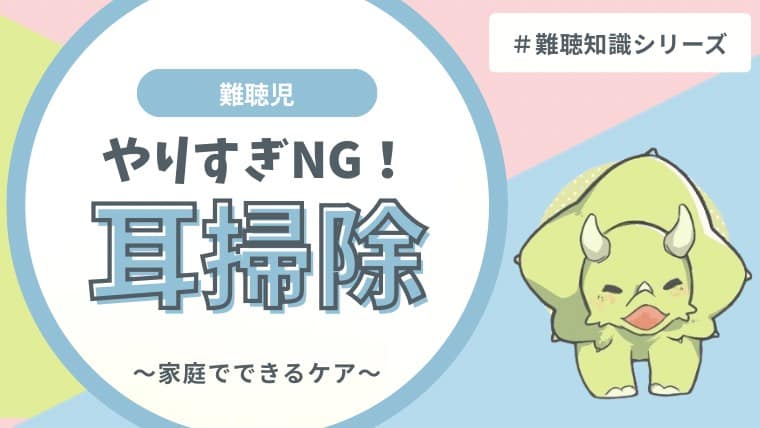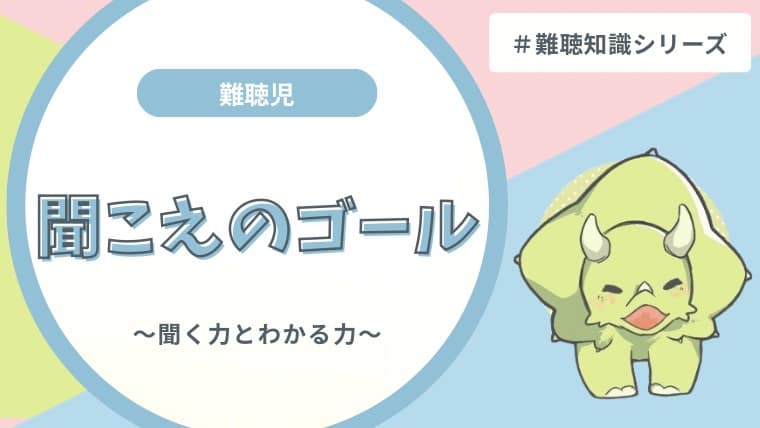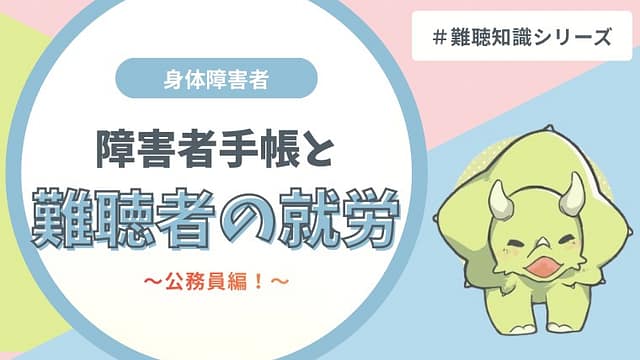補聴器っていくらで買える?
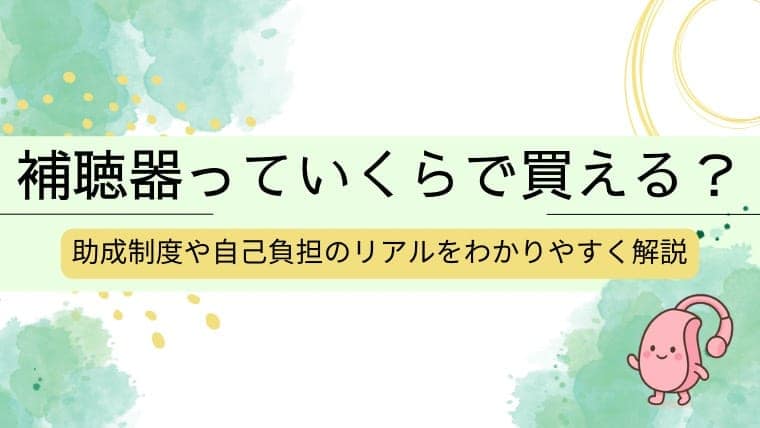
補聴器を買うことになったけど、高そうなイメージがあるなあ…
「子どもの補聴器って、いくらするんだろう?」
──そう思って検索したこと、ありませんか?
私も最初に値段を聞いたとき、正直びっくりしました。
でも調べていくうちに、補聴器の価格には大きな幅があり、助成を受けられる制度もあることがわかりました。
補聴器は“医療機器”として扱われるため、種類や機能、購入先、そして障害者手帳の有無によって費用が変わります。
同じ機種でも、制度を利用できるかどうかで自己負担額が大きく違うことも。
- 補聴器の購入には健康保険は使えないが、助成制度を使えば自己負担を大幅に減らせる
- 助成制度には「障害者手帳あり(補装具費支給制度)」と「手帳なし(日常生活用具給付等事業)」の2種類がある
- 条件を満たせば、両耳60万円の補聴器でも自己負担は数万円程度に抑えられることもある
この記事では、子どもの補聴器の一般的な価格帯や障害者手帳がある場合の助成制度、手帳がない場合でも受けられる補助のしくみ を、わかりやすくまとめて紹介します。
「うちも補聴器が必要になったかも…」という親御さんが、安心して次の一歩を踏み出せますように。
補聴器と保険の関係
補聴器の購入は、健康保険や生命保険、医療保険の対象外です。
そのため、医療機関で「補聴器が必要」と言われても、保険適用にはなりません。
ただし、障害者総合支援法による助成制度や、自治体ごとの補助制度を利用することで、費用の一部または大部分を補うことができます。
つまり、「保険ではなく制度でサポートを受ける」こと。
これが補聴器購入の基本の考え方です。
補聴器の価格帯
補聴器の価格は、一般的に片耳あたり5万円〜50万円ほどと幅があります。
この差は主に次の3つの要素で決まります。
1. 機能の違い
自動調整・ノイズキャンセル・Bluetooth対応など 高性能な機能が多いほど価格が上がります。
特に子ども用では、教室での聞き取りを助けるロジャー(FMマイク)対応機種が人気です。
2. 形の違い
耳かけ型・耳あな型などの形状によって価格が異なります。
成長に合わせてイヤーモールドを作り直す必要があるため、子どもには耳かけ型が主流です。
3. 購入場所の違い
補聴器専門店・医療機関・家電量販店など、販売ルートによっても価格や保証が異なります。
助成制度を使う場合は、自治体が指定した業者で購入する必要があります。
- 軽度難聴用:10〜20万円前後
- 中等度〜高度難聴用:20〜40万円前後
- 高度〜重度・高性能モデル:40〜60万円以上
補聴器の助成制度(手帳あり・なしの違い)
補聴器の助成制度には、「障害者手帳を持っている場合」と「まだ持っていない場合」の2種類があります。
どちらも障害者総合支援法に基づきますが、申請の窓口や負担割合が少し異なります。
障害者手帳がある場合(補装具費支給制度)
手帳を持っている人は、「補装具費支給制度」の対象になります。
ここでいう「補装具」とは、身体の機能を補うための道具のことで、義肢・車いす・メガネ・補聴器などが含まれます。
補聴器を“補装具”として申請・認定されると、費用の大部分が公費で補助されます。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 根拠法 | 障害者総合支援法 |
| 制度名 | 補装具費支給制度 |
| 負担割合 | 原則1割負担(=購入基準額の1/10) |
| 公費負担内訳 | 国50%・都道府県25%・市町村25% |
| 自己負担上限 | 0円〜37,200円(所得に応じて変動) |
障害者手帳がない場合(日常生活用具給付等事業)
手帳を持っていない人は、「補装日常生活用具給付等事業」の対象になります。
トリケラ家の長女とうこは障害者手帳を持っていないため、この制度を利用して補聴器を購入しました。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 根拠法 | 障害者総合支援法 |
| 制度名 | 日常生活用具給付等事業 |
| 負担割合 | 多くの自治体で3割自己負担 |
| 公費負担内訳 | 国50%以内・都道府県25%以内・市町村はそれぞれの判断による |
| 自己負担上限 | 自治体によって対象年齢・助成上限額が異なる |
両耳で約60万円の補聴器でしたが、リオネットの「ほちょうき購入サポート制度」と併用することで、実際の自己負担は約5万円ほどで済みました。
補聴器購入助成の申請の流れ
- 耳鼻科で聴力検査を受け、「補聴器が必要」と診断してもらう
- 意見書・見積書をもとに、市区町村の福祉課に申請
- 審査・決定後、補聴器専門店で製作・調整
制度の詳細や基準額は自治体によって異なるため、「〇〇市 補聴器 助成」で検索して確認するのがおすすめです。
メーカーによる購入サポート(リオネット)
補聴器メーカーの中には、購入時のサポートや助成制度に対応した販売を行っているところもあります。
中でもリオネット補聴器では、助成制度を利用する方に向けた「ほちょうき購入サポート制度」を実施しています。
この制度では、どれだけ高性能な補聴器を選んでも、購入基準額の1/10の価格で購入できるという仕組み。
とうこの場合もこの制度を利用し、当時一番小型で高性能な両耳60万円の補聴器を自己負担約5万円ほどで購入できました。
本当にありがたい仕組みですよね!
主要な補聴器メーカーの特徴については、こちらの記事で詳しく解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]子どもの補聴器どこで買う?主要メーカーを徹底比較【リオネット・フォナック・ほか】
https://www.triceratops-family.com/hearing-aid-manufacturer/421/まとめ
補聴器は高価に感じますが、制度を正しく利用すれば、数万円の自己負担で購入できる場合もあります。
大切なのは、購入前に一度自治体へ相談してみること。
「うちの場合はどんな制度が使えるのか」を知るだけでも、気持ちがぐっとラクになります。
助成制度の手続きは少し時間がかかるけれど、その一歩を踏み出すことで、子どもに合った聞こえの環境を整えることができます。
私も最初は戸惑いましたが、補聴器をつけたとうこの笑顔を見て、「申請して本当によかった」と感じました。
補聴器の価格に不安を感じたら、まずは制度を調べてみてください。
きっとあなたの子どもにもぴったりの“聞こえのサポート”が見つかります。
中~高程度の難聴なら、補聴器を着けると声かけに対する反応がぐっとよくなるよ!