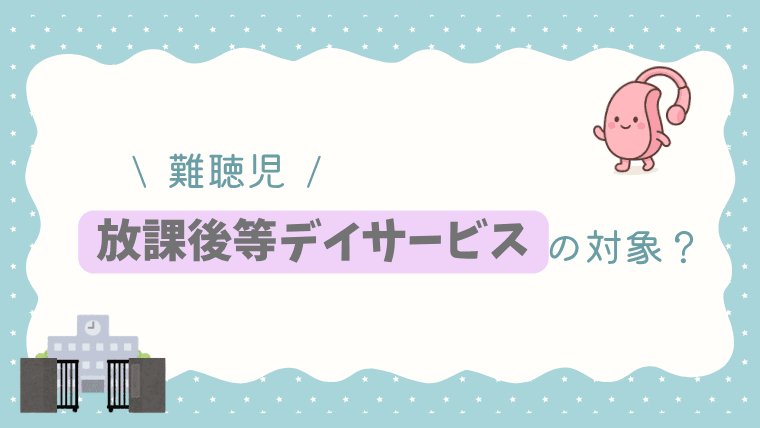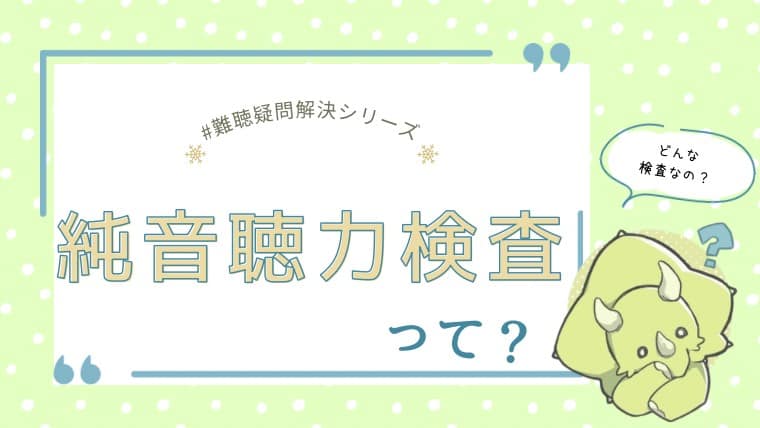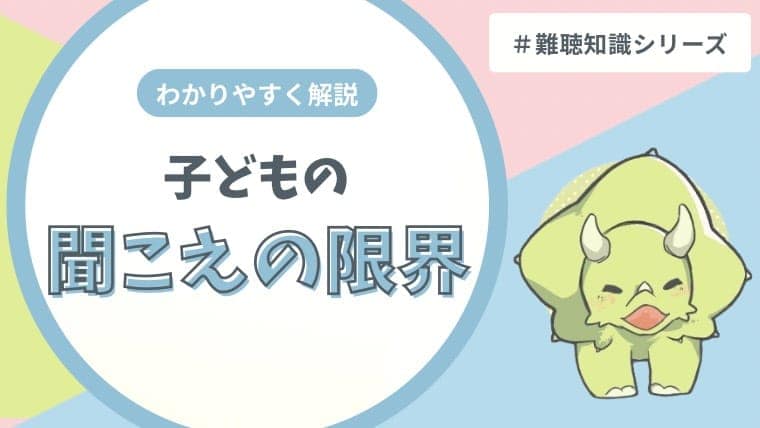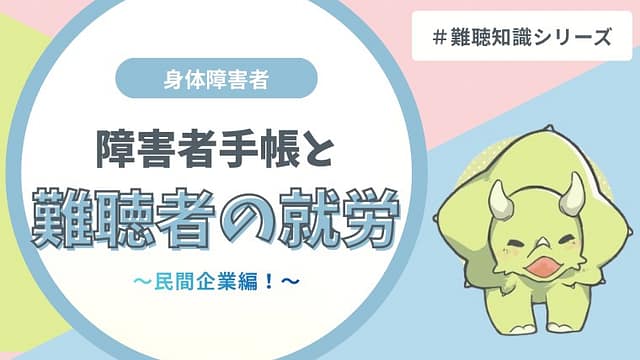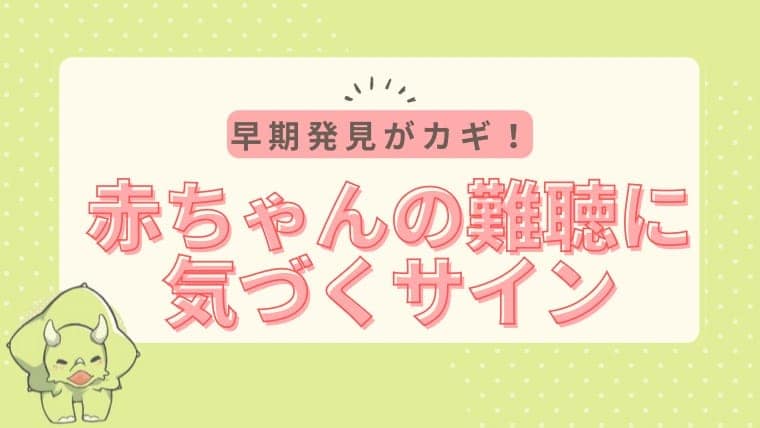DPOAE検査とは?結果に「反応なし」と書かれていたら
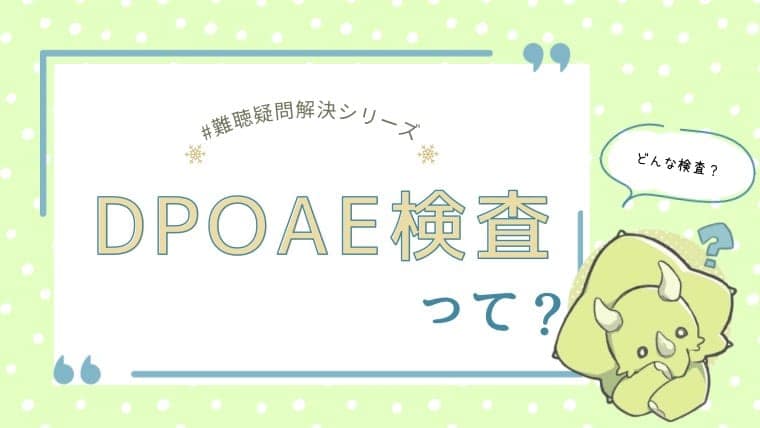

左の写真は、トリケラ家の長女とうこの補聴器作成にかかる補助の申請をした際に耳鼻科医からいただいた意見書の一部です。
ABR検査の結果の下に、「DPOAE 両側反応なし」と書かれています。
とうこの補聴器申請に添付されていた、医師の意見書を見返していたときのこと。
ふと目にとまったのが、「DPOAE 両耳反応なし」という文字でした。
当時の私は、その意味がまったく分からず、“反応なし”と聞くだけで「何か悪い結果なんじゃないか」と不安になったのを覚えています。
DPOAEとは、耳の奥の「内耳」がどのくらい音に反応しているかを調べる検査のこと。
今日は、あのときの私のように「結果の見方がわからない」という方へ向けて、DPOAEのしくみと“反応なし”の意味を、やさしく解説していきます。
- DPOAEは、耳の奥(内耳)の細胞が音に反応しているかを調べる検査
- 「反応なし」は、内耳の反応が確認できなかったという意味で、聞こえていないと断定する結果ではない
- ABRやASSRなどの検査と組み合わせて、総合的に聴力を判断することが大切
DPOAEとは?
DPOAE(ディーピーオーエーイー)とは、耳の奥にある「内耳(ないじ)」の働きを調べるための検査です。
私たちが音を聞くとき、内耳の中にある「蝸牛(かぎゅう)」という部分が音の振動を感じ取って脳へ伝えています。
この蝸牛の中には、「外有毛細胞(がいゆうもうさいぼう)」という細胞があり、音を受け取ると小さな“振動のような音”を自分でも出すんです。
DPOAE検査では、この小さな音をキャッチすることで、蝸牛がちゃんと働いているかどうかを確かめます。
つまり、「音を感じ取る耳の細胞が元気に動いているか」を見る検査なんですね。
赤ちゃんでも痛みはなく、眠ったままでもできる検査なので、「いつ検査したんだろう?」と覚えていないこともよくあります。
でも、その一枚の結果は、赤ちゃんの“聞こえの入り口”を知るための大切な情報なんです。
新生児聴覚スクリーニング検査との検査方法の違いについては、こちらの記事を参考にしてください。

どんな仕組みで音を測るの?
DPOAE検査では、耳の中に小さなイヤホンのような機械を入れて、2種類の音(ちょっと違う高さのトーン)を同時に流します。
すると、内耳の「蝸牛」の中にある外有毛細胞が反応して、自分でも小さな音を出します。
この音を「耳音響放射(じおんきょうほうしゃ)」といって、とても微弱ですが、専用のマイクでキャッチすることができます。
この反応が確認できれば、「内耳の細胞がちゃんと音に反応している=蝸牛の働きが正常」と判断されます。
一方で、音を流しても反応が見られない場合は、外有毛細胞がうまく働いていない、つまり内耳の機能が低下している可能性があると考えられます。
結果に「反応なし」と書かれていたら
とうこの意見書を見たとき、「DPOAE 両耳反応なし」という言葉を目にして、不安でいっぱいになったのを覚えています。
“反応なし”と聞くと、まるで「何も聞こえていない」という意味のように感じてしまいますよね。
でも、DPOAEはあくまで「内耳(蝸牛)の細胞が音に反応しているかどうか」を見る検査です。
反応がなかったというのは、音を感じ取る外有毛細胞の働きが弱い、もしくは確認できなかったという状態を示しています。
この結果だけで「聞こえていない」と断定するわけではありません。
医師はこのDPOAEの結果をもとに、ABR(聴性脳幹反応)やASSRなど、脳の反応を調べる検査を組み合わせて、総合的に聴力を判断します。
冒頭のとうこの意見書も、ABRの検査結果とあわせて書いてありました。
つまり、“反応なし”という言葉は「音の入り口である内耳の反応が見えなかった」という意味であって、「すべての音が聞こえない」という結果ではないのです。
他の検査との違い(ABRやASSRとの関係)
DPOAEは、「内耳の細胞がちゃんと働いているか」を確認する検査です。
それに対して、ABRやASSRは、「脳が音を感じ取って反応しているか」を見る検査。
同じ“聞こえ”を調べる検査でも、見ている場所が少し違います。
◆DPOAE
→ 内耳(蝸牛)の外有毛細胞の働きを確認する。
→ “音を感じ取る入り口”のチェック。
◆ABR(聴性脳幹反応)
→ 音を聞いたときに、脳の中のどの部分がどんな反応をするかを調べる。
→ 小さな電極を頭につけて、眠った状態で行うことが多い。
◆ASSR(聴性定常反応)
→ ABRと似ているけれど、周波数ごと(音の高さごと)に聴こえの程度をより詳しく測定できる。
→ 補聴器をつけるときの“調整の目安”にもなる。
この3つの検査を組み合わせることで、「耳のどの部分に原因があるのか」「どのくらいの大きさの音なら聞こえるのか」をより正確に知ることができます。
だから、DPOAEの結果だけで判断するのではなく、ABRやASSRとあわせて“総合的に”見ることが大切なんです。
赤ちゃんの難聴に気付くサインについては、こちらの記事で解説しています。
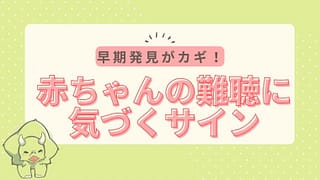
まとめ
とうこの意見書にあった「DPOAE 両耳反応なし」という言葉。
あのときは「どうしよう」と胸がぎゅっとなりました。
でも、調べていくうちにわかったのは——
それは“聞こえの入り口である内耳の細胞が反応しなかった”という意味であり、「すべての音が聞こえない」という結果ではないということ。
DPOAEは、赤ちゃんでも受けられる、負担の少ない大切な検査です。
そしてABRやASSRと組み合わせることで、子どもの「今の聞こえ方」をより正確に知ることができます。
私も最初は不安でいっぱいでしたが、検査の意味が分かると、少しずつ安心に変わっていきました。
結果を“終わり”ではなく、“始まり”として受け止めていけば、きっとその子に合ったサポートの道が見えてきます。

DPOAEは“聞こえの入り口”を知る大切な検査ということだね!