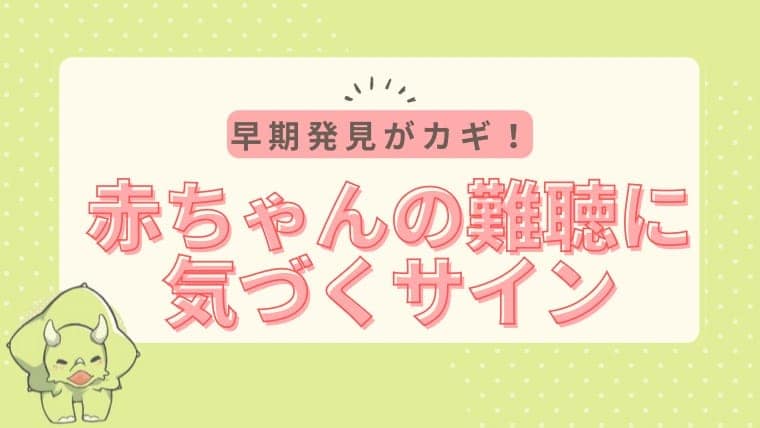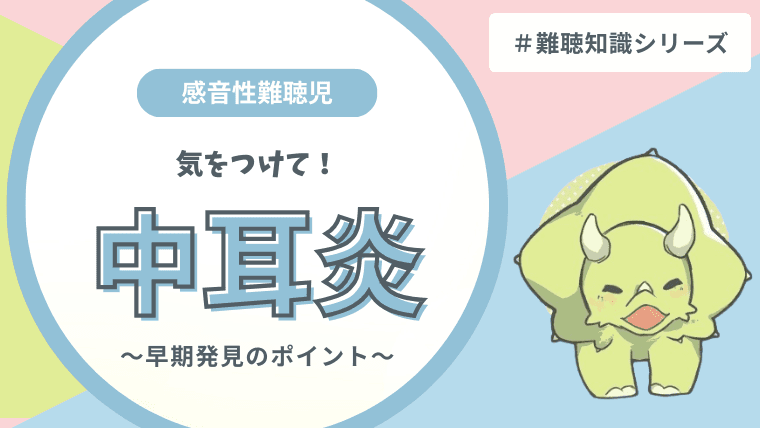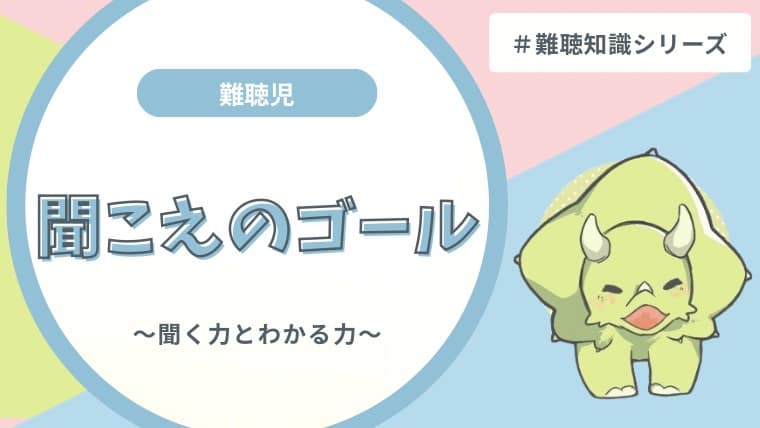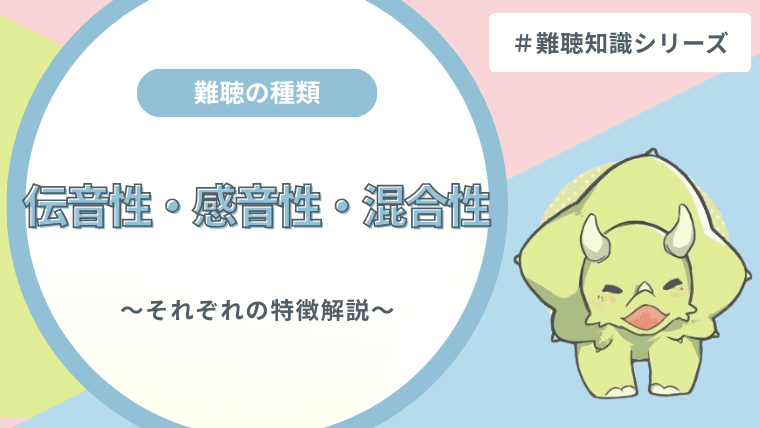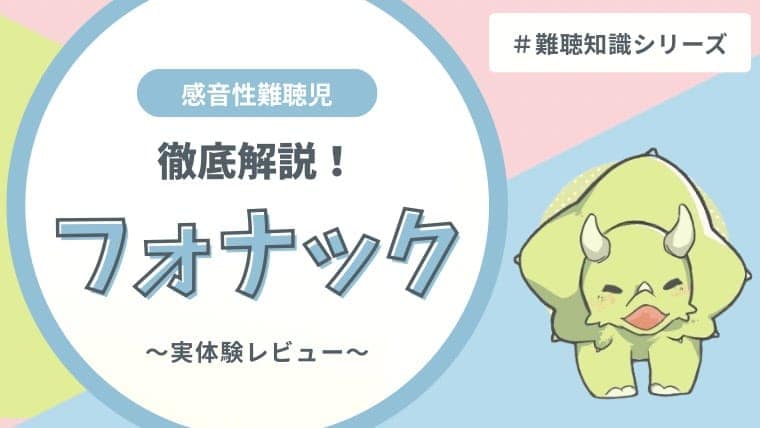難聴児への声かけの工夫5選|家庭でできる“伝わる”コミュニケーション
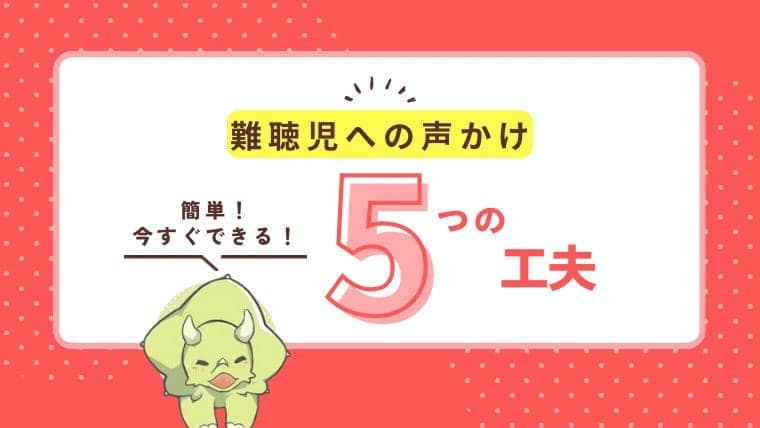
難聴のある子どもと向き合う中で、そんなふうに感じたことはありませんか。
実は、家庭の中での“声かけ”や“環境づくり”こそが、子どもの言葉の育ちを支える大きな力になります。家庭でのちょっとした工夫が、子どもの「伝えたい」「わかりたい」を支えるきっかけになります。
今回の記事では、感音性難聴の長女・次女に対してわたしが日々意識している声かけや家庭でできる環境づくりの工夫を紹介します。
- 難聴児にとって大切なのは、“どう話すか”より“どう伝わるか”
- オノマトペや肯定的な言葉かけで、伝わる喜びを育てる
- 静かな環境と優しい対応が、子どもの自信につながる
家でできる“伝わる声かけ”の工夫
①オノマトペをふんだんに使う
まず工夫していることの1つ目は、会話の中でオノマトペをふんだんに使うことです。
オノマトペとは、「ポカポカ」「キラキラ」「ゴロゴロ」「ワクワク」など、音や動き、感触、気持ちなどを音の響きで表す言葉のことです。日本語にはオノマトペがとても多く、感覚的にイメージを伝えられるのが特徴です。
難聴のある子どもにとって、耳だけではなく「見た感じ」や「体の感覚」からも言葉を理解することが多いため、オノマトペは“ことばの世界を広げるサポート”になります。
たとえば、こんなふうに日常会話に取り入れています。
- 「今日の天気は晴れだねぇ。お日さまポカポカだね」
- 「猫さんがトコトコ歩いているよ。どこに行くんだろうねぇ」
- 「お片づけしよっか。ピカピカにしちゃおう!」
オノマトペを使うと、言葉が生き生きとして、子どもが表情や動きで“意味”を感じ取りやすくなります。会話の中にリズムが生まれて、ママの声かけも自然と楽しくなります。
オノマトペについては、こちらの記事でも解説しています。

②否定せずに、正しい言葉で言いかえる
工夫していること2つ目は、子どもの言葉を否定せず、正しい言葉に言いかえてあげることです。
子どもが言葉を覚え始めるころは、発音がまだあいまいだったり、言い間違いが多かったりします。そんなとき、私は「違うよ」と否定せず、まず伝えたい気持ちを受け止めるようにしています。
たとえば、お散歩中に空を飛んでいるヘリコプターが見えたとき。
子どもが
「ママー!へりぽくたーいた!」
と言ったとき、つい「違うよ、“ヘリコプター”だよ」と言いたくなるけれど、私はこう返すようにしています。

ほんとだ!ヘリコプターだね!よく見えたね!
このように子どもの発語が間違っていたとしても、否定せず、肯定してから正しい言葉で言い替えてあげる。
このように「伝えたいことがママに届いた!」という成功体験を積み重ねることで、子どもは自信を持ち、言葉への興味が深まります。
間違いを正すよりも、“伝わったうれしさ”を共有すること。その積み重ねが、自然と正しい言葉の習得にもつながっていきます。
難聴のある子がどのように話す力を育てていくのかについては、こちらの記事で解説しています。
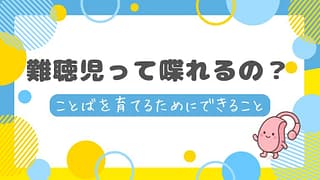
③聞こえやすい環境づくり
工夫していることの3つ目は、聞こえやすい環境づくりです。
言葉のやりとりは、どんな環境で話すかでも伝わり方が大きく変わります。私は、声かけをするときには「周りの音」をできるだけ整えるようにしています。
たとえば、家にいるとき。子どもが何かに集中しているときは、基本的にテレビは消します。
一対一で向き合って話すときに、余計な雑音は必要ありません。私の声がまっすぐ子どもに届くように、静かな空間をつくることも大切な工夫のひとつです。
静かな環境でゆっくりと話すだけで、子どもの表情がふっとやわらかくなる瞬間があります。「聞こえた」「わかった」という安心感が、子どものやる気や自信につながっていく気がします。
④「聞こえなかった」ときの対応
工夫していることの4つ目は、聞こえなかったときの対応です。
これは、難聴児の“あるある”のひとつなのですが、難聴児は「今なんて言ったの?」とよく聞き返してきます。うちの子もよく言います。
難聴のある子は、健聴の子が当たり前のようにやっている“ながら聞き”ができません。何かに集中しているときに話しかけられても、音が届いていなかったり、言葉がはっきり聞き取れなかったりすることがあります。
これから社会の荒波に揉まれて育っていくこの子たちは、将来私の助けなしで社会で生きていかなくてはなりません。自分のできないこと・できなかったことを、自分の力できちんと把握する力をつけていかなくてはなりません。
だから私は、「聞こえなかったときに聞き返すこと=悪いこと」と思ってほしくありません。
「今なんて言ったの?」と言われたときは、「〇〇って言ったんだよ」と、落ち着いてもう一度伝えるようにしています。
「聞こえなかった」ときにやさしく返すことで、「聞き返してもいいんだ」「ママはちゃんと教えてくれる」という安心感が生まれます。その安心感こそが、子どもが自分から会話を楽しめるようになる第一歩だと感じています。
⑤名前を呼んで、聞く姿勢をつくってから話す
工夫していることの4つ目として、子どもに声をかけるときには、まず子どもの名前を呼び、こちらを向いて“聞く姿勢”になったのを確認してから話し始めるようにしています。
難聴のある子は、耳だけでなく口の動きや表情からも情報を受け取っています。だから、顔を見て話すことはとても大切です。
正面を向いて話すだけで、聞き取りやすさも理解のしやすさも変わってきます。
小さいころは必ず目を合わせてから話すようにしていましたが、今では2人ともだいぶ大きくなり、聞こえているのにわざと無視するという小技(!?)を身につけました。笑
なので最近は、名前を呼んで反応があれば、無理にこちらを向かせず話し出すこともあります。「聞く準備ができてから話す」ことを意識するだけで、伝わり方も、子どもの集中度もまったく違います。
まとめ
言葉の力は、日常の中で少しずつ育っていきます。難聴のある子どもにとっては、音だけでは伝わりにくいことも多いため、家庭での“伝わる工夫”が特に大切です。
オノマトペを取り入れることで、音や動きをイメージしやすくなり、否定しない言いかえは、言葉への前向きな気持ちを育てます。
また、静かな環境づくりや、聞き返されたときに落ち着いて伝え直す姿勢、そして「名前を呼んでから話す」という小さな習慣は、子どもが安心して聞く準備を整える助けになります。
これらの積み重ねは、言葉そのものだけでなく、「話すって楽しい」「伝わるってうれしい」という経験を増やしていきます。
その経験こそが、子どもの自己肯定感やコミュニケーションの力をゆるやかに、そして確かに育てていくと感じています。

まずはこの5つの中から自分にもできそう!と思ったことをお家でやってみてね!