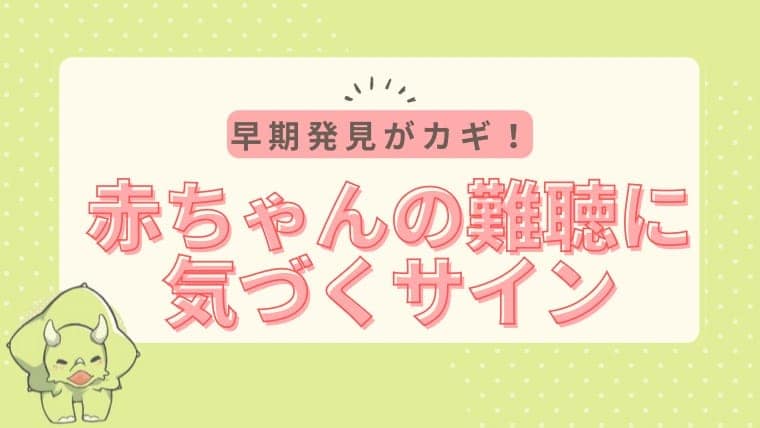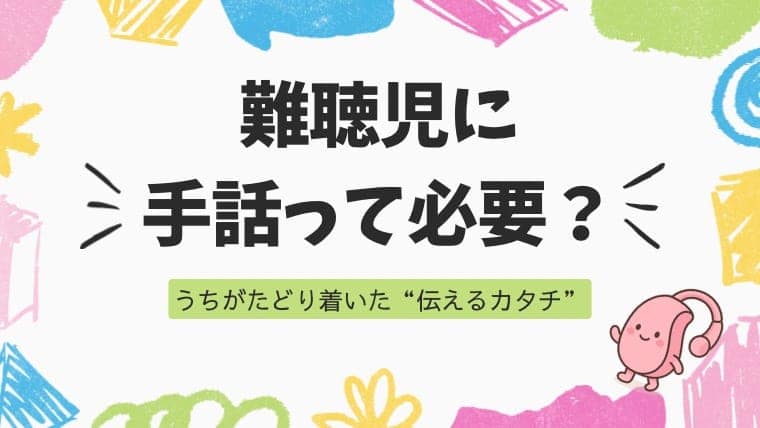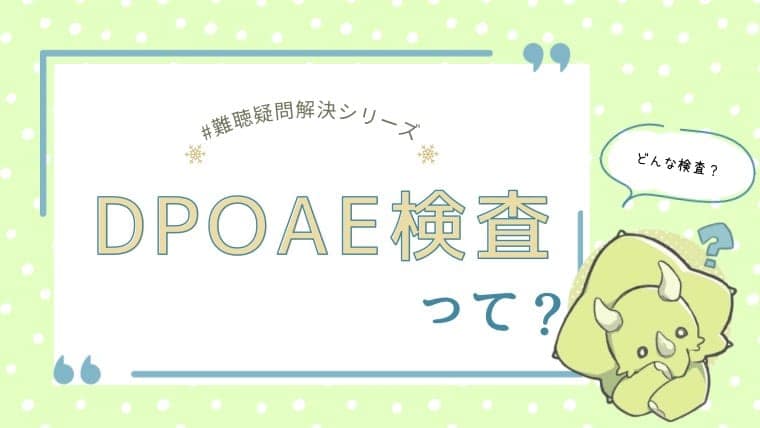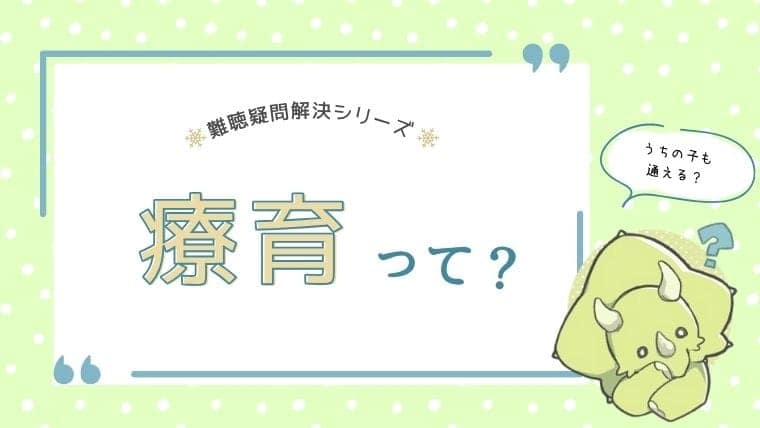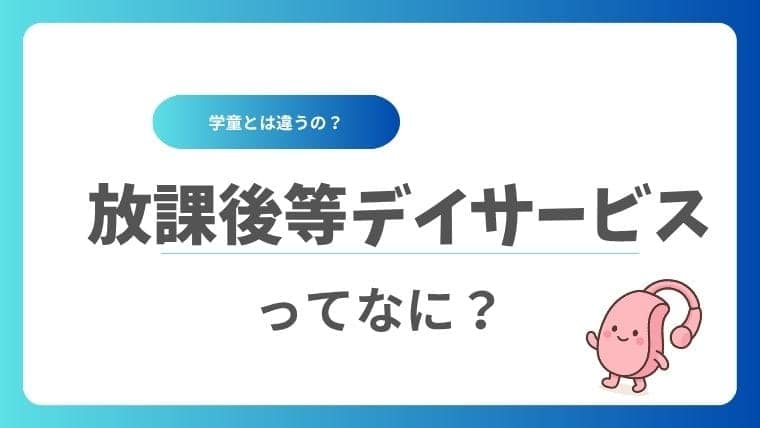子どもの障害の受容について
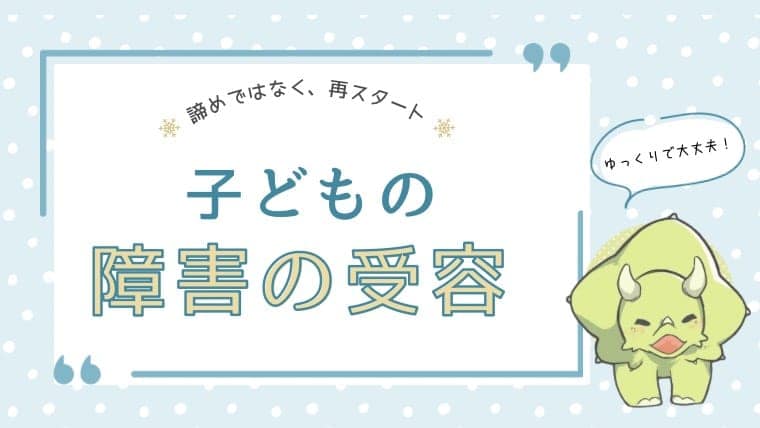
この子が聴覚障害?なんで?どうして?
長女とうこの難聴の診断を聞いたあの日、「どうしてうちの子が?」と頭の中が真っ白になりました。
泣いても泣いても現実は変わらなくて、ただ時間だけが過ぎていきました。
けれど、今振り返ると――
あのとき感じた「混乱」や「否定の気持ち」も、ぜんぶ“受け入れへの途中”だったんだと思います。
- 「障害の受容」は“前向きな再スタート”のプロセス
- 否定・怒り・悲しみなどの感情も、受容のための自然で大切な通過点
- 受け入れることは、諦めではなく「わが子をもう一度愛し直すこと」
「子どもの障害を受け入れる」って、けっして一瞬でできることじゃありません。
ゆっくり、少しずつ、心が整っていくプロセスなんです。
受容のプロセスとは?
心理学では、障害や病気など大きな出来事を受け止めていく過程に「受容のプロセス」があると言われています。
それはまるで、心が少しずつ現実に追いついていくような時間です。
たとえば──
否認(そんなはずない)
診断を聞いた直後は、信じたくない気持ちでいっぱいになります。
「きっと検査のミス」「もう少し成長すれば聞こえるようになるかも」
そう思うのは自然な反応です。
怒り(どうしてうちの子が)
少し現実が見えてくると、悔しさや不公平感が湧いてきます。
誰かを責めたい、どうにもならない気持ちをぶつけたくなる。
でも、それも“心が動き出した証拠”です。
取引(何かすれば治るかも)
「毎日マッサージしたら良くなる?」「特別な療法を受けたら…?」
できることを必死に探す時期。希望と不安が入り混じります。
抑うつ(悲しみ・無力感)
努力しても現実は変わらない…と感じて落ち込む時期。
涙が止まらなくなる日もあります。
けれど、この静かな時間こそ、心が受け止める準備をしている段階です。
受容(今の子どもを愛し直す)
時間をかけて、「うちの子はこの子のままでいい」と思えるようになる。
“障害がある”という事実よりも、“今この子が笑っている”ことを大切に感じられるようになります。
こうした段階は、順番どおりに進むわけではありません。
行きつ戻りつしながら、少しずつ“心の形”が変わっていくのです。
そして、それぞれのペースでたどり着いた「受容」は、その人だけの温かい答えになります。
とうこの難聴を受け止めるきっかけになった出会い
私の場合、「取引」の段階はありませんでした。
医師から「治るタイプの難聴ではありません」とはっきり聞いていたので、“どうしたらいいかわからない”という混乱と、“なぜうちの子が”という怒り、そして深い悲しみの中を、ただ行き来していました。
そんな育休中のある日、職場にとうこを連れて行き、特別支援に詳しい上司に「この子、難聴って言われたんです。どうしたらいいかわからなくて…」と泣きながら相談しました。
上司はとても親身に話を聞いてくださり、仕事をやめてこの子の療育に全力を尽くした方がいいのか悩んでいると伝えたところ、
「この子が大人になったときに、母親が自分のせいで仕事をやめてしまったと聞いて、果 たしてその子は喜ぶだろうか?育休を3年まで延ばしてもいい。あなたのような可能性がある人がやめてはいけない」
と言ってくださり、仕事はやめずに育てていこうと決めました。
そして上司が、当時住んでいた県の「難聴児保護者の会」の会長さんを紹介してくれたんです。
その方との出会いが私の人生を変えました。
初めてお会いした日は、上司も一緒に喫茶店でお茶をしました。
会長さんはとても穏やかで、「今度、家に遊びにおいで」と声をかけてくれました。
数週間後、勇気を出してお邪魔すると、彼女はお子さんの小さな頃の絵日記や写真を見せながら、
「こんなふうに育ててきたのよ」と話してくれました。
そのとき初めて、「ろう学校の幼稚部」という存在を知りました。
そしてしばらくして、その家の中学生の息子さんが学校から帰ってきたんです。
難聴があると聞いていたけれど、元気に動き、笑い、会話する姿を目の前で見た瞬間――
胸の奥がふっと軽くなりました。
「難聴があっても、ちゃんと大きくなれるんだ」
その実感が、わたしにとって“受容”の始まりでした。
受容を支える理論モデル:ドローターの「障害受容の段階的モデル」
心理学者デニス・ドローター(Dennis D. Drotar)は、子どもの障害を知った親の心の動きを「段階的モデル」としてまとめています。
それは、悲嘆(grief)のプロセスをもとにしたもので、親が現実をどう受け止め、子どもとの新しい関係を築いていくかを説明しています。
このモデルでは、障害を受け入れるまでの過程をいくつかの感情段階として示しています。
- ショック(Shock):診断を受けた直後の混乱と現実感の喪失
- 否認(Denial):まだ信じたくない、現実を受け止めきれない気持ち
- 悲しみ・怒り(Grief / Anger):どうしてうちの子が、という強い感情
- 適応(Adaptation):少しずつ現実を見据え、行動を取り戻す時期
- 受容(Acceptance):障害のある子どもを“わが子として再び愛し直す”段階
このモデルの特徴は、「直線的に進むわけではない」という点です。
一度受け入れたと思っても、ふとしたきっかけでまた悲しみが戻ることもあります。
でも、それでいいんです。
その繰り返しの中で、少しずつ“親としての心の強さ”が育っていきます。
受け入れること=諦めることではない
「受け入れる」と聞くと、どこか“もう仕方ない”という響きを感じる人もいるかもしれません。
でも、本当の意味での“受容”は、あきらめではなく、再スタートです。
障害を受け入れるということは、「この子の可能性を、ありのままの形で信じる」こと。
聞こえにくさという現実を受け止めながら、その子らしく育っていく道を一緒に見つけていくことです。
難聴児の進路選びについては、こちらの記事で解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児小学校選び方ガイド|通級?難聴学級?ろう学校?
https://www.triceratops-family.com/school-selection-guide/413/私も、会長さん親子との出会いを通して、「難聴があっても、できることがたくさんある」「未来は閉ざされていない」ということを、実際の姿で見せてもらいました。
それからは、少しずつ「聞こえにくさ」を“特別な個性”のように感じられるようになり、“できないこと”ではなく、“どうすればできるか”を考えるようになっていきました。
受け入れることは、“終わり”じゃない。
むしろ、“新しい親子のはじまり”なんです。
まとめ:同じように悩む親御さんへ
とうこの難聴の診断を受けたばかりのころは、「前向きに」なんて言葉、到底信じられませんでした。
泣いて、落ち込んで、どうしていいかわからなくて。
そんな日々を、私も通ってきました。
でも、泣いた日も、悩んだ時間も、全部が「わが子を想う気持ち」そのものだったんだと、今では思います。
受け入れるスピードは、人それぞれ。
時間がかかっても、戻っても、立ち止まってもいい。
気づけばちゃんと、子どもと一緒に前に進んでいます。
あのとき出会った会長さんが私にしてくれたように、今度は私が、誰かの背中をそっと押せたら。
そんな思いで、今日もこのブログを書いています。
私の体験談が誰かの希望になるといいな!