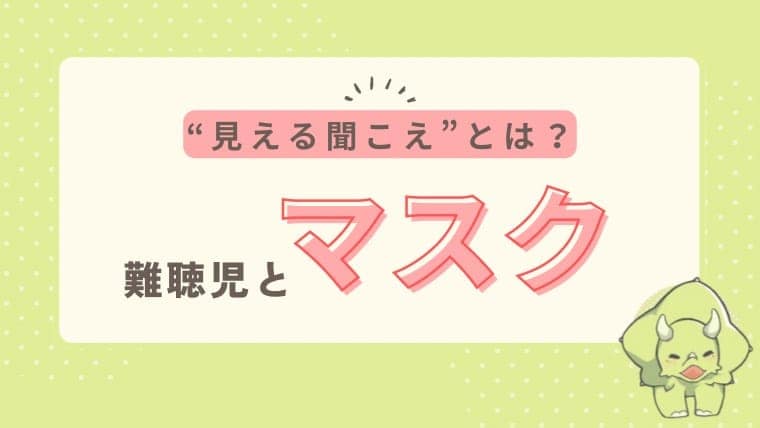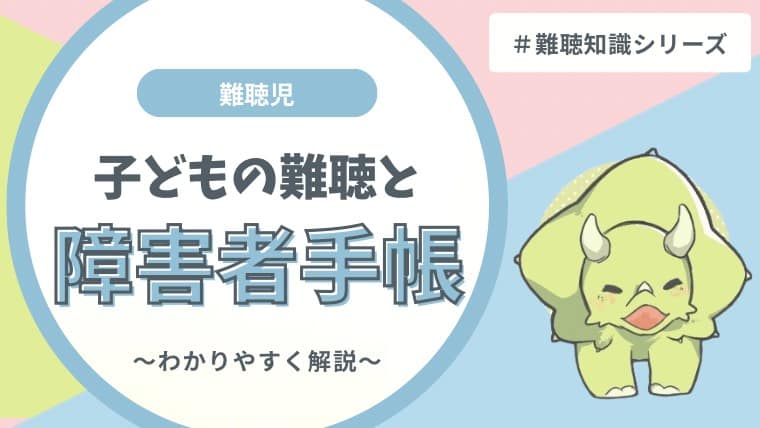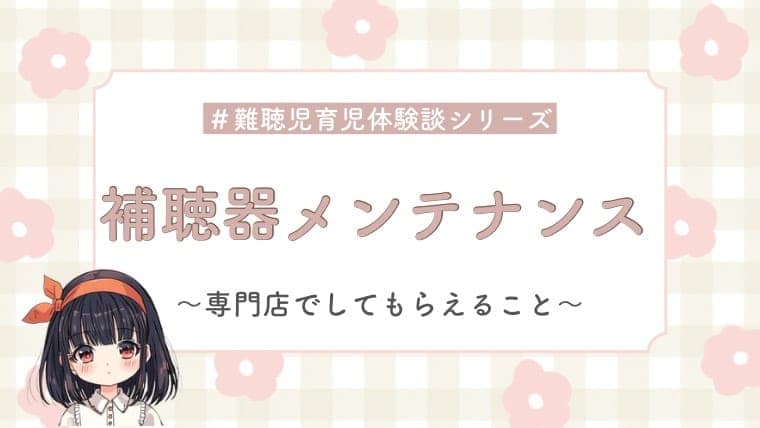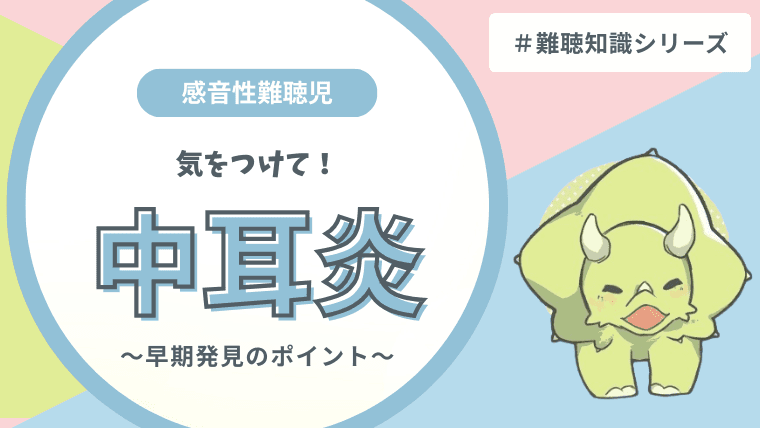難聴児が補聴器を外すとき
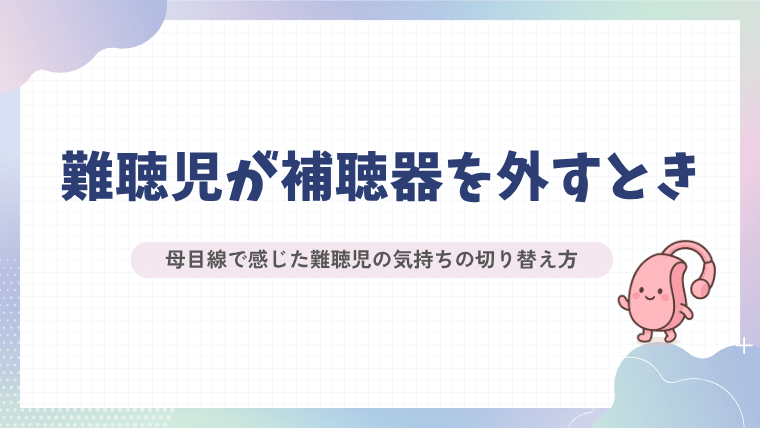
補聴器って一日中ずっと着けとくの?
「補聴器って寝るときも着けたままなの?」
「外してしまっても大丈夫?」
トリケラ家の長女とうこが補聴器を使い始めたばかりの頃、私もよくこんな疑問を抱いていました。
補聴器のおかげで音が聞こえるようになった喜びの反面、大きな音にびっくりして泣いたり、すぐに外そうとしたり。
補聴器との付き合い方には、親として悩む場面がたくさんあります。
補聴器を着け始めた頃は、「外さないこと」が目標のように感じていました。
でも、何年もそばで見てきて気づいたんです。
“外す時間”にも、ちゃんと意味があるということを。
お祭りやゲームセンターのように音があふれる場所では、娘は補聴器の電源をオフにしたり、自分で補聴器を外したりします。
それは“自分の耳を守る”ための行動。
その姿を見て、私は子どもの成長を感じるようになりました。
- 補聴器を外す時間は、子どもにとって「耳を休める大切な時間」
- ただし、外すタイミングや環境はまわりの見守りが必要
- “聞こえない時間”も、安心して過ごせるように環境を整えてあげよう
今日はそんな“補聴器を外す時間”について、
私がそばで見て、感じたことをお話ししたいと思います。
補聴器の選び方や価格の目安については、こちらの記事で解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]補聴器っていくらで買える?
https://www.triceratops-family.com/hearing-aid/385/補聴器を外す時間って必要?
「補聴器は、どんなときに外せばいいの?」
これは、補聴器を使い始めたばかりの親御さんがよく抱く疑問のひとつです。
結論から言うと──
補聴器を外す時間は「必要」です。
なぜなら、補聴器は精密機器であり、また子どもの耳を守るためにも、状況に応じて“外したほうがいい場面”があるからです。
①寝るとき
寝るときは補聴器を外します。
就寝中は汗や湿気で内部が故障する原因になるため、外して乾燥ケースに入れるのが基本です。
また、寝返りの際に耳を圧迫したり、ハウリングしたり、イヤーモールドが外れてしまったりするリスクもあります。
我が家の寝かしつけについては、こちらの記事でご紹介しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児の寝かしつけはどうする?|補聴器を外すタイミングと安心して眠るための工夫
https://www.triceratops-family.com/putting-to-bed/741/②お風呂・プールのとき
水に弱い補聴器は、防水仕様でない限り、必ず外す必要があります。
お風呂やプールのときはもちろん、洗顔やシャワーのとき、ミストシャワーにも注意が必要です。
濡れた手で触るだけでも内部に湿気が入りやすいため、しっかり乾いた手で着脱する習慣をつけると安心です。
③音が大きすぎる場所
お祭り、ゲームセンター、花火大会などの「大音量の場所」では、一時的に補聴器を外すこともあります。
補聴器を通して過剰な音が入ると、耳が痛くなったり、聞こえのバランスが崩れることがあるためです。
ただし、完全に外してしまうと周囲の声が聞こえにくくなるため、事前に「静かな場所に避難する」「少し距離を取る」などの工夫をしておくと安心です。
④ 外す時間も「経験のひとつ」
補聴器を外すことは、決して“サボり”ではありません。
「今は外したほうが心地いい」と自分で判断できるようになることも、難聴児にとって大切な成長の一歩です。
『1-3-6ルール』で補聴器に慣れる大切さ
難聴がわかったあとによく耳にするのが、「1-3-6ルール」という言葉です。
これは、生後1ヶ月で新生児聴覚スクリーニング検査、3ヶ月で確定診断、6ヶ月で介入サービス開始を目指すという流れのこと。
この時期に補聴器を着け始めることで、赤ちゃんは“音のある世界”に少しずつ慣れていきます。
まだ自分の意思で補聴器を外せない時期に、自然と音を受け入れていく──
それが、のちの言葉の発達にもつながっていくと言われています。
私自身も、娘がまだ小さかったころ、「こんなに早くから着けて大丈夫かな?」と不安に感じたことがありました。
でも、慣れてくると少しずつ“音がする安心感”が生まれ、補聴器をつけることが日常の一部になっていきました。
1-3-6ルールは、無理をさせるためではなく、『できるだけ早く音にふれさせてあげよう』という考え方です。
焦らず、親子のペースで慣れていくことが何より大切です。
1-3-6ルールの具体的な内容や、時期ごとのサポートのポイントについては、別の記事で詳しくまとめていきます。
新生児聴覚スクリーニング検査については、こちらの記事で解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]新生児聴覚スクリーニング検査って?
https://www.triceratops-family.com/newborn-hearing-screening/410/「補聴器を外すこと」にはちゃんと理由がある
補聴器を外している姿を見ると、「どうしたのかな?」と心配になることがあります。
でも、それは“イヤだから外している”わけではありません。
長く補聴器を使っている子どもほど、自分の聞こえをよく分かっているものです。
お祭りやゲームセンター、フードコートなど、音が多すぎる環境では、耳がとても疲れてしまいます。
そんなときに補聴器の電源を切ったり、補聴器を外したりするのは、「もう聞きたくない」ではなく、「ちょっと耳を休ませたい」というサイン。
私たちが大きな雑音の中で少し耳をふさぎたくなるのと同じです。
娘も、にぎやかな場所では自然と補聴器を外すことがあります。
その姿を見ると、“音の世界と自分とのちょうどいい距離”をちゃんと見つけているんだな、と感じます。
子どもが自分で「今は外したい」と思えること。
それは、補聴器との付き合い方を理解し始めた証拠だと思っています。
家での“聞こえない時間”をどう過ごす?
補聴器を外している時間は、「聞こえない時間」ではあるけれど、トリケラ家ではその時間を“ゆっくり過ごす時間”として大切にしています。
夜はお風呂に入る前に補聴器を外し、そのまま次の日のお着替えまで外したまま。
お風呂の時間、寝る前の絵本読みの時間、そして寝かしつけのゆったりした時間を、補聴器を外した状態でリラックスして過ごしています。
テレビの音や雑音のない世界で、子どもの表情や仕草、肌のぬくもりだけでつながる時間。
「聞こえない」ことを不便と感じるのではなく、安心できる静けさの中で心を休める時間になっています。
そして朝。
着替えのあとに補聴器をつける瞬間、娘にとってそれは“今日もがんばるぞ”というスイッチのようなもの。
大きな音の中で過ごす一日は、きっと私が想像する以上にエネルギーを使うはず。
それでも、自分で補聴器を手に取り、音の世界へ向かっていく姿を見ると、本当にたくましくなったなと誇らしい気持ちになります。
まとめ
補聴器を外して過ごす時間は、ただ“聞こえない時間”ではなく、心を整える時間。
その静けさの中で、娘は安心して、次の日に向けて力をためています。
朝、自分の手で補聴器をつける姿を見るたびに思います。
「今日もがんばるぞ」っていうその気持ちが、どれだけの勇気を持って生まれているんだろう、と。
外す時間があるからこそ、また着けることに意味がある。
音のある時間も、静かな時間も、どちらも大切にしながら、これからも歩んでいきたいと思います。
耳を休ませる時間に、心も一緒に休ませてあげよう!