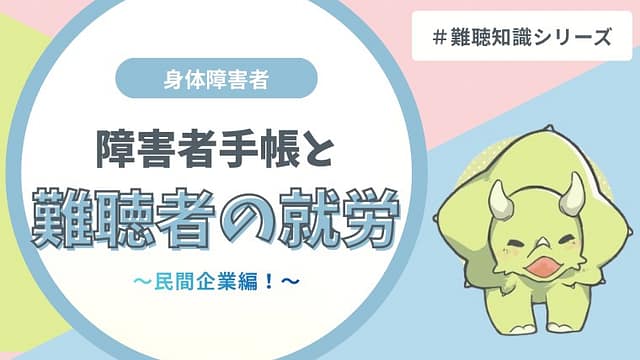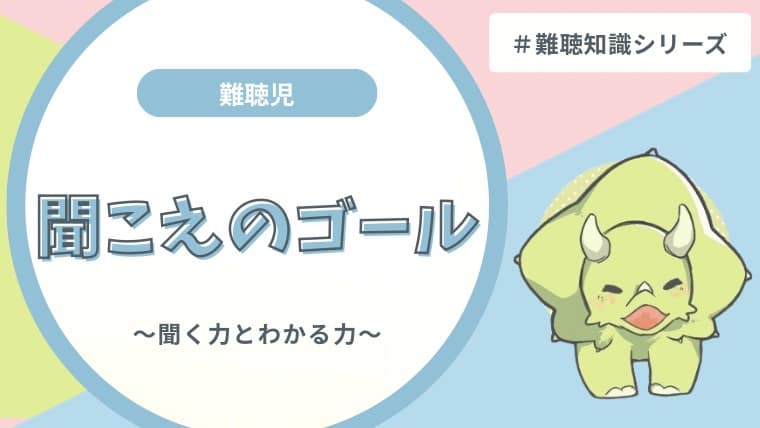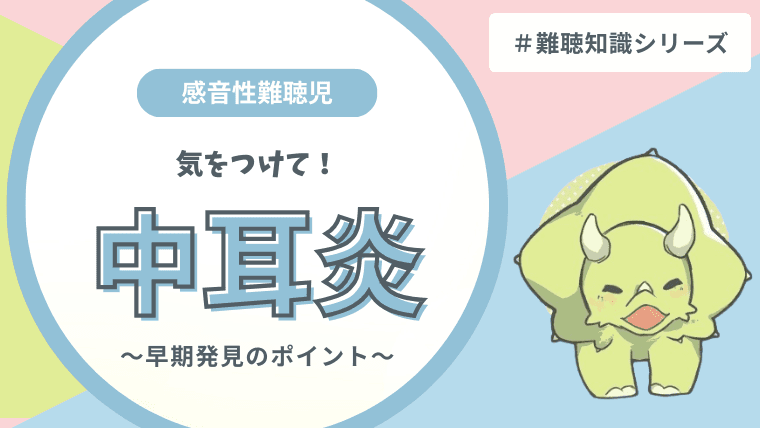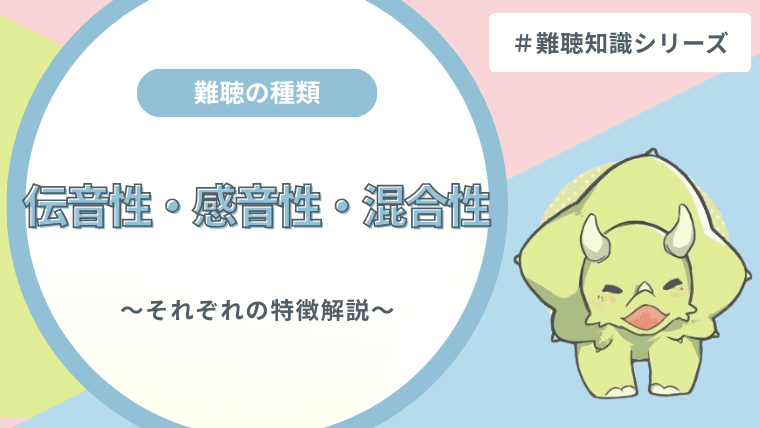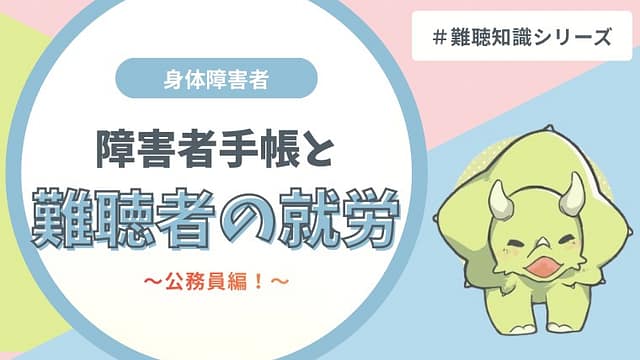難聴児小学校選び方ガイド|通級?難聴学級?ろう学校?それぞれの違いをわかりやすく解説
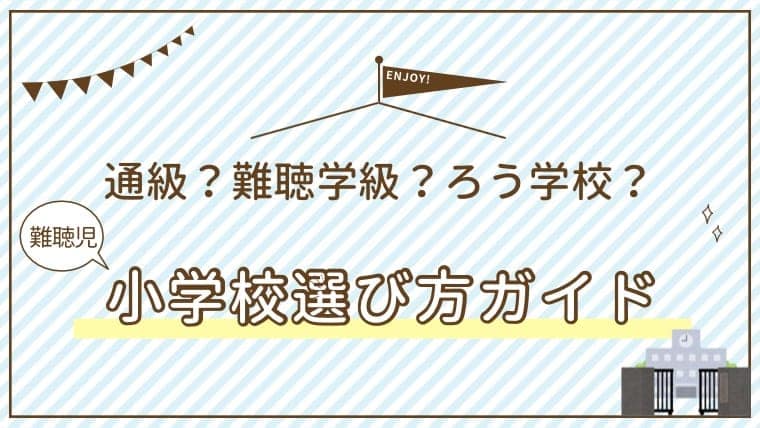

難聴がある子は地域の小学校に通えるの…?
この子が大きくなったら、小学校はどうすればいいのかしら…?
ろうではないけれど、ろう学校の方がいいのかしら…?
わが子が難聴だと分かったとき、「小学校はどうすればいいんだろう」と不安になっていませんか?まだ小さな手を握っている今は、ずっと先の話のように感じるかもしれません。でも、気づけばあっという間に就学相談の時期はやってきます。
- 普通級で大丈夫なのか。
- 難聴学級がいいのか。
- ろう学校という選択肢もあるのか。
難聴児の小学校の選び方は、多くの保護者が立ち止まる大きなテーマです。
実は、難聴児が通う小学校には大きく分けて3つの選択肢があります。なぜなら、聴力の程度だけでなく、本人の性格やコミュニケーションの方法、学びやすい環境がそれぞれ違うからです。
わたしは、中等度難聴の娘を育てる母として、就学相談から実際の小学校生活までを経験してきました。学校へ見学に行くたびに迷い、先生の話を聞くたびに揺れ、何度も「これでいいのかな」と自問しました。けれど、毎日楽しそうに小学校へ通う長女を見て、これでよかったと今は思っています。
この記事では、難聴児の小学校の選び方について、
- 地域の小学校(普通級+通級指導教室)
- 地域の小学校(普通級+難聴学級)
- ろう学校
この3つの進路の違いと判断ポイントを、体験を交えながら整理します。この記事を読むことで、 わが子に合った学びの場を見つけるための“考える軸”がきっと見えてきます。
結論からお伝えすると、 小学校選びは聴力の数値だけで決めるものではありません。本人の性格、家庭の方針、学びやすさ、安心できる環境。それらを総合的に考えることが、いちばん大切です。
小学校のことなんて、まだまだ先の話だと思っていたけれど、意外とあっという間に“その時”はやってきます。しっかり情報収集して、“その時”に備えましょう!
地域の小学校(普通級+通級指導教室)

難聴児の多くは、この地域の小学校普通級+通級指導教室というパターンです。
通級指導教室とは、普段は地域の小学校に通いながら、週に数時間だけ聞こえ方に合わせた特別な授業を受ける仕組みを指します。発音や聞き取りの練習、補聴器やロジャーの使い方などを個別に教えてもらえます。保護者が送迎する必要がありますが、地域の友達と一緒に学びながら必要な支援を受けられる点が魅力です。
ただし、通級が週1〜2時間程度と限られているため、支援の時間は短めです。先生やクラスメイトの理解がないと、環境調整が難しいケースもあります。
他にも、難聴児が普通級で学ぶ際は、ロジャーや座席配慮などの合理的配慮が重要になります。
聞こえ方や学び方にもう少しきめ細かい支援が必要な場合は、2つ目の「地域の小学校(普通級+難聴学級(特別支援学級))」を選ぶケースもあります。
地域の小学校(普通級+難聴学級)

先ほどのパターンと少し似ているけれど、もう少しきめ細かい支援が必要な場合は、この普通級+難聴学級のパターンもあります。
難聴学級とは、聴覚に配慮した少人数の特別支援学級で、聞こえのサポートを受けながら子どものペースに合わせて学べる環境を指します。
通常の授業より静かな環境で、先生がロジャーや補聴器を活用しながら一人ひとりの聞こえ方に合わせて授業を進めます。言葉の練習や発音指導、補聴機器の管理なども行われるため、理解の定着がしやすいです。
ただし、在籍人数が少なく学級間で交流の機会が限られることがあります。地域によっては難聴学級が設置されていない場合もあるため、事前の確認が必要です。
トリケラ家の長女・とうこは、このパターンで、地域の小学校に通いながら、普通級+難聴学級に在籍しています。交流学級(普通級)で過ごす時間も多く、聞こえに配慮された環境の中で、友達との関わりも大切にしながら学んでいます。
実際にとうこが小学校の普通級と難聴学級でどのような支援を受けているのかについては、また別の記事で解説予定です。
ろう学校(聾学校)

ろう学校は、聞こえに課題のある子どもが通う学校です。
以前は「ろうの子または重度の子が行く場所」というイメージがありました。しかし実際には、聴力の程度に関わらず、その子に合った学び方を大切にしています。
聞こえに頼らず、手話や筆談などの視覚的な方法で学ぶのが大きな特徴です。授業中は先生も手話や口話を使い分けながら、一人ひとりのコミュニケーション方法に合わせて丁寧に教えます。
手話や視覚的支援が充実しており、聞こえに悩むことなく自然体で過ごせる環境が整っています。同じ立場の友達と出会えることで、自己肯定感を育みやすい点も魅力です。
ただし、おおよそ都道府県に1箇所しか学校がないため、通学距離が長くなるケースがあります。地域の友達との関わりが少なくなることや、地域の小学校とのカリキュラムに違いがあることも考慮すべき点です。
中等度難聴の子でもろう学校に通うことがあります。聞こえの数値よりも、「どんな環境なら安心して学べるか」「どんな伝え方が自分に合うか」を大切にして、家庭と学校が話し合いながら決めていくケースが多いです。
難聴児の小学校の選び方|聴力だけで決めていいの?
なぜなら、同じ聴力レベルでも、本人の性格やコミュニケーションスタイル、家庭の方針によって最適な環境が異なるからです。聴力以外に考慮すべきポイントは以下の通りです。
本人の性格とコミュニケーションスタイル
積極的に友達と関わりたいタイプなのか、少人数でじっくり学びたいタイプなのか。本人がどんな環境で安心できるかを観察することが大切です。
補聴器やロジャーを使って聞き取ることに抵抗がないか、手話でのコミュニケーションを好むかなども判断材料になります。
家庭の教育方針
地域の友達と一緒に育ってほしいのか、聴覚障害のある仲間との出会いを大切にしたいのか。家庭の価値観も進路選択に影響します。
通学の負担や送迎の可否も現実的な判断要素です。
学校の支援体制
ロジャーや座席配慮などの合理的配慮が受けられるか、先生の理解があるかなど、実際の支援体制を確認することが重要です。
見学や体験入学を通じて、学校の雰囲気や先生の対応を肌で感じることをおすすめします。
難聴児の就学相談はいつから?スケジュールの目安
難聴児の小学校選びでは、早めの情報収集(就学相談)が大切です。
就学相談は通常、入学の前年度(年長の春〜夏頃)から始まります。自治体によってスケジュールが異なるため、早めに確認しておくことが重要です。
具体的なスケジュールの目安は以下の通りです。
自治体の教育委員会に就学相談の申し込みを行います。この時期に学校見学や体験入学の情報も集めておくとよいでしょう。
難聴学級や通級指導教室の有無、ろう学校の所在地なども確認します。
就学相談の面談や検査が行われます。本人の様子や家庭の希望を伝える大切な機会です。並行して、候補となる学校の見学や体験入学に参加することをおすすめします。
就学先の決定通知が届きます。入学説明会に参加し、具体的な配慮事項を学校と相談します。余裕を持って準備を進めるためにも、早めの行動が安心につながります。
このブログでは、これよりさらに早い「年中から就学相談へ向けて動き出すこと」をおすすめしています。詳しくはこちらの記事で解説しています。
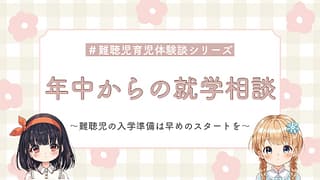
難聴児が小学校で受けられる合理的配慮とは
難聴児が普通級で学ぶ際は、合理的配慮が重要な役割を果たします。合理的配慮とは、障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受けられるよう、学校が行う調整や支援のことです。
難聴児が小学校で受けられる主な合理的配慮は以下の通りです。
聞こえに関する配慮
ロジャー(FM補聴システム)の使用許可と充電環境の整備が挙げられます。教室の前方や窓側など、音が聞き取りやすい座席への配置も有効です。
騒音を減らすため、机や椅子の脚にテニスボールをつけるなどの工夫も行われます。
授業に関する配慮
先生が口の動きが見えるよう、マスクを外して話す、またはフェイスシールドを使用することがあります。重要な指示は視覚的に示す(黒板に書く、プリントで配布する)工夫も効果的です。
聞き逃しがあった場合のフォロー体制を整えることも大切です。
周囲の理解促進
クラスメイトに難聴について説明する機会を設けることで、理解と協力を得やすくなります。先生や支援員への研修実施も、適切な支援につながります。
合理的配慮は学校と保護者が話し合って決めるものです。遠慮せずに必要な配慮を伝えることが、子どもの学びやすさにつながります。
難聴児の小学校選びで後悔しないためのチェックポイント
パンフレットや説明だけでは分からない雰囲気や、先生の対応、子どもたちの様子を確認することで、わが子に合うかどうかが見えてきます。
後悔しないために確認すべきポイントは以下の通りです。
学習環境を確認する
教室の音環境(反響や騒音の程度)をチェックします。難聴学級がある場合は、実際の授業の様子や在籍人数も確認しましょう。
先生の難聴への理解度や、ロジャーなどの支援機器への対応姿勢も重要な判断材料です。
難聴児本人の反応を大切にする
可能であれば、子ども本人を連れて学校を訪問します。子どもが「ここに通いたい」と感じられるかどうかは、最も大切な判断基準の一つです。
体験入学や交流会に参加すると、より具体的なイメージが持てます。
通学の現実性を考える
通学時間や経路、送迎の必要性など、日常的に続けられるかどうかを確認します。特にろう学校や遠方の難聴学級を検討する場合は、家族の負担も考慮すべきです。
兄弟姉妹がいる場合は、送迎のスケジュール調整も現実的な問題になります。
先輩保護者の話を聞く
同じ学校に通う難聴児の保護者から話を聞くことで、実際の支援内容や学校の対応が分かります。難聴児の親の会やSNSのコミュニティも情報源として活用できます。リアルな体験談は、判断の大きな助けになります。
難聴児の小学校の選び方に「正解」はある?
難聴児の小学校選びに、万人に共通する正解はありません。なぜなら、子どもの聴力、性格、コミュニケーションスタイル、家庭環境はそれぞれ異なるからです。ある子にとって最適な環境が、別の子には合わないこともあります。
わたしも娘の進路を考え始めたときは、どんな学校があるのか、どうやって決めるのか全然分からず不安でいっぱいでした。しかし実際に見学に行って、先生の話を聞いたり、通っている子どもの様子を見たりするうちに、「この子にはこの環境が合っているかも」と思える瞬間がありました。
どんな選択をしても大丈夫です。それぞれの学校には、それぞれの良さがあります。
子どもの特性や家庭の希望、通学のしやすさ、先生や支援体制など、たくさんの要素を少しずつ比べながら決めていくことが大切です。悩んで迷った時間も、きっとお子さんを理解するための大事なステップになります。
まとめ|安心して学べる環境を探そう!
わたしも、長女とうこの進路を考え始めたときは、「どんな学校があるのか」「どうやって決めるのか」全然分からず、不安でいっぱいでした。
でも実際に見学に行って、先生の話を聞いたり、通っているお子さんの様子を見たりするうちに、“この子にはこの環境が合っているかも”と思える瞬間がありました。
どんな選択をしても大丈夫。それぞれの学校には、それぞれの良さがあります。
難聴のある子どもの学校選びに「これが正解!」という形はありません。
どんな選択をしても、いちばん大切なのは「その子が安心して学べる環境かどうか」。悩んで迷った時間も、きっとお子さんを理解するための大事なステップになります。
とうこが小学校に入学した際、わたしが実際に小学校に対してお願いしたことについては、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。


お子さんにとって安心できる学びの場が見つかりますように!