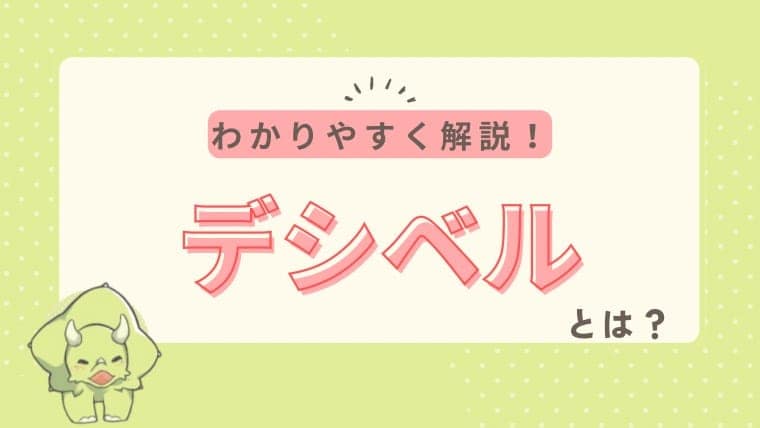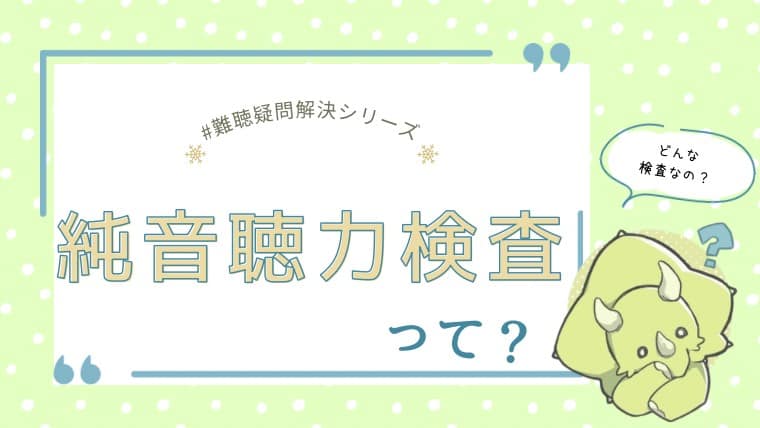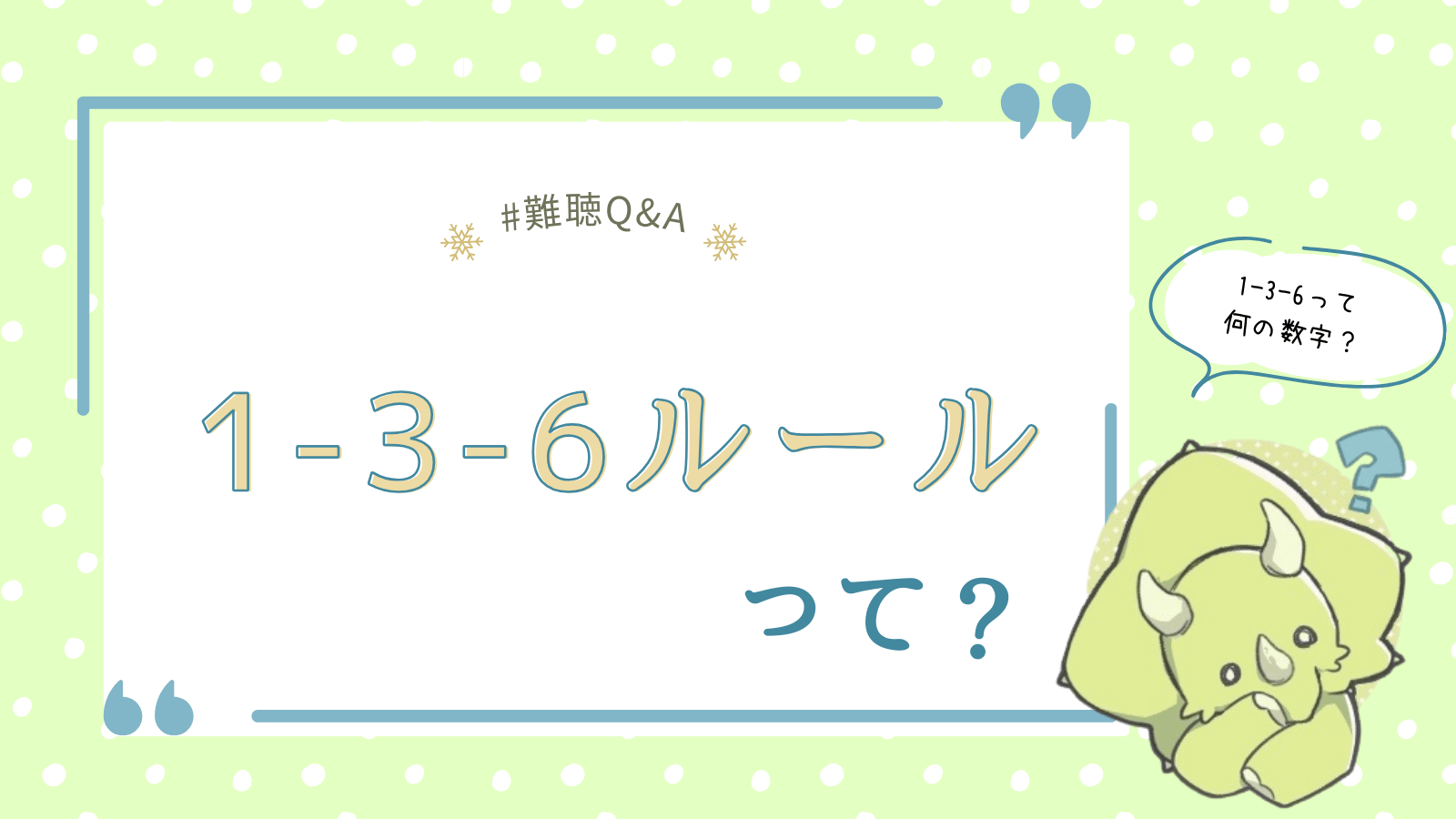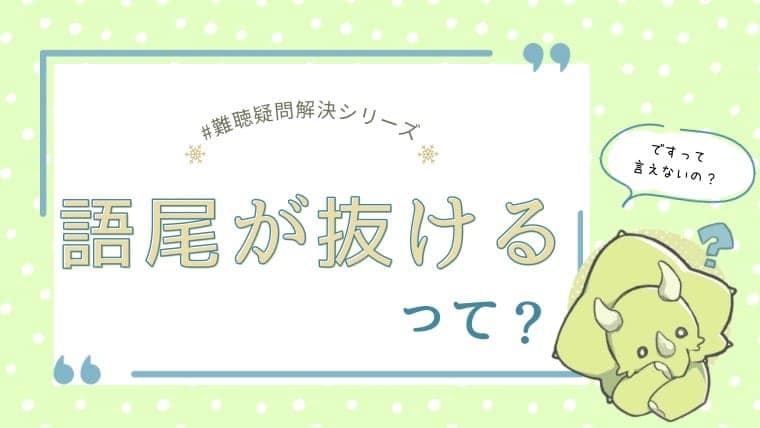新生児聴覚スクリーニング検査って?
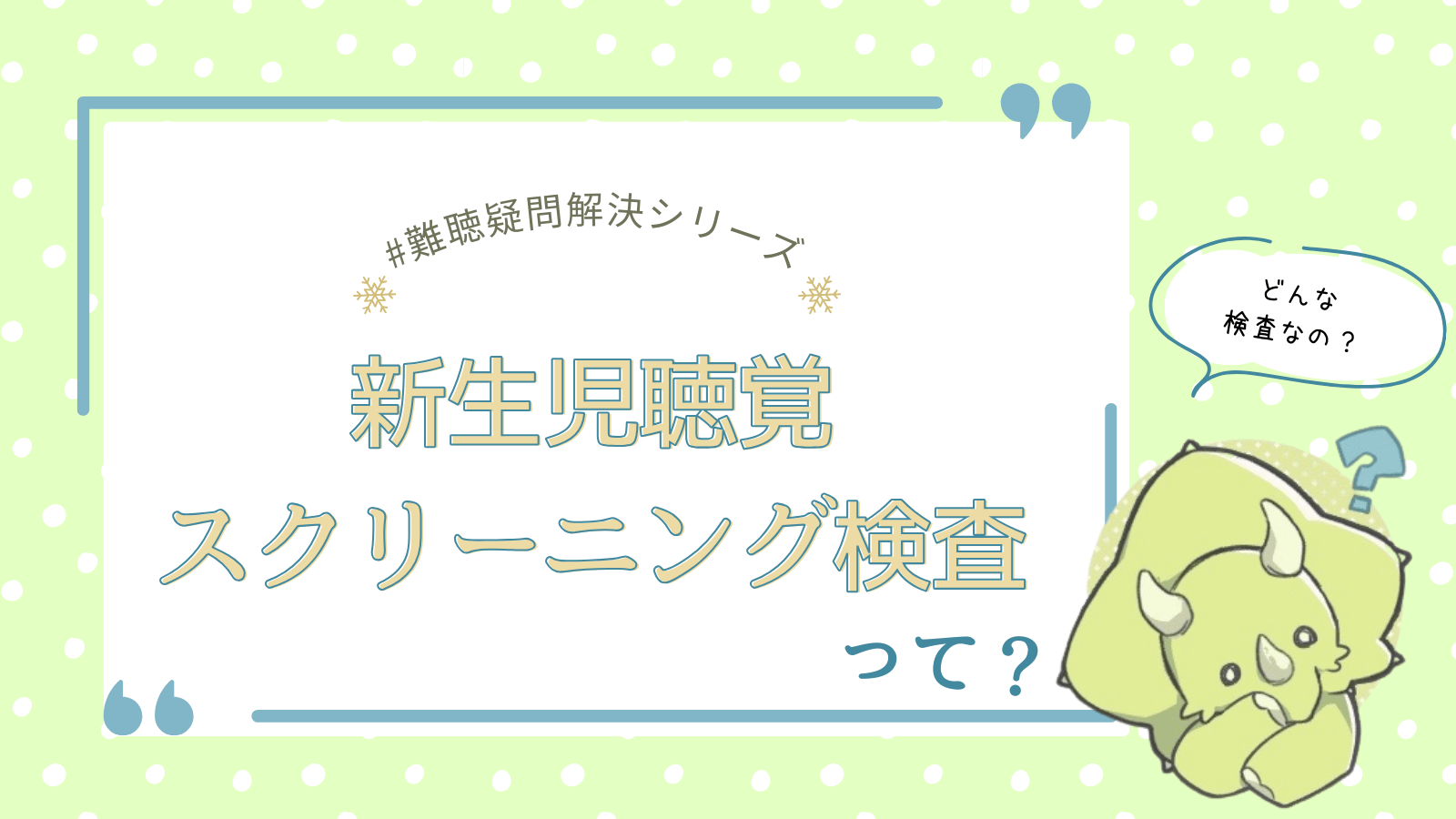
みなさんは新生児聴覚スクリーニング検査という名前をご存じでしたか?
私は、赤ちゃんを産むまでこんな検査があるなんて知りませんでした。
新生児聴覚スクリーニング検査は、難聴の可能性がある子をスクリーニングする(ふるいにかける)大事な検査です。
- 新生児聴覚スクリーニング検査は、耳が聞こえにくい可能性のある赤ちゃんをふるいにかける重要な検査
- 約9割の赤ちゃんは「パス」となるが、「リファー」であっても難聴が確定するわけではなく、数週間後の再検査で確認できる
- この検査によって早期に難聴に気づくことができれば、適切な支援や療育をいち早く始めることができる
産院で「今この時期しかできない大切な検査ですよ」と説明を受け、費用はかかるけれど、「この子のために、有料でも受けられる検査は全部受けよう」と思って同意書にサインをしました。
今思うのは、あのとき受けると決めた自分に、本当に感謝しています。
なぜなら、結果的に娘は難聴だったから。
見落とさずに済んで、本当によかった。
あのとき検査を受けていたからこそ、早期に支援を始めることができたんです。
どんな検査なの?
検査は、生まれてからすぐの赤ちゃんが眠っているあいだに行われます。
小さなイヤホンのような機械を耳にあてて、音を聞かせ、そのときの反応を調べます。
赤ちゃんに痛みはまったくなく、数分で終わる検査です。
耳の中の反応を見る「OAE」という方法と、脳の反応を調べる「AABR」という方法がありますが、どちらも赤ちゃんに負担はありません。
退院前に行う病院が多く、“聞こえ”のチェックとして最初にできる大切なステップです。
OAE(耳音響放射検査)とは?
赤ちゃんの『内耳(ないじ)=音を感じ取る“かたつむりの形の部分”』が、音に反応して“小さな音”を返す性質を利用した検査です。
小さなイヤホンのような機械を耳の穴にそっと入れて、「ピッ」「ポッ」といった音を聞かせると、内耳がその音に反応して“反射音”を返します。
その反応音が機械で確認できれば「音を感じ取れている=パス」という結果になります。
- 痛くない(耳に軽くあてるだけ)
- 数分で終わる
- 赤ちゃんが眠っていても検査できる
AABR(自動聴性脳幹反応検査)とは?
AABR(エーエービーアール)は、耳から入った音が、脳にきちんと届いているかを調べる検査です。
赤ちゃんが眠っているあいだに、耳にイヤホン、そして頭やおでこなどに小さなシール状の電極をつけて行います。
この電極で、音を聞いたときの脳の反応(電気信号)をキャッチするんです。
痛みはまったくなく、イヤホンを通して「ピッピッ」という音を聞かせて、そのときの脳の反応を機械が自動で測定します。
- 耳だけでなく「脳の反応」まで確認できる
- より正確に“聞こえ”をチェックできる
- 赤ちゃんが眠っていても検査できる
結果の見方:「パス」と「リファー」
検査の結果は、「パス(検査時点で異常なし)」か「リファー(再検査が必要)」の2択で示されます。
「パス」とは、“聞こえに問題がないと考えられる”という意味で、ほとんどの赤ちゃんが「パス」になります。
一方で、「リファー」と書かれることがあります。
これは“もう一度くわしく検査をしましょう”という合図のようなもの。
決して「難聴が確定した」ということではありません。
実は、生まれてくる赤ちゃんのうち、約1,000人に1〜2人の割合で、生まれつき聞こえにくさがあるといわれています。
決して特別なことではなく、どの赤ちゃんにも起こりうることなんです。
また、生まれたばかりの赤ちゃんは、耳の中に羊水が残っていたり、検査のときに動いたり泣いたりしていたりすると、うまく音の反応が取れないこともあります。
そのため、リファー=聞こえにくい可能性があるという段階。
多くの場合、数週間後に再検査(確認検査)を行い、もう一度、落ち着いた状態でチェックします。
トリケラ家の場合
わたしの娘も“リファー”でした。
その言葉を聞いた瞬間、頭の中が真っ白になって、「どうしよう」「何か悪かったのかな」と不安でいっぱいでした。
でも今振り返ると、早く気づけたことが本当によかった。
あのとき検査を受けていたからこそ、早い段階で支援につなげることができました。
生後3ヶ月で確定診断を受けた後、大学病院での療育を開始し、生後4ヶ月で補聴器のイヤーモールドの型取り、生後5ヶ月で補聴器装用開始、この頃ろう学校の幼稚部の乳幼児相談へ通い始めました。
1-3-6ルールの通りにとうこの支援を始められたのは、間違いなく新生児聴覚スクリーニング検査のおかげです。
リファーになったらどうすればいい?
「リファー」と言われたとき、まず大切なのは焦らないことです。
リファーは“聞こえにくさの可能性がある”という段階であり、次にすることは再検査を受けることです。
ただ、再検査まで1ヶ月ほど期間が空くこともあります。
その間、
「難聴 可能性」
「新生児聴覚スクリーニング検査 リファー」
「難聴 どうすれば」
そんな言葉で検索して、同じように不安になるママも多いと思います。
私もその一人でした。
けれど、検索の答えは人それぞれ。
大事なのは、“結果が出るまでの時間”をどう過ごすかです。
赤ちゃんへの語りかけやスキンシップをいつも通り大切にして、結果を待ちながら、赤ちゃんとの時間を少しでも穏やかに過ごせるといいですね。
再検査では、もう一度OAEやAABRを行い、必要に応じて、専門機関でより詳しい検査(ABR検査など)を受ける流れになります。
ほとんどのケースでは、再検査で「問題なし」となることも多いので、どうか一人で抱え込まず、落ち着いて確認していきましょう。
再検査でまたリファーになった場合は、その子が難聴である可能性を視野に入れて、情報収集を開始しましょう!
検査結果の受け止め方に悩んだ場合は、こちらの記事も読んでみてください。
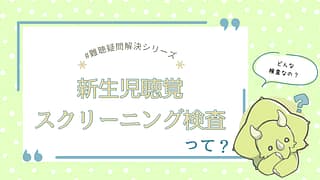
まとめ
新生児聴覚スクリーニング検査は、生まれたばかりの赤ちゃんにとって、「聞こえ」を確かめる最初の大切なステップです。
もし“リファー”だったとしても、それは「もう少し詳しく見てみよう」というお知らせ。
焦らず、ゆっくり確認していけば大丈夫。
早く気づけたぶん、きっとその子に合ったサポートを始められます。
私もあの頃は不安でしたが、再検査を待つあいだにできることは、赤ちゃんといつも通りコミュニケーションをとることを意識していました。
結果的にお子さんが難聴でも、難聴じゃなくても、どうか今、目の前にいるかわいい我が子との毎日を楽しんでください。