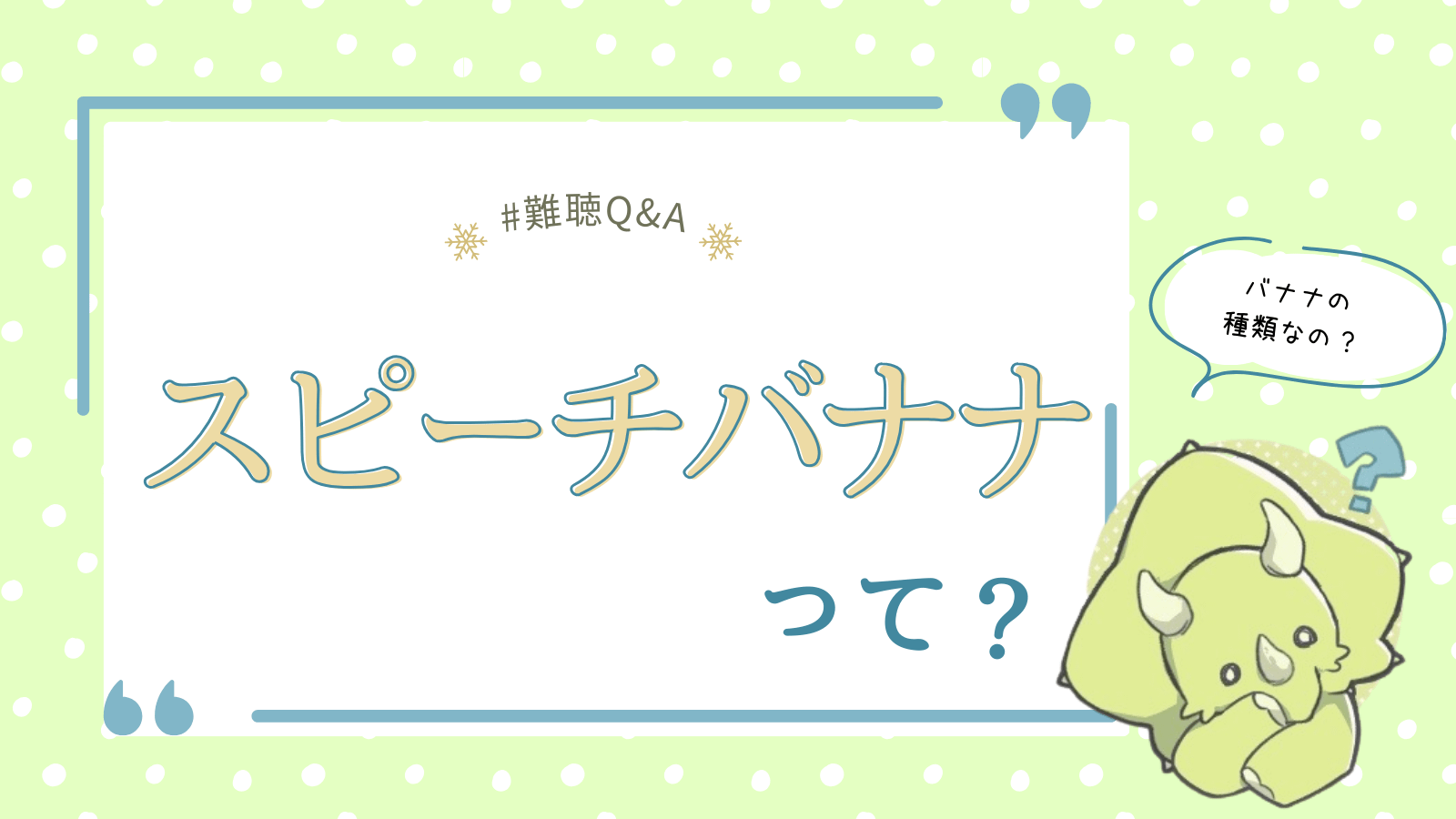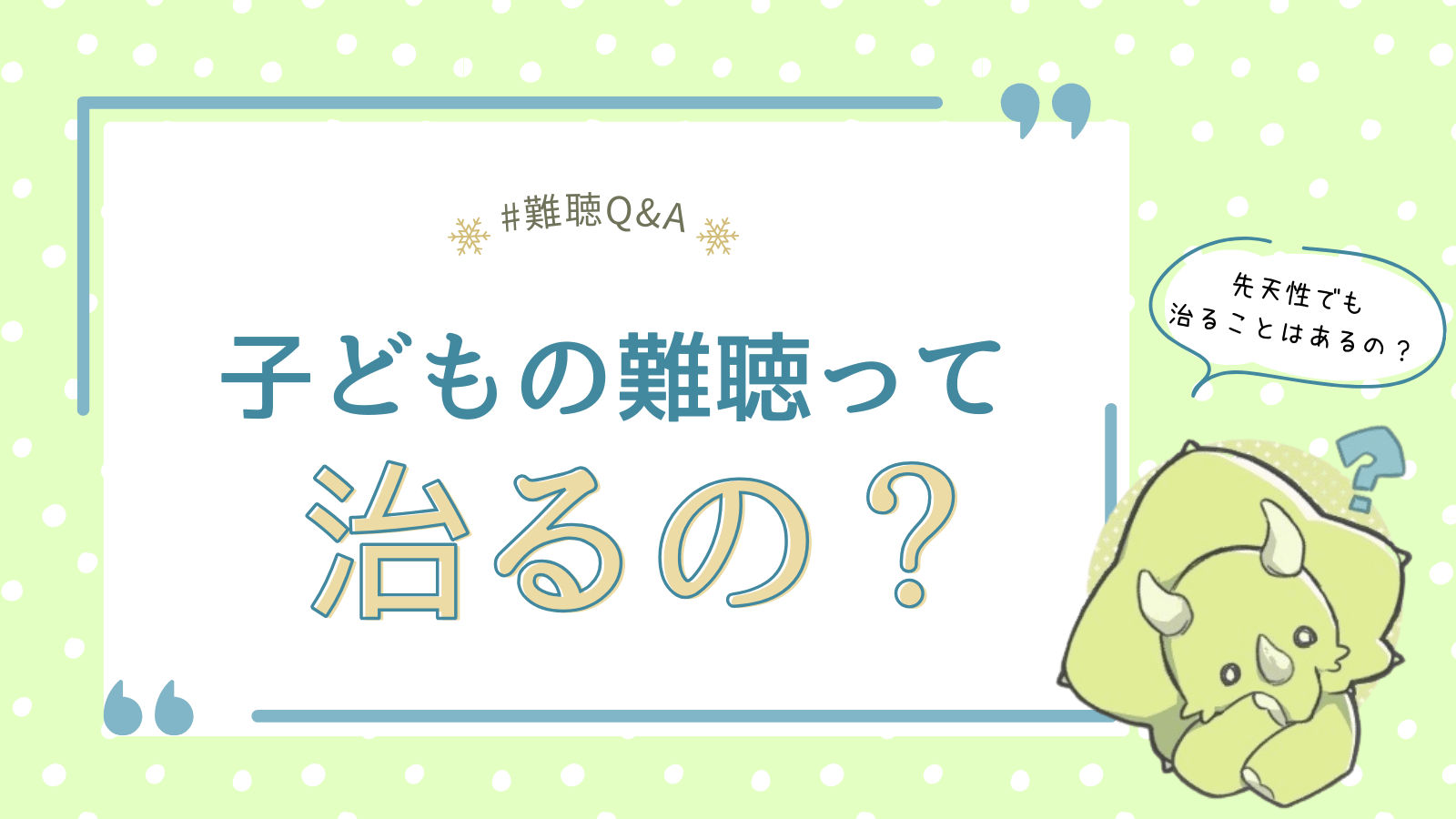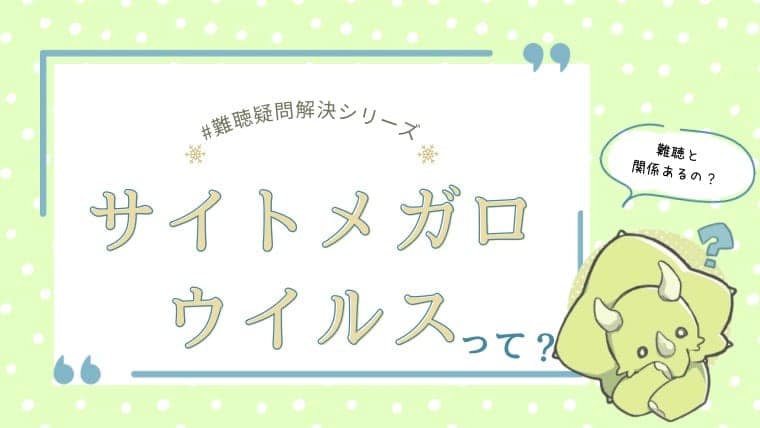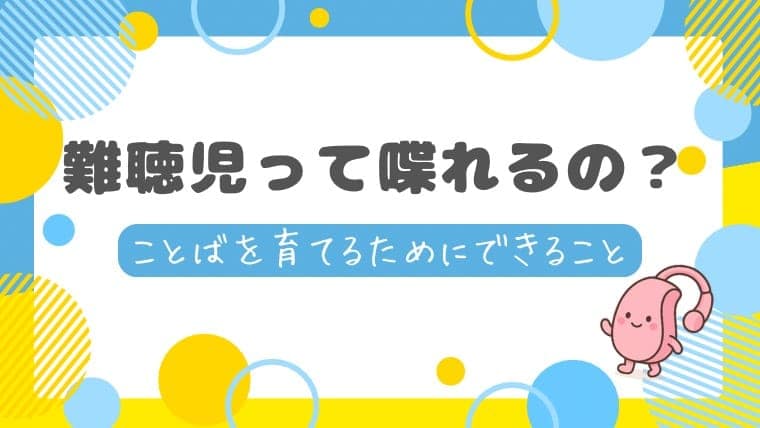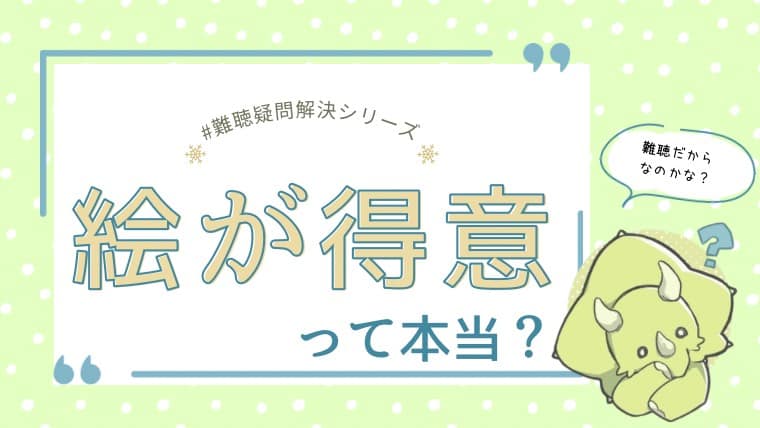ムンプス難聴とは?おたふく風邪の後に起こる“まれな聴力低下”
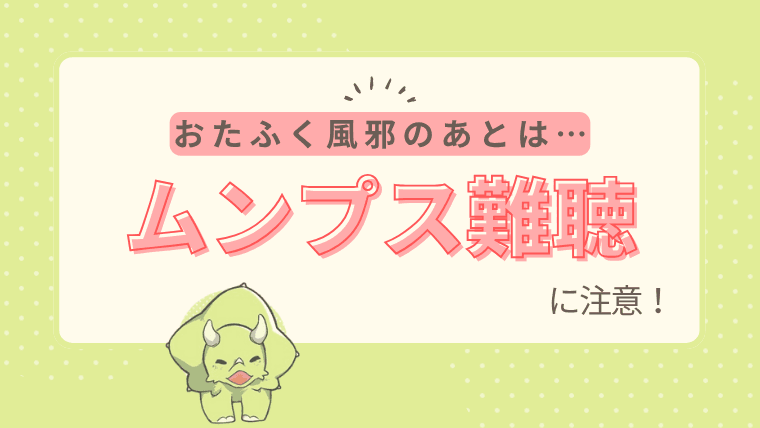
子どもの“おたふく風邪”、いわゆるムンプス。実はこのウイルス、まれに「聞こえ」に影響を及ぼすことがあるのを知っていますか?
ムンプスウイルスが内耳に入り込むと、「ムンプス難聴」と呼ばれる感音性難聴を引き起こすことがあります。ほとんどが片耳だけの発症ですが、いったん起きると回復が難しいことが多いと言われています。
我が家の子どもたちはすでに難聴があるので、「さらにムンプス難聴にもなったら…」と思い、予防接種をきちんと受けています。特に、聞こえに不安のある子どもにとって“二次的な聴力の低下”は大きな影響があるからです。
この記事では、ムンプス難聴の基本をやさしく解説します。
- ムンプス難聴は、発症はまれだが、いったん発症すると治りにくい
- 多くは片耳のみで起こるため、気づかれにくい
- ワクチン接種で予防が可能
- 聞こえに不安のある子ほど、早めの予防と日常の観察が大切
ムンプスって何?どうして難聴につながるの?
おたふく風邪(ムンプス)は、ムンプスウイルスというウイルスに感染して起こる病気です。耳の下にある「耳下腺(じかせん)」が腫れるのが代表的な症状で、ほっぺがぷっくりふくらむ姿から“おたふく”と呼ばれています。
ほとんどの場合は発熱や腫れが数日でおさまり、後遺症も残らずに回復します。
けれど、まれにウイルスが体の奥——特に“内耳”と呼ばれる部分に入り込み、「感音性難聴」を引き起こすことがあります。これを「ムンプス難聴」と呼びます。
感音性難聴とは、音を電気信号に変えて脳へ送る仕組みのどこかに障害が起きることで、音は届いているのに「脳まで正しく伝わらない」状態です。
ムンプスウイルスは、耳の奥にある蝸牛(かぎゅう)という器官や聴神経に炎症を起こし、そこがダメージを受けてしまうのです。
この難聴は、片耳だけに起こることが多く、突然発症します。本人が「聞こえない」と言わない限り気づきにくく、発見が遅れることも。
しかも、一度起きると自然に治ることは少ないと言われています。
だからこそ、「おたふく風邪=軽い病気」と思い込まず、もし感染したあとに聞こえ方が変わったように感じたら、早めに耳鼻科を受診することが大切です。
感音性難聴などの難聴の種類については、こちらの記事で解説しています。
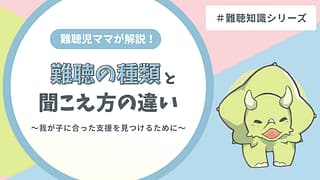
ムンプス難聴と中耳炎の違い(聞こえにくさの見分け方)
「聞こえにくい」といっても、原因によって感じ方やサインが少し違います。
ムンプス難聴は、内耳(神経の部分)の障害。
中耳炎は、中耳(鼓膜の奥にある空間)の炎症です。
| 比較項目 | ムンプス難聴 | 中耳炎 |
|---|---|---|
| 原因 | ムンプスウイルスが内耳・聴神経に感染 | 細菌やウイルスが中耳に感染 |
| 発症タイミング | おたふく風邪の腫れや熱が落ち着いた後に突然 | 風邪のあとなどに発症することが多い |
| 痛み | ほとんどなし | 耳の痛み・熱・夜泣きが増えるなど |
| 聞こえ方 | 片耳だけ急に聞こえにくい/方向感が分からない | 両耳または片耳が詰まったようにこもる感じ |
| 治りやすさ | 回復が難しい(治療しても改善しにくい) | 多くは治療で改善する |
| 確認方法 | 聴力検査・内耳の反応を見る検査(ABRなど) | 耳鏡で鼓膜を見る・滲出液の有無を確認 |
もし子どもがおたふく風邪になったら、聞こえをどうチェック?
おたふく風邪にかかったあと、熱が下がっても“聞こえ”の様子を観察することが大切です。ムンプス難聴は発症が数日〜数週間後になることもあります。
家で気づけるサイン
- 呼びかけに反応しにくくなった
- テレビの音量を上げるようになった
- 片方の耳を向けないと会話がしづらそう
- 音のする方向が分からなくなった
- 集中しているときに声をかけても気づかない
こうしたサインが見られたときは、早めに耳鼻咽喉科で聴力検査を受けましょう。
受診の目安
- 発熱や腫れが治まってから数日後に聞こえづらさが出た
- 痛みはないのに呼びかけに反応しない
- 片方の耳をふさぐと聞こえにくいと訴える
学校や園でも、話しかけた方向によって反応が違うなどの変化が見られたら要注意。家庭と連携しながら「聞こえの変化」に気づけると安心です。
万が一、聞こえにくさが残った場合は、補聴器の活用や療育などでの支援を検討していきましょう。
補聴器の価格などについては、こちらの記事で解説しています。
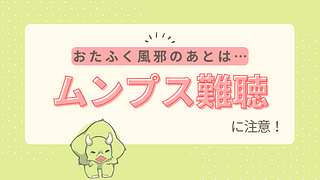
予防がいちばんの安心材料 ― おたふく風邪ワクチンの大切さ
ムンプス難聴はまれとはいえ、発症すると回復が難しいといわれています。
だからこそ、できる予防はしておきたいところ。その中心となるのがおたふく風邪ワクチンです。
日本では任意接種ですが、ワクチンによって感染リスクを大きく減らせることがわかっています。
いつ接種するの?
- 1歳ごろに1回+年長時に追加接種(2回でより効果的)
- 母子手帳で接種記録を確認
- 自治体によって助成制度がある場合も
難聴のある子にとっては特に大切
すでに聞こえに課題がある子にとって、「残っている聴力を守ること」はとても大切です。
わたしは子どもたちのムンプス難聴り患だけは絶対に避けたいと思い、子どもたちのおたふく風邪ワクチンを迷わず受けました。予防接種という“守れる選択肢”を知っておくことが、安心につながります。
まとめ
おたふく風邪は多くの子が自然に治りますが、まれに「ムンプス難聴」という後遺症が起こることがあります。
多くは片耳で起こり、痛みがないため気づかれにくいものの、早く気づけば支援につなげることができます。
そして、ワクチンによる予防が可能です。
すでに難聴のある子どもも、そうでない子も、「聞こえを守るためにできること」を知っておくことで、より安心して成長を見守れます。
ムンプス難聴は、怖い話ではなく「知ることで防げる話」。今日知ったこの知識が、誰かの聞こえを守るきっかけになりますように。