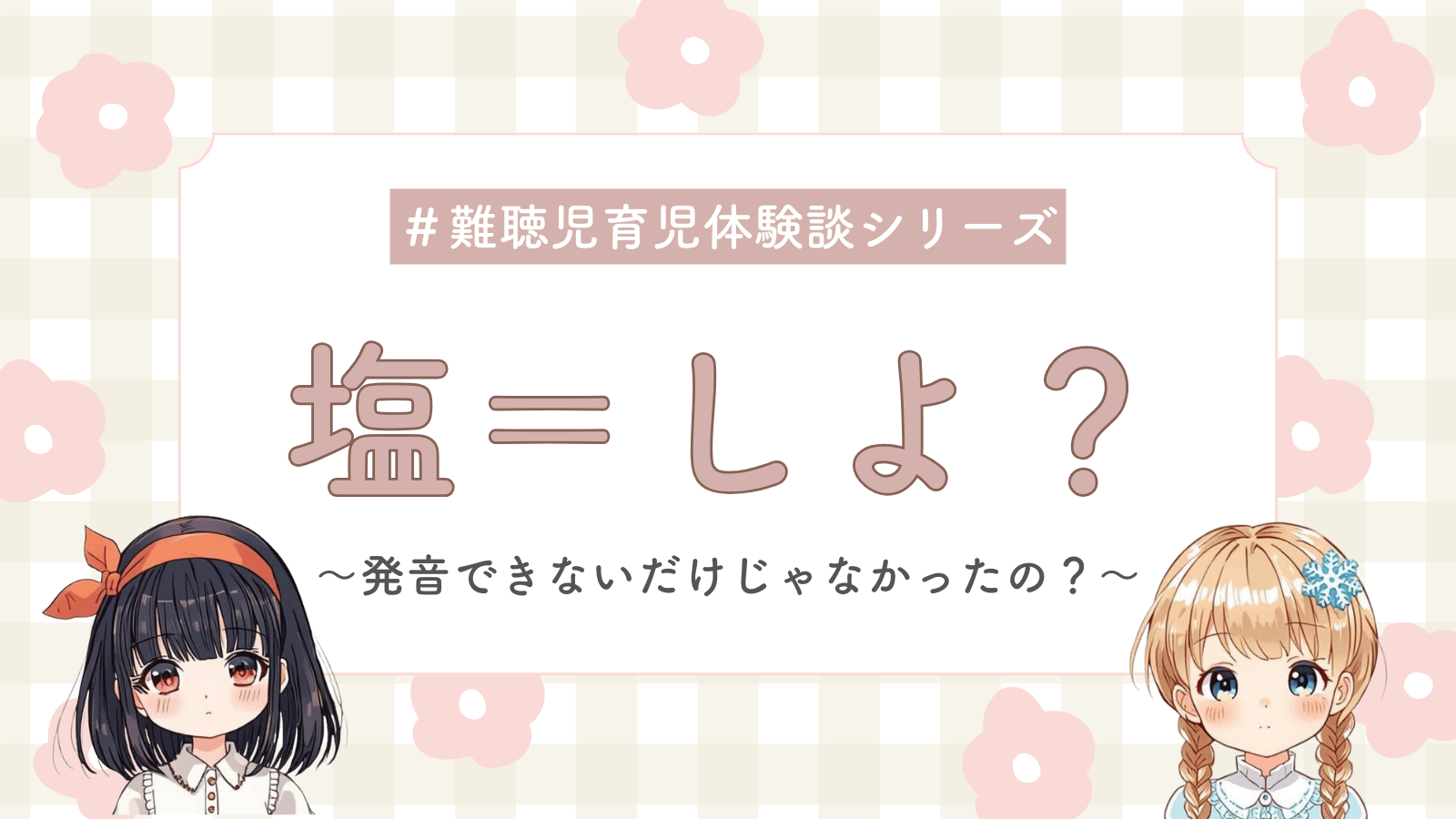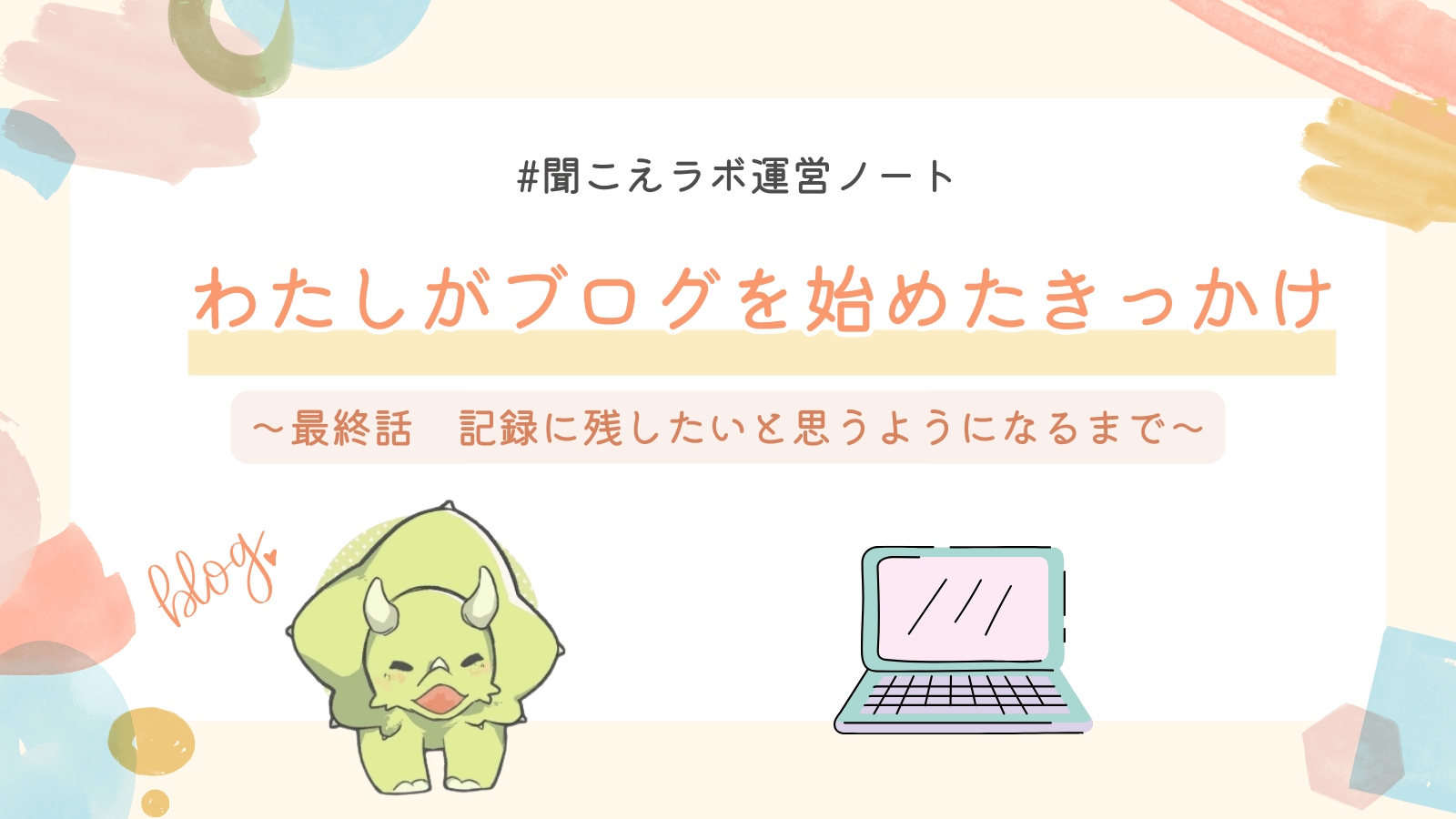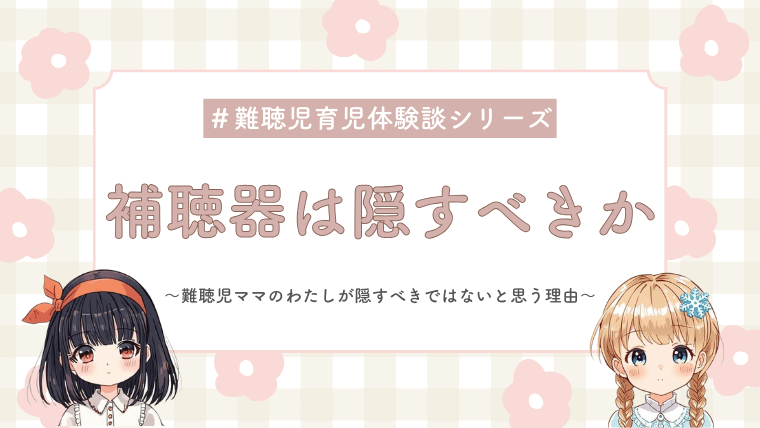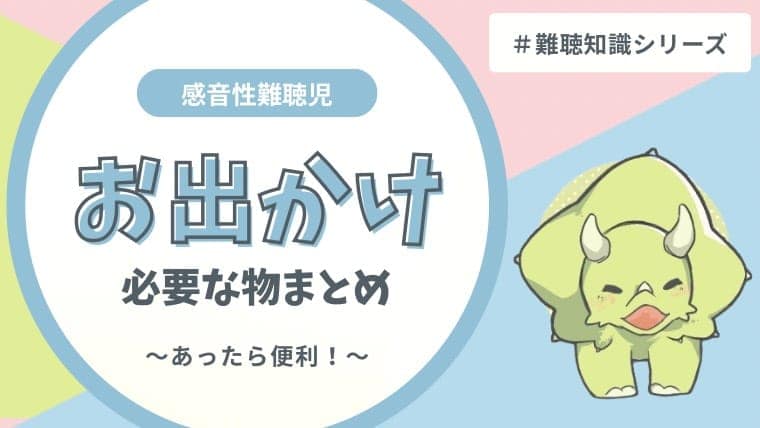ろう学校の乳幼児相談ってどんなところ?実際に行って感じたことまとめ
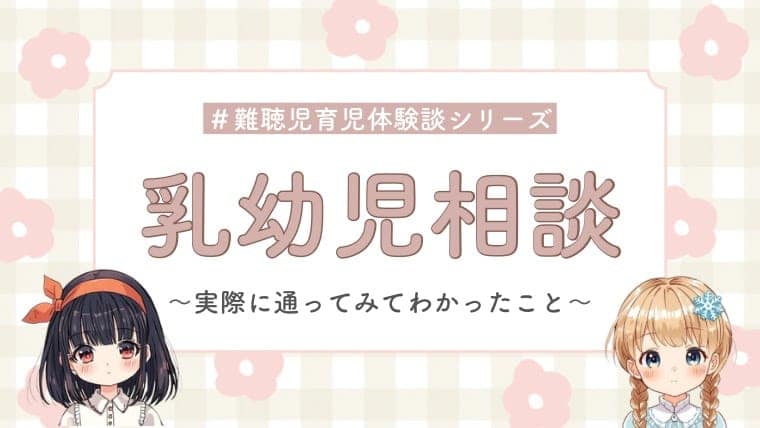
わたしが「ろう学校の乳幼児相談」という場所の存在を知ったのは、娘の難聴が確定した日のことでした。
病院の先生から「こんなところがありますよ」と、一枚の案内を手渡されたのがきっかけです。
そこには、“難聴のあるお子さんやご家族が相談できる場所です”と書かれていました。
半信半疑のまま電話をかけると、優しい女性の先生が出てくださいました。
「実は、娘が難聴と診断されて……」と話し始めた途端、いろいろな思いが溢れてわたしは涙が止まらなくなりました。
わたしが落ち着くようにゆっくりと電話の向こうで先生は静かにこう言いました。

お母さん、大丈夫ですよ。ここにはいつでも来ていいんです。一緒にとうこちゃんの難聴のことを学んでいきましょうね。
その言葉に、胸の奥がふっと軽くなったのを今でも覚えています。
──今日は、そんな“ろう学校の乳幼児相談”について、実際に行って感じたことをお話しします。
- ろう学校の乳幼児相談は、就学前から“聞こえ”や“ことば”の相談ができる場所
- 先生が親の気持ちに寄り添いながら、一緒に学びを進めてくれる
- 難聴と向き合う第一歩として、安心して訪ねられる場所
ろう学校の乳幼児相談とは?
ろう学校というと、「耳の聞こえない子が通う学校」というイメージを持つ方も多いかもしれません。
でも実は、就学前の赤ちゃんや幼児とその家族が、早い段階から聞こえの相談をできる場所なんです。
対象は、難聴がある・難聴の疑いがある・ことばの発達に心配があるお子さんなど。
聴力や発達の状況を見ながら、先生たちが家庭での関わり方や補聴器の使い方などを一緒に考えてくれます。
初めて行った日のこと
初めてろう学校を訪れた日は、ドキドキでいっぱいでした。
とうこも初めての場所に少し不安そうで、「大丈夫かな…」と思いながら、学校の門をくぐりました。
「とうこちゃん!お母さん!待っていましたよ~!」
出迎えてくださったのは、電話でお話ししたあの優しい先生。
案内されたのは、小さなカーペット敷きのお部屋でした。
ホワイトボードには「とうこちゃん ◯月◯日」「とうこちゃんの聞こえについて」と書かれていて、その一文字一文字がとても温かく感じました。
この日は、これまでの聴力検査の結果を持参していました。
先生が資料を見ながら「とうこちゃんの聞こえはこのくらいですね」と言うと、わたしの両手をそっと取り、その手で耳をふさいでくださいました。
「お母さん、このまま喋ってみてください。」
そう言われて話してみると、声が遠くにぼんやりとくぐもって聞こえます。
その瞬間、とうこが日々感じている“世界の音”を、ほんの少しだけ実感しました。
別の日には、耳の構造の話やスピーチバナナの図を使った説明もありました。
「このバナナ型の範囲が、人の声が聞こえる高さなんですよ」と、先生は色とりどりの図を見せながら教えてくださいました。
さらに、補聴器をつけたときと外したときの聞こえ方の違いを体験できるようにと、補聴器の聞こえ体験もさせてもらいました。
実際に耳をふさぎながら音を聞くと、「ああ、とうこはこういう世界で音を感じているんだな」と、胸の奥にぐっと響いたのを覚えています。
それからしばらくの間、乳幼児相談に通うことになりました。
行くたびにホワイトボードには、とうこの名前と“今日のお勉強”の内容が書かれていて、まるで小さな学校のよう。
通うたびに、とうこの耳のことを少しずつ理解できるようになっていくのが、嬉しかったのを覚えています。
療育にあまり関心がなかった夫を持つわたしにとって、乳幼児相談の先生は、唯一とうこの難聴のことを理解してくれる話し相手でもありました。
子どもの障害の受容については、こちらの記事で解説しています。

行ってよかったと思ったこと
乳幼児相談に通ううちに、「難聴について学ぶ場所」から「親子で安心できる場所」へと気持ちが変わっていきました。
先生方はいつも「お母さん、無理しなくていいですよ」と声をかけてくれて、どんな小さなことでも一緒に考えてくださいました。
補聴器のこと、言葉の育ち方、家庭での関わり方。
一人では抱えきれなかった悩みも、先生と話すうちに少しずつ整理されていきました。
何より、「とうこの聞こえ」に寄り添ってくれる人がいるという安心感が、あの頃の私を支えてくれたように思います。
これから相談に行こうと思っている方へ
もし「うちの子、聞こえのことで少し気になるかも…」と感じたら、どうか一人で悩まずに、ろう学校の乳幼児相談を訪ねてみてください。
そこは、“診断のための場所”ではなく、“子どもを理解するための場所”です。
どんな質問でも受け止めてくれる先生方がいて、きっと帰るころには心が少し軽くなっているはずです。
まとめ
ろう学校の乳幼児相談は、“診断の場”ではなく“理解の場”です。
難聴のことを何にも知らなくても、耳の仕組みや聞こえ方、家庭での関わりまで丁寧に教えてもらえて、不安な気持ちを受け止めてくれる先生がいます。
初めて行く前は緊張するかもしれませんが、帰るころには前向きな気持ちになれる温かい場所です。
ろう学校の乳幼児相談は、“難聴”という言葉に不安を感じていた私に、「一緒に学んでいけばいいんだ」と思わせてくれた場所でした。
引っ越しを機に顔を出すことはなくなりましたが、表紙に「とうこちゃん」と書かれたファイルを持って先生と一緒に勉強した日々は、今でもわたしの心の支えです。
これからも、とうこの聞こえを通して、親子で少しずつ成長していけたらと思います。