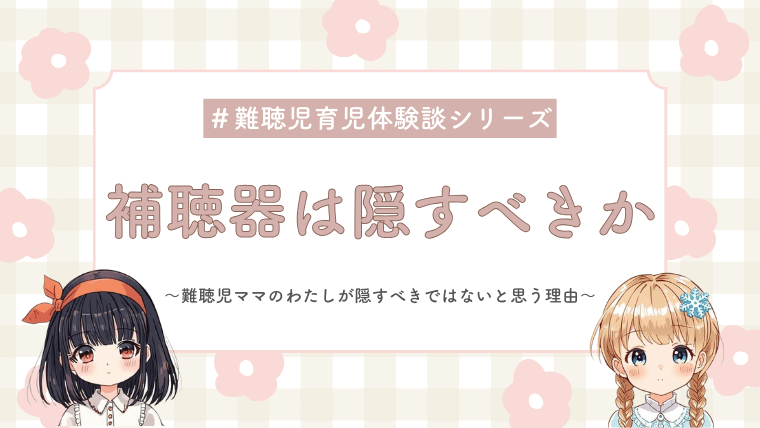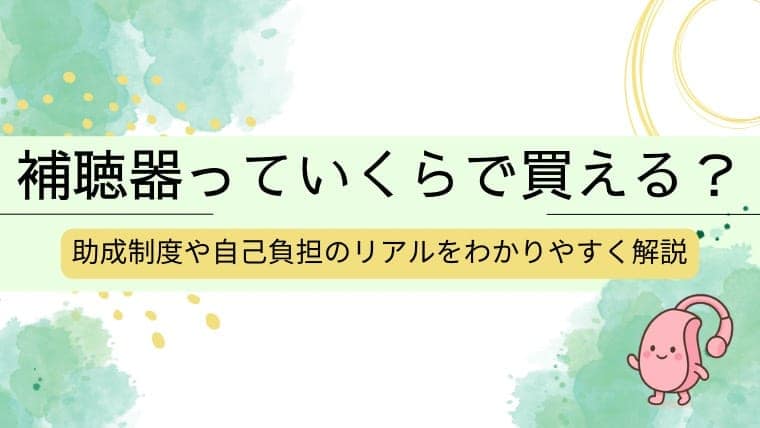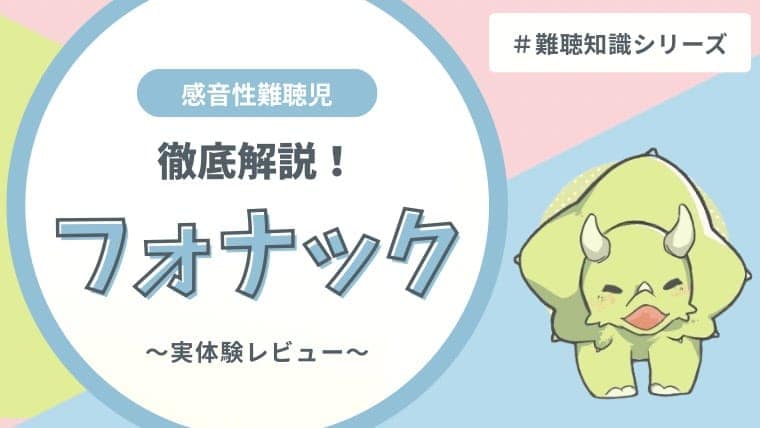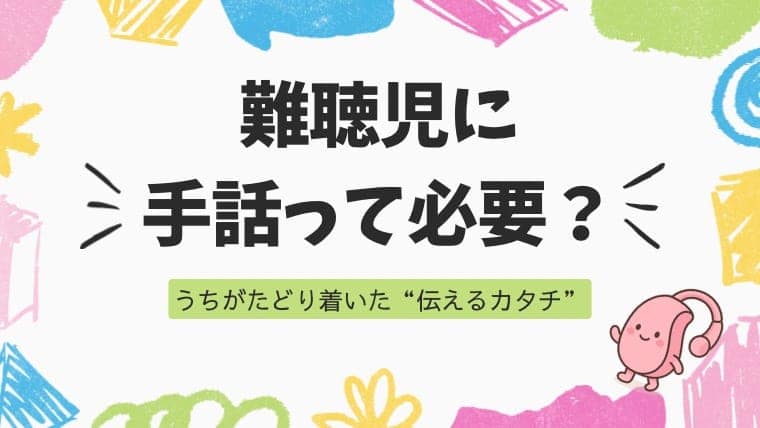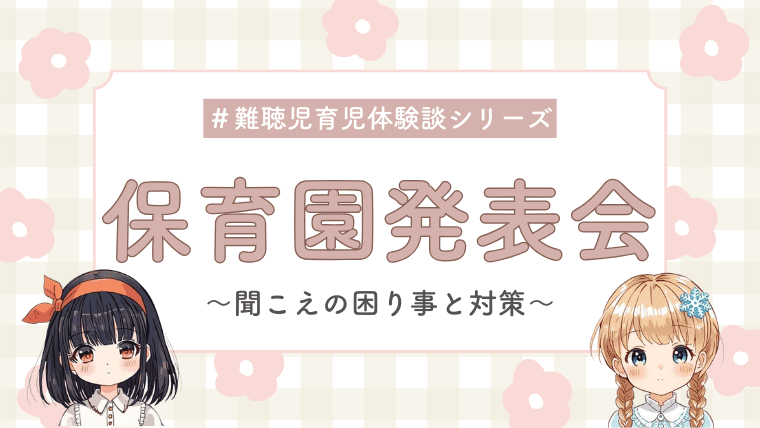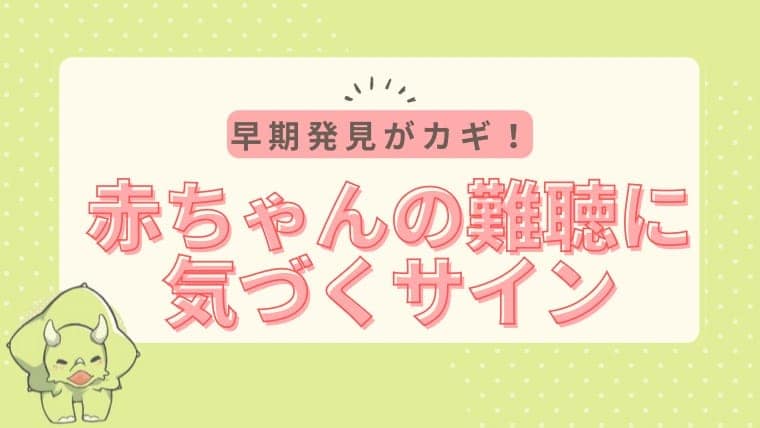指文字とは?難聴児の言語発達を助ける“視覚のことば”の使い方
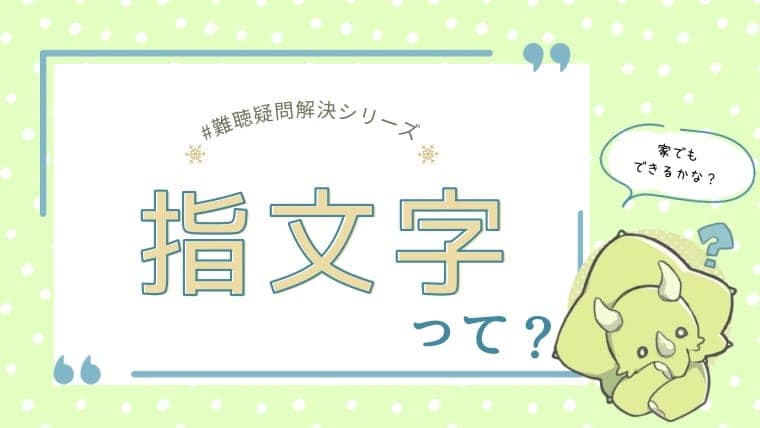
今日は指文字を紹介するよ!
指文字という言葉を聞いたことはあっても、「いつ使うの?」「手話とは違うの?」と感じる方も多いと思います。
わたし自身、長女が生まれるまで指文字の存在自体を知りませんでした。
しかし、難聴の娘たちと関わる中で、音だけでは伝わりにくい場面で“視覚的に伝える手段”としてとても役立ったのが指文字でした。
全部を覚える必要はなく、1〜2個だけでもコミュニケーションがぐっと楽になることがあります。
今日は、そんな指文字の基本、使いどころ、家庭での取り入れ方を初めての方にもわかりやすくまとめていきます。
- 指文字は「50音を手の形で表す視覚的な文字」で、音の手がかりを補うのに役立つ
- 難聴児の語彙獲得のサポートとして、1〜2個だけ取り入れても効果を感じやすい
- 全部覚える必要はなく、日常の会話の中で無理なく使うのがポイント
指文字とは?
指文字は、50音を手の形で表す“視覚的な文字” のことです。
ひらがなの「ひと文字」にそれぞれ対応する形があり、あいうえお、かきくけこ…というように、音の並びを表現できます。
よく混同されやすい手話とは、役割が異なります。
- 手話:語や文章をそのまま表す視覚言語
- 指文字:ひらがなを1音ずつ“目で綴る”ための表記手段
たとえば「車」を伝えたいとき、指文字なら“く → る → ま”と3つの手の形を順に示します。
一方で手話なら、“車”という手話を1回だけ示せば伝わります。
つまり、
- 指文字=音の流れを細かく見せるもの
- 手話=意味をひとつの動きで表すもの
という違いがあります。
難聴児と手話との関係については、こちらの記事でも解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児に手話って必要?
https://www.triceratops-family.com/sign-language/369/難聴児の言語発達と指文字
難聴のある子どもは、語頭の子音(か行・さ行など)が聞き取りにくく、「音のつながり」を捉えることが少し難しいことがあります。
指文字は、その音の形を“目で見える形”として補うことができる手段です。
たとえば「くるま」を指文字で表すと、「く → る → ま」というように、音の並びが視覚的にわかり、単語の構造理解を助けてくれます。
ここでよく出る疑問が、「だったら1回で伝わる手話だけ覚えればいいんじゃない?」というもの。
もちろん、手話は意味を伝えるのにとても便利です。
ただ、手話は語全体をまとめて表すため、音のつながり(音韻)や、ひらがなとの対応までは示せません。
一方で指文字は、
- “く”という音
- “る”という音
- “ま”という音
と、音を細かく見せられるので、語彙の獲得や読み書きの土台づくりにつながる役割があります。
いつから・どうやって教える?家庭でできる指文字の取り入れ方
指文字は、特別な教材がなくても日常の会話に“少し添えるだけ”で取り入れられるのが魅力です。
指文字ポスターなどもありますので、検索してみてください。
我が家も子ども部屋とトイレの壁に指文字ポスターを貼って、日常的に目に触れるようにしています。
よく使う言葉・好きな言葉から1つだけ
「くるま」「パン」「ママ」など、子どもがよく使う単語の最初の1音だけを指文字で示すところから始めます。
生活の流れで“ながら”で見せる
机に座ってお勉強のように覚える必要はありません。
- 絵本を開くとき
- おやつを出すとき
- おもちゃを渡すとき
その一瞬だけで十分です。
補聴器を外している時間帯は特に効果的
お風呂・寝る前・着替えなど、補聴器を外して聞こえが下がる時間こそ、指文字が音の手がかりになります。
口の動きが見えにくい場面にも
マスク越しなど、口元の視覚情報が取りにくい場面では、指文字が「代わりの手がかり」になります。
難聴児とマスクの関係については、こちらの記事でも解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児とマスク|言葉の習得を支える“見える聞こえ”とは
https://www.triceratops-family.com/mask/498/注意点と“無理をしない”ライン|指文字は万能じゃない
指文字は便利ですが、「これができれば言葉が育つ」という万能の方法ではありません。
子どもの興味が向かない日はやらなくてOK
無理に見せると逆効果です。
子どもが興味を向けた瞬間に“ちょこっと”見せる程度で十分。
詰め込みは不要
幼児期にたくさん覚えさせようとすると、子どもが“勉強っぽさ”を感じてしまいます。
日常の会話の中で、できる量でOKですよ。
言語発達は多くの要素が重なって育つ
指文字はその中のひとつの手段です。
パパママが無理しない範囲で
できない日があっても全く問題なし。
“できた日だけ”で大きな価値があります。
そのほかの家庭でできる声かけの工夫については、こちらの記事でも解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児への声かけの工夫5選|家庭でできる“伝わる”コミュニケーション
https://www.triceratops-family.com/communication/456/まとめ
指文字は、机に向かって覚えるものではなく、日常の会話にそっと添えるだけで使える“視覚のことば” です。
難聴児は、音の手がかりが少なくなる場面があります。
そんなときに、1つの音をゆっくり示してあげるだけで、ことばの形が理解しやすくなることがあります。
大切なのは、全部覚えようとしないこと。
子どもが興味を向けた瞬間に少しだけ使うこと。
無理のない範囲で日常の中に取り入れるだけで、子どものことばの世界は確かに広がっていきます。
子どもは自分の名前が大好きだから、まずは名前の頭文字を覚えて一緒に使うのが、指文字のスタートとしておすすめだよ!
「とうこ」と呼びながら「と」の指文字を見せるイメージだよ!