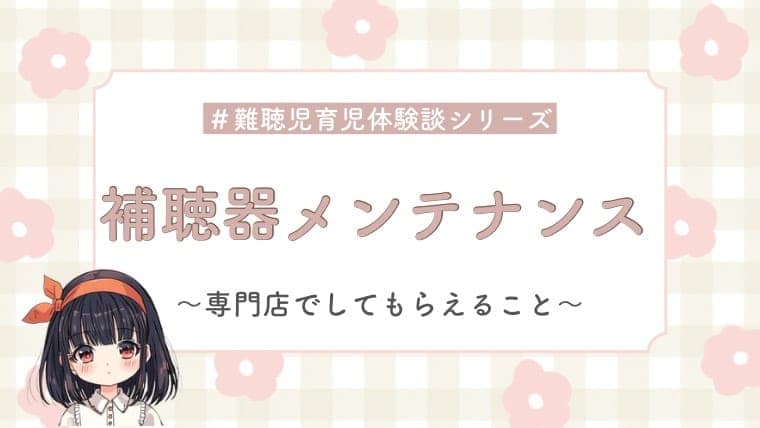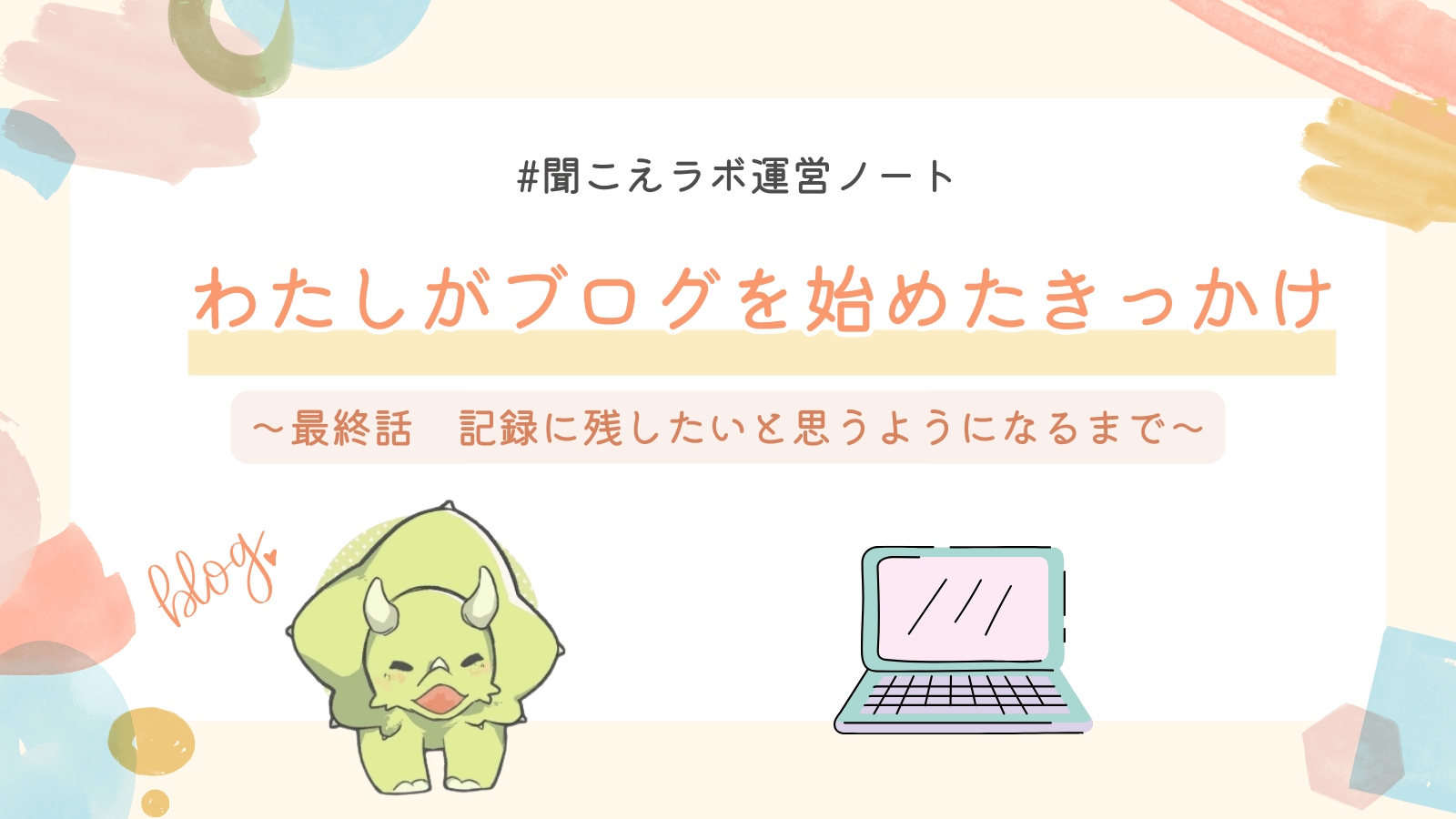難聴児小学校入学―先生に伝えたこと―

トリケラ家の長女とうこは、特別支援学校やろう学校ではなく、難聴学級に在籍しながら地域の小学校に通っています。
聞こえのサポートが必要な子どもが、みんなと一緒に学校生活を送るには、少しだけ工夫や配慮をお願いする場面があります。
- 座席やロジャーの使い方など、聞こえやすい環境を整えることが大切
- 学校全体での配慮(騒音対策・防音・行事での支援など)が、子どもの安心につながる
- 家庭と学校がこまめに連携し、「一緒に支えていく」関係を築くことが何より大切
今日は、「学校にお願いしていること」について、長女とうこの体験も交えながらお話ししていきます。
座席や教室の工夫
とうこは地域の小学校の難聴学級に在籍していますが、道徳と書写の2時間以外は、ほとんどの時間を交流学級で過ごしています。
入学のとき、私たち親から学校にお願いしたことは2つありました。
①机を前から2番目〜3番目の列に配置してもらうこと
この位置をお願いした理由は、先生の声や口の動きが見える位置であり、さらにお友だちの動きも見える位置だからです。
一番前に座ると先生はよく見えますが、お友だちの様子が見えなくなってしまいます。
たとえば先生の指示を聞き逃してしまったとき、前の列のお友だちの動きを見れば「今はプリントをする時間なんだな」「終わったら先生に持っていくんだな」と気づくことができます。
こうした周りの様子から学ぶ力も、とうこにとって大切な学びのひとつです。
②必要に応じてロジャーを使うこと
「ロジャー」とは、スイスのフォナック社が開発した補聴援助システムで、先生がマイクを通して話した声が、とうこの補聴器に直接届く仕組みになっています。
体育館での集会や運動場での体育など、距離がある場面でも、先生の声をクリアに届けることができます。
ただ、とうこの場合は中~高程度の難聴で、教室で使用すると音が大きすぎて疲れてしまうため、今は必要な場面だけで使っています。
ロジャーについては、こちらの記事で解説しています。

入学のときにお願いしたのは、この2つ。
どちらも「とうこが自分で考えて動ける環境」を整えるための工夫です。
とうこの実際の時間割については、こちらの記事で紹介しています。

学校全体の工夫
とうこの通う小学校には難聴学級があり、全ての机と椅子の脚に、騒音を防ぐためのテニスボールが取り付けられています。
1年生から6年生まで、理科室や音楽室などの特別教室もすべてです。
ここまで全校的に配慮されている学校は、県内でもなかなかありません。
また、集会や行事のときには、前に出て話す先生や児童が自然にロジャーを使ってくれます。
特別なことではなく、「聞こえにくい子がいるから使うのが当たり前」という空気が学校全体にあります。
さらに、難聴学級の教室も防音カーペット仕様になっていて、反響音が少なく、落ち着いて学べる環境が整っています。
聞こえにくい子どもを育てる親として、こうした学校全体の配慮には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
だからこそ、この環境で学ばせたいと思い、わたしたちは学区外からでも通うことを選びました。
学校との連携と先生方への感謝
学校との連携で私が大事にしているのは、連絡帳でこまめに様子を伝えること。
とうこが苦手なこと、苦手な環境、そんなときにどう対応しているか――
その日の小さなエピソードを、1日1つだけ書くようにしています。
先生方も難聴の子を受けもつのは初めてということが多いので、「一見普通に見えるけれど、聞こえにくいという特性がある」ことを忘れずに接してもらえたらと思っています。
そして、私も小学生ママは初めて。
必要以上に口を出しすぎないように、見守る姿勢も大切にしています。
また、家庭では補聴器やロジャーの調子、家での聞こえの様子を先生に共有しています。
とうこには巾着を持たせていて、中には補聴器ケース・替えの電池・使い終わった電池を入れるケースを用意しています。
難聴学級と交流学級のそれぞれの先生に、2冊の連絡帳を書いているので、伝える内容はできるだけ簡潔に、分かりやすくまとめるようにしています。
難聴学級の先生とはLINEで連絡を取り合い、何か変わったことがあるとすぐに連絡をくださいます。
ときどき行事や遠足の写真を送ってくださることもあります。
とうこの学校には、難聴だけでなく、発達面や視覚面で配慮が必要な子どもたちもいます。
それでも先生方は、特別扱いするのではなく、自然にサポートしてくれるんです。
その姿勢が本当にありがたくて、いつも頭が下がります。
だからこそ、こちらからのお願いも“必要なことを、必要な分だけ”。
先生方の負担になりすぎないように、「一緒に支えていく」という気持ちを大切にしています。
まとめ
難聴がある子どもが地域の学校で学ぶには、まわりの理解と協力が欠かせません。
でもそれは、“特別な支援”というよりも、「みんなが学びやすい環境を整える」という姿勢なのだと思います。
とうこの学校のように、自然に配慮が行き届いた場所がもっと増えていけば、聞こえにくい子も、そうでない子も、安心して学べる環境になっていくはずです。
そして何より、学校と家庭が“お互いを信頼して支え合うこと”がいちばんの力。
今日も「ありがとう」の気持ちを忘れずに、とうこを見守っていきたいと思います。

配慮してもらえることは当たり前ではないので、いつも支えてくださっている先生方にはとても感謝しています!