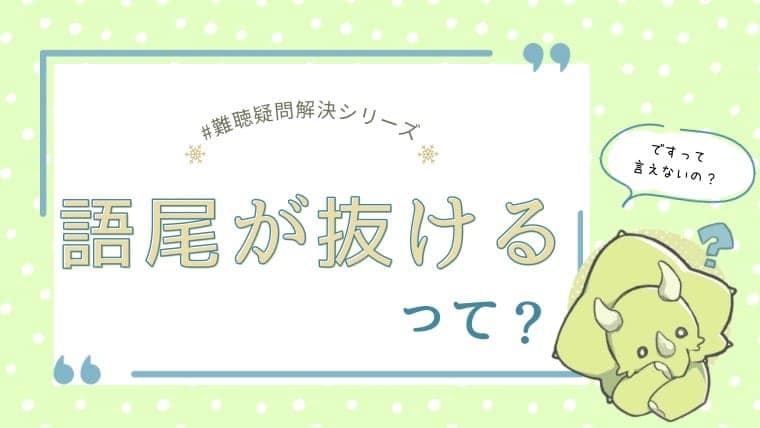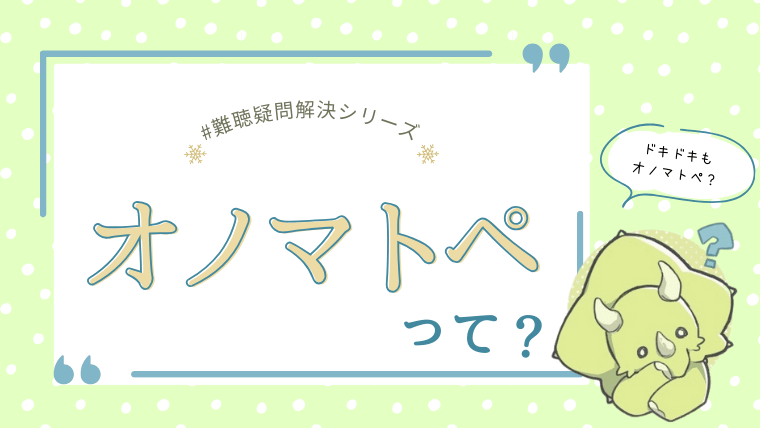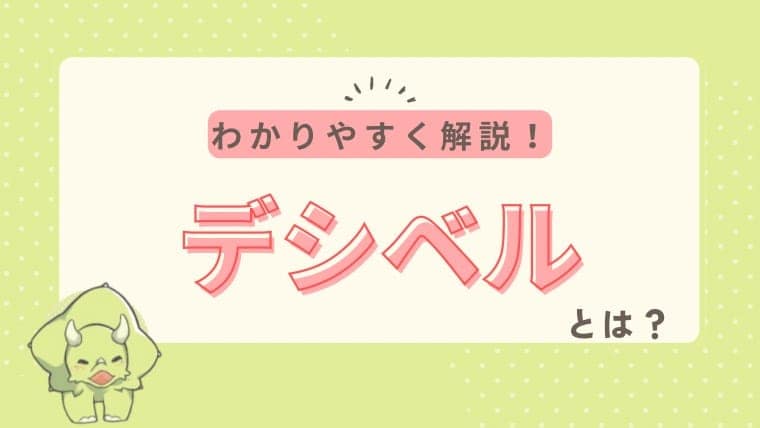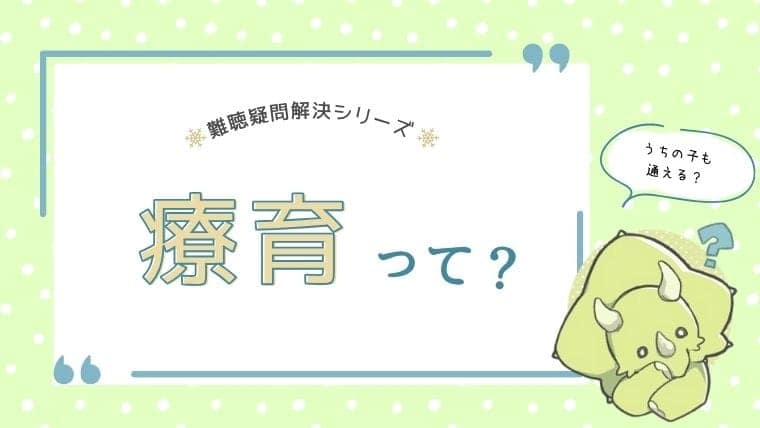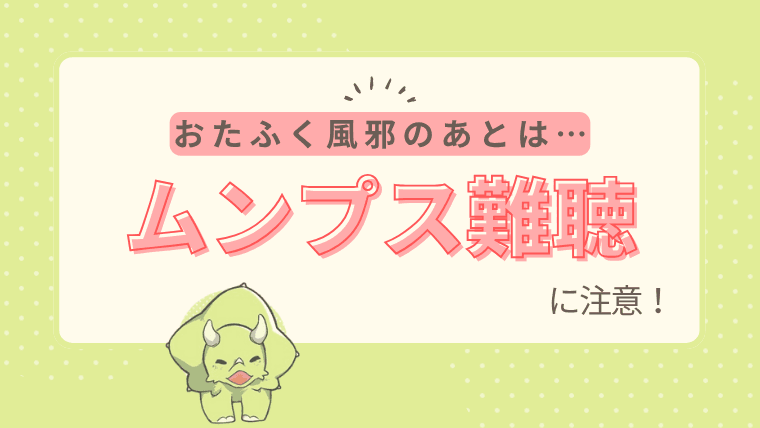難聴児とマスク|言葉の習得を支える“見える聞こえ”とは
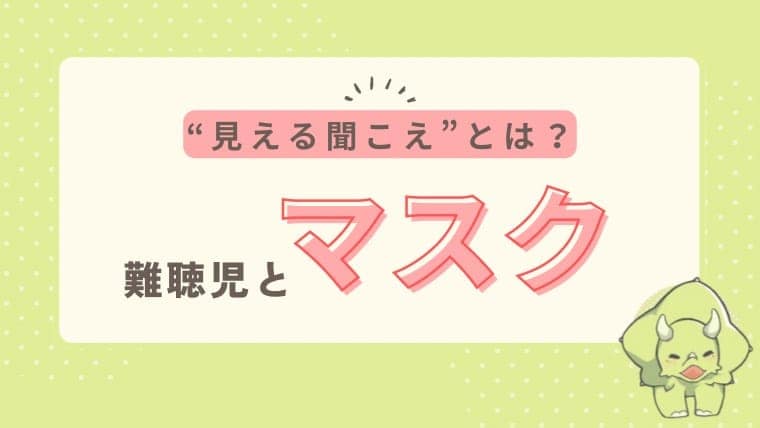
マスクって口の形が見えないんだよな…
コロナ禍でマスク生活が始まったころ。
「聞こえにくい」「声がこもる」と感じた人も多いと思います。
でも、難聴のある子どもたちにとっては、それ以上に大きな変化でした。
マスクで口の動きが見えないだけで、会話のヒントが一気に減ってしまうのです。
トリケラ家の次女そらは、コロナ禍生まれ。
難聴があるため、先生や友達の口形を読みながら言葉を理解することが多い子です。
だから、マスク越しの会話が続いた時期は、聞き返しが増えたり、疲れやすくなったりしていました。
今では当たり前になったマスク。
けれど、難聴のある子どもたちにとっては、言葉を学ぶうえでの思わぬ弊害になることもあります。
マスクで何が変わる?
マスクをつけると、音も口の動きも表情も、すべてが少し届きにくくなります。
難聴のある子どもたちにとって、それは“聞こえ”の世界が一段暗くなるような感覚です。
トリケラ家の長女とうこの発音はとてもきれいなのですが、次女そらはまだまだ発音が未熟です。
その理由のひとつが、そらがコロナ禍生まれであり、周囲の人々がだれでもずっとマスクをしていたことにあるのではと感じています。
私たち保護者も、保育園の先生も、療育先の先生も、みんながマスクをして過ごしていたあの時期。
ちょうどそらは言葉をたくさん吸収する“言語獲得期”でした。
口の動かし方が見えないまま言葉を覚えていったため、今も発音しづらい音があるのかもしれません。
例えば、そらは「ぞう」が「どう」になったり、「ティッシュ」が「ぴっしゅ」になったりします。
このように、マスク生活と発音の未熟さには関係があるのではと感じています。
学校や療育で感じた困りごと
マスク生活のあいだ、そらが通っていた保育園や療育先でも、先生たちはみんなマスク姿でした。
先生の声が少しこもって聞こえるだけでなく、口の動きや表情も見えないため、言葉の理解に時間がかかることがありました。
たとえば、グループ活動の中で先生の指示を聞き逃してしまったり、友達との会話でタイミングをつかめずに戸惑ったり。
補聴器をしていても、周りの声やざわめきの中では聞き分けるのが難しく、「聞き返す回数が増える」「集中力が途切れやすい」といった変化が見られました。
マスクは感染予防のために必要なものだったけれど、難聴のある子どもたちにとっては、音と言葉をつなぐ“表情”が失われた期間でもあったのだと思います。
家庭や先生と一緒にできた工夫
あの頃、家では基本的にマスクをせずに過ごしていました。
難聴のある子どもにとって、口の動きを見せることが何より大切だと思っていたからです。
保育園の先生にも、「とうこやそらに話や指示が伝わっていないときは、一時的にマスクを下げて口を見せてください」とお願いしていました。
先生方も理解してくださって、できる範囲で工夫してくださっていたと思います。
でも、あの頃は誰もが未知の病原体と闘っていた時期。
感染を防ぐために、誰もが必死でした。
私自身も、先生たちがマスクを外すことへの不安を理解していたつもりです。
でも本当は、療育の先生にはマスクをつけてほしくなかった。
難聴児が口の動きから言葉を読み取っているため、言葉の発達を支える療育の場でマスクをしているのは、とてももどかしく感じていました。
フェイスシールドを使う先生もいましたが、すぐに曇って口元が見えなくなる。
「意味がないな」と思う一方で、「それでも先生方を感染から守らなければならない現実」もありました。
あのコロナ禍の2年間は、難聴児とその家族をはじめ、療育先の先生方にとっても本当に過ごしづらい時期だったと思います。
マスク以降の今、できる工夫
マスク生活が落ち着いた今だからこそ、改めて感じることがあります。
それは、「聞こえる環境は、つくることができる」ということ。
コロナ禍の経験を通して、学校や社会全体が“見えない困りごと”に気づくきっかけにもなりました。
最近では、声がこもりにくいマスクや透明マスクが開発されたり、字幕付き動画やタブレットを使った授業が広がったりしています。
少しずつですが、“聞こえやすさ”と“安心”を両立させる工夫が広がってきています。
家庭でも、できるだけ顔を見て話すことや、話す前に名前を呼んで注意を向けてから話すなど、小さな工夫を続けています。
たったそれだけでも、子どもが安心して聞こうとする姿勢につながります。
「見せる聞こえ」「伝わる言葉」——
マスク生活を経た今だからこそ、社会全体がやさしく変われるチャンスなのかもしれません。
まとめ
マスクは、感染を防ぐために必要だったもの。
でも、難聴のある子どもたちにとっては、言葉の世界との間にできた小さな壁でもありました。
それでも、家族や先生、そして社会の工夫によって——
「聞こえにくさ」は少しずつ乗り越えられるものになっています。
聞こえは、耳だけで感じるものではありません。
表情・口の動き・まなざしなど、たくさんの要素が合わさって、初めて“伝わる”という形になります。
そして、あの頃を振り返ると、心のどこかでこう思うこともあります。
「もしわたしが手話を覚えて日ごろから子どもたちに使っていれば、あのマスク生活の中でも難なく過ごせたのかもしれない」と。
けれど、あの時できる精一杯の選択をしてきたからこそ、今の子どもたちがいるのだと思います。
マスク生活を経た今、私たちが学んだのは、「伝えようとする気持ち」があれば、方法はいくらでもあるということ。
これからも、見えない音を見せる工夫を大切にしながら、子どもたちが安心して言葉を育てていける環境を守っていきたいと思います。
手話や指文字、ベビーサインはマスク生活で大活躍するんだよ!
難聴児と手話との関係については、こちらの記事でも解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児に手話って必要?
https://www.triceratops-family.com/sign-language/369/