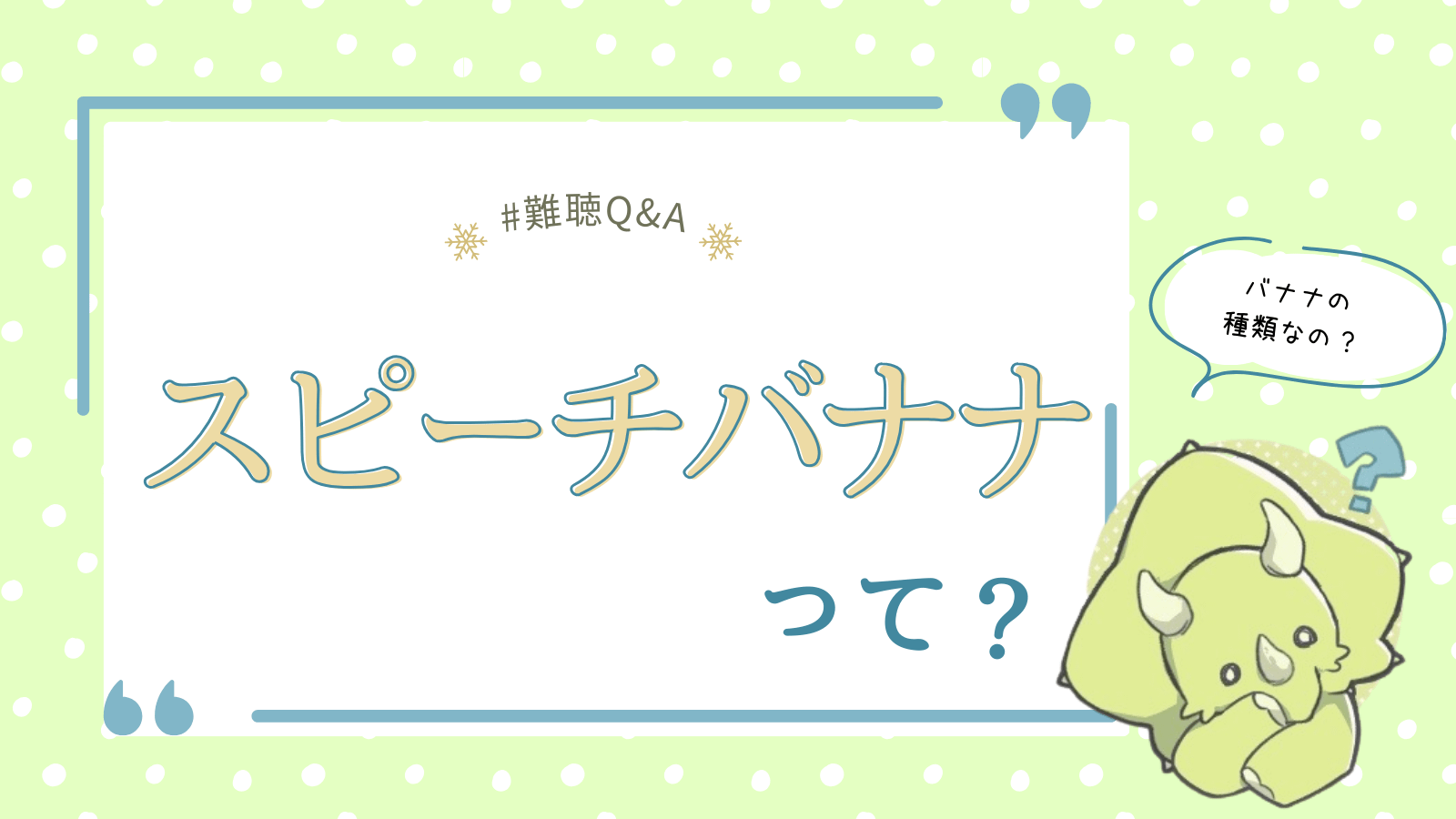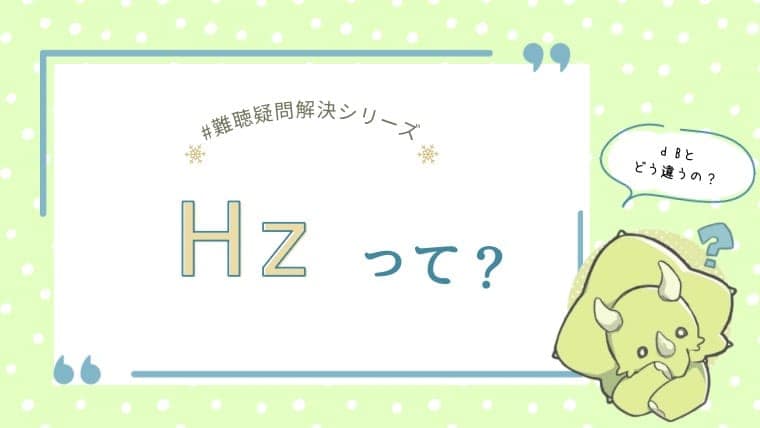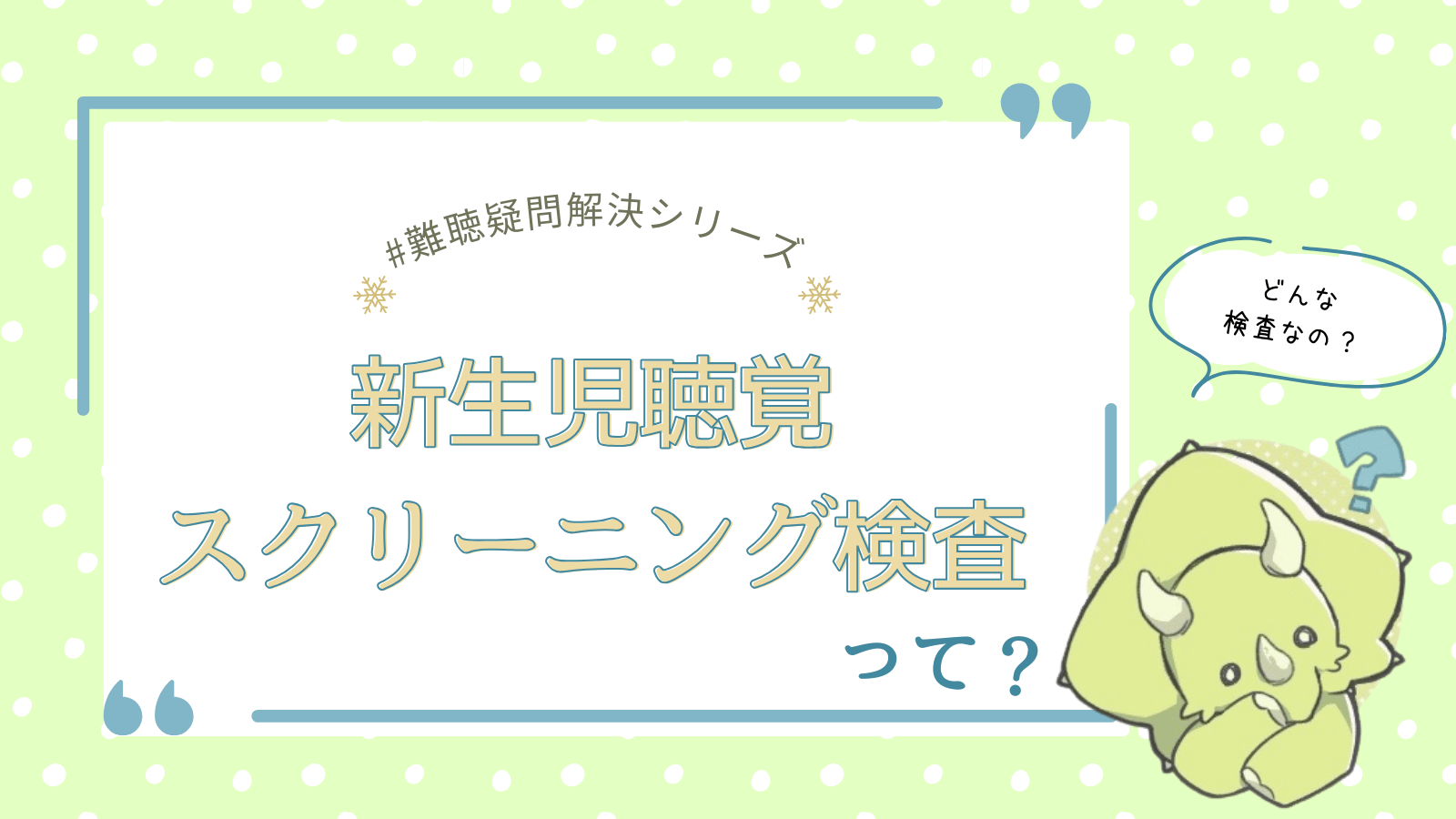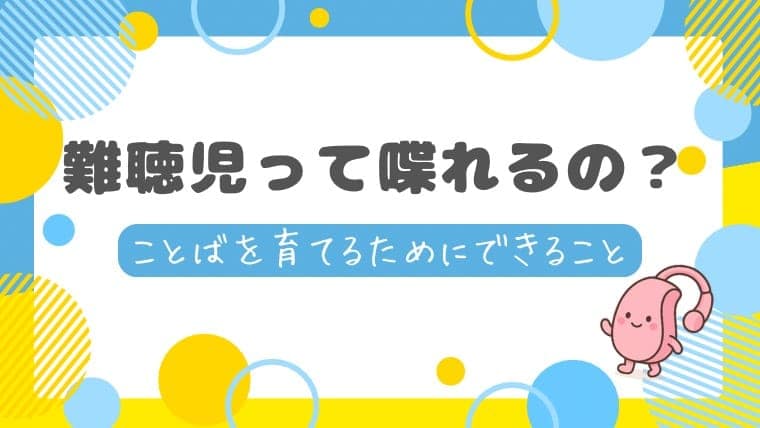難聴児に手話って必要?
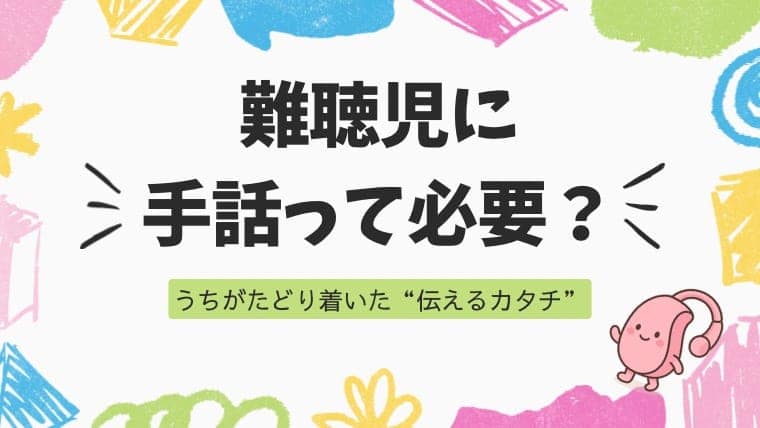
難聴の診断を受けたとき、多くのママが一度は考えることだと思います。
専門家のあいだでは、ろう児だけでなく難聴のある子にも手話は有効とされています。
耳からの情報だけでは拾いきれないことを、“目で見てわかる言葉”で補える。
そして、言葉をまだ話せない時期から「伝わった」「わかってもらえた」という経験を重ねることで、言葉の発達がスムーズになるという研究もあるんです。
- 手話はろう児だけでなく難聴児にとっても有効なコミュニケーション手段
- ただし、今まで口話で育ってきた親御さんが家庭で無理なく続けるのは簡単ではない
- 大切なのは、「どんな手段を使うか」よりも、“伝えたい気持ち”を持ち続けること
『難聴児にも手話は有効』
頭ではそうわかっていても、現実はなかなか簡単じゃありません。
親が一から手話を覚えるのは大変だし、家族全員がそれを共有するのはもっと大変。
私も、「やったほうがいいのかな」と思いながらも、うまく続けられずに悩んだ時期がありました。
ちょこっと専門メモ:手話や指文字の効果について
手話や指文字が難聴児に与える効果を調べた3つの研究
専門家のあいだでは、手話はろう児だけでなく中〜高程度の難聴のある子にも有効とされています。耳からの情報だけでは取りこぼしてしまう音も、「目で見てわかる言葉」があることで理解しやすくなるんだって。
実は日本でも、とうこのように中〜高程度難聴で、地域の学校の難聴学級に通うお子さんを対象に、手話や指文字、視覚教材など“音+目で伝える工夫”を取り入れた実践や調査が行われています。
指文字については、こちらの記事で解説しています。
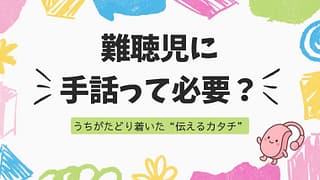
ここから先は、手話や指文字、視覚教材など“音+目で伝える工夫”を取り入れた実践や調査研究を3つ紹介します。
①「聴覚障害幼児の言語獲得における指文字の役割に関する文献的考察」(2019)
研究内容
新生児聴覚スクリーニング(NHS)により聴覚障害の早期発見が進み、補聴機器の発達で「聞こえ」は改善しているが、依然として助詞・助動詞など文法の習得が困難とされているため、日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙(JCDI)を用いて、聴覚障害幼児の語彙・文法発達の特徴と困難な分野を明らかにすることを目的とした研究。
研究結果
- 対象児平均年齢:4歳7か月。裸耳聴力平均:76.6dB、装用閾値平均:37.9dB。
- 家庭でのコミュニケーション手段:音声のみ28.6%/音声+手話60.0%/手話のみ11.4%。
- 平均補聴開始:9.6か月(約7割が1歳未満に補聴開始)
★音声+手話併用群が最も取得率が高い。
★語彙より助詞・助動詞・最大文長の取得率が有意に低い。
音だけでは理解が難しい単語や文章でも、手話や指文字を一緒に使うと理解しやすくなる傾向が見られました。
特に、語彙(ことば)の意味をつかむときに「目で見てわかる手がかり」が役立っていたそうです。
ここから言えること
手話や指文字は、ただの“特別な言葉”じゃなくて、聞こえを補う大事なサポートツール。
トリケラ家流の「口話中心+指文字少し」というスタイルも、研究的にすごく理にかなっていることが分かりました。
参考リンク
https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/52384/files/JJDS_43_137.pdf
②国立特別支援教育総合研究所「軽度・中等度難聴児の教育的支援に関する調査」
研究内容
特別支援学校を含め、軽度・中等度難聴の児童生徒への教育的な対応が重要な課題になっているため、軽度・中等度難聴児への指導や支援の在り方とともに保護者等への支援も含めて検討することを目的とした研究。
全国の学校(難聴学級を含む)を対象に、どんな支援が行われているかを調べた調査です。
手話や視覚教材、通訳などの支援体制に関する具体的なデータがまとめられています。
研究結果
- 乳幼児期から高等部まで、軽度・中等度難聴児への支援は学部ごとに特徴がある。
- 乳幼児教育相談・幼稚部では、保護者への情報提供やベビーサインなどを活用し、ことばや心の発達を支える取組が見られる。
- 小学部では手話などの視覚的手段を使いながら、学力や思考力への支援方法を検討している。
- 中学部では、自分の聞こえ方を理解し、主体的にコミュニケーションをとる力の育成を重視。
- 高等部では、障害理解と自己発信力を育て、社会での自立を目指している。
全体として、年齢が上がるほど軽度・中等度難聴児への特化した支援が減少する傾向があり、今後は理解啓発と個別支援の充実が課題である。
という結果が出ています。
ここから言えること
“地域の学校+難聴学級”という環境でも、手話や目で見えるサポートを取り入れる流れはちゃんとある。
つまり、家庭でも少しずつ取り入れる価値がある支援方法だと言えます。
参考リンク
https://www.nise.go.jp/cms/resources/content/7051/seika9_3.pdf
③ 鳥越 隆士「聴覚障害児のインクルーシブ教育 ―合理的配慮としての手話活用の実践的検討―」(2015)
研究内容
通常の学校に通う難聴児・ろう児を対象に、手話を「合理的配慮」としてどう活かせるかを実際の授業で検討した研究です。
研究結果
授業中に手話や指文字などの視覚的サポートを使うと、子どもたちが発言や理解の機会を得やすくなり、クラスの一体感も生まれたとのこと。
ここから言えること
手話は、「見る力」を育てる大切な言葉だと言われています。
声でのやりとりが中心だった子どもたちも、少しずつ手話を使って伝え合うようになっていきます。
指導というより、自然な会話の中で手話を交えていくことが、理解を深める近道。
また、個別の支援だけでなく、先生方やクラス全体で手話を共有することで、より安心して学べる環境が広がっていきます。
手話を「特別支援」ではなく、みんなで使えるコミュニケーションのひとつとして考えることで、子ども自身も周囲の友達も安心して関われるようになるんですね。
参考リンク
https://www.hyogo-u.ac.jp/riron/pdf/27-28_torigoe.pdf?utm_source=chatgpt.com
ろう学校の手話教室に通ってみたけれど…
難聴の診断を受けたあと、「やっぱり手話も覚えたほうがいいのかな」と思って、ろう学校で開かれていた手話教室に通い始めました。
週に一度、赤ちゃんを抱っこしながら、指の形をまねしたり、表情で気持ちを伝える練習をしたり。
最初はすごく新鮮で、「こんなふうに伝えられるんだ!」とワクワクしていたのを覚えています。
でも、現実はなかなかハードでした。
赤ちゃん連れで車を走らせて毎週通うのは思った以上に大変で、授業中も泣いてしまったり、途中で抜けざるを得ないことも。
家に帰っても、私が学んだ手話を夫に伝えても「そんなのいらないよ」と言われてしまって…
そんな日々が続いた数ヶ月後、ちょっと心が折れてしまいました。
「私ひとりで頑張るには、もうキャパが足りないかも」
そう感じて、しばらくして教室に通うのをやめました。
でも、あの頃の自分を責める気持ちはもうありません。
できなかったことよりも、「どうしたら子どもに伝わるか」を一生懸命考えていた自分を、今では少し誇りに思っています。
それでも、「伝えよう」としていた日々
手話教室には通えなくなったけれど、「できる範囲で伝わる方法を探したい」と思っていました。
そんなとき、療育先の壁に貼ってあった指文字ポスターを見つけました。
「これ、家にも欲しいなぁ」と思って調べたら、全国早期支援研究協議会で販売されていることを知りました。
コピーは禁止されていたので、療育先からはもらえず……。
調べたら難聴に関する書籍も販売されていることを知り、送料がかかるので療育先のお母さん方と合同で、指文字ポスターと難聴関連の本をいっしょに購入しました。
夫にも関心を持ってもらいたくて、『パパと学べるハッピーサイン』という親子で学べる本も買いました。
でも、結局夫がその本を開くことは一度もなくて(笑)
あの頃の私は、「それでも私ができることをしよう」って思ってたんだと思います。
そんな中で、指文字ポスターをトイレの壁に貼るという小さな工夫をしました。
トイレトレーニングのとき、子どもが指さした文字を「これは『か』だよ、かえるの“か”ね!」と指文字を見せながら一緒に覚えていきました。
遊び感覚で学べたから、トイレの時間が少し楽しくなったんです。
今でもそのポスターは貼ったままで、ひらがなを覚えはじめた次女そらも、まだ1歳の三女みどりも、トイレのたびに眺めて、「かえる!」と指差して笑っています。
あの頃の小さな工夫が、今もわが家の“ことばを育てる時間”につながっている気がします。
難聴児への家庭でできる声かけの工夫については、こちらの記事で解説しています。
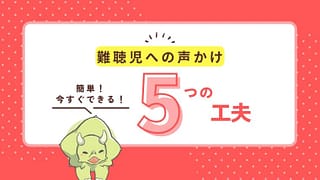
手話の効果と、ベビーサインとの共通点
手話や指文字を使うことは、難聴のある子どもにとってだけじゃなく、言葉をまだ話せない時期の子どもにも役立つと言われています。
それは、“ベビーサイン”ととても似ています。
赤ちゃんが「おっぱい」「もっと」「できた!」などのサインを覚えて伝えられるようになると、自分の思いが通じて嬉しそうに笑う。
――その瞬間を見たことある親御さんも多いと思います。
手話もそれと同じで、言葉が出る前から「伝わった!」という成功体験を積み重ねられるんです。
音が聞こえづらくても、相手の手の動きや表情で気持ちを読み取れたとき、子どもは「わたしにも伝える力があるんだ」と自信を持てるようになります。
それが、次の“話したい”“伝えたい”という意欲につながっていく。
だから、手話や指文字は、単なる補助ではなく、心を育てる言葉の一部だと私は思っています。
まとめ
あの頃の私は、「手話をちゃんと覚えられなかった」という後悔をずっと心のどこかに抱えていました。
“子どものためにもっとできたんじゃないか”って、自分を責めたこともあります。
でも今は、そう思わなくなりました。
あのときの私なりに、できる限りの工夫をして、どうしたら伝わるか、どうしたらこの子が安心できるか。
――それを一生懸命考えていた。
それこそが、あのときの「正解」だったんだと思います。
手話を完璧に使えなくても、指文字をちょっと使うだけでもいい。
手話で伝えることも、声で伝えることも、表情で伝えることも、どれも立派なコミュニケーション。
大事なのは、“どうやって”よりも、“どんな気持ちで伝えるか”。
これからも、手話でも口話でも、我が家らしい“伝え方”で向き合っていきたいなと思っています。
手話を頑張っている親御さんたちも、口話を中心にしている親御さんたちも、みんな子どもを想って選んでいることに変わりはありません。
どんな形でも“伝えたい気持ち”がある限り、それはきっと正解です。