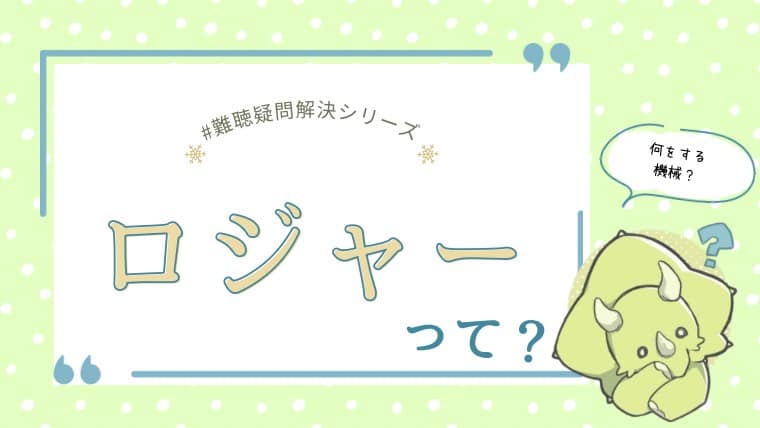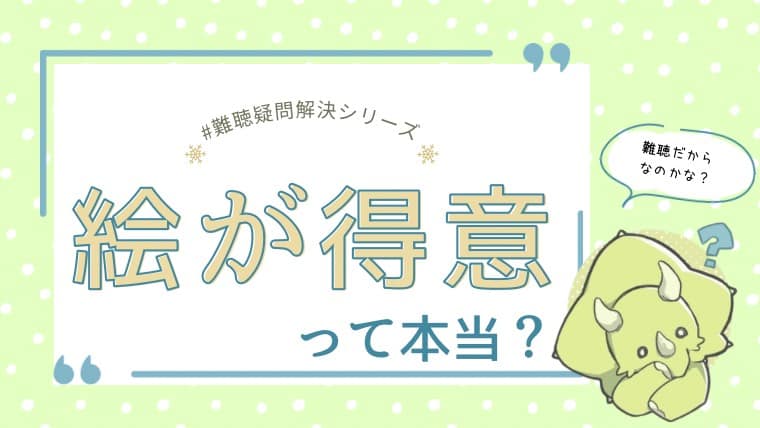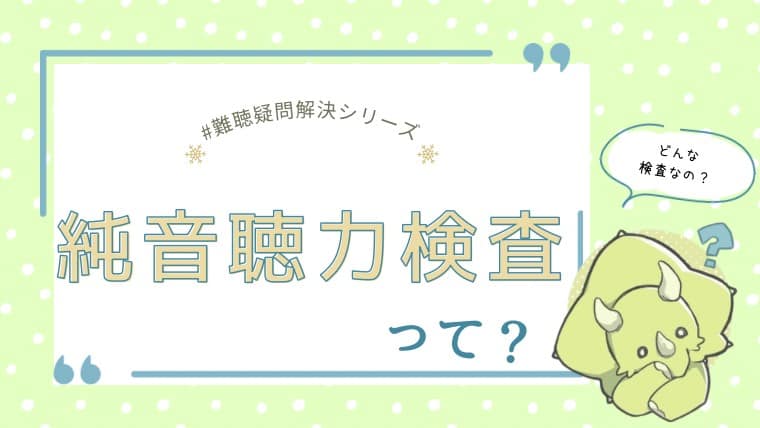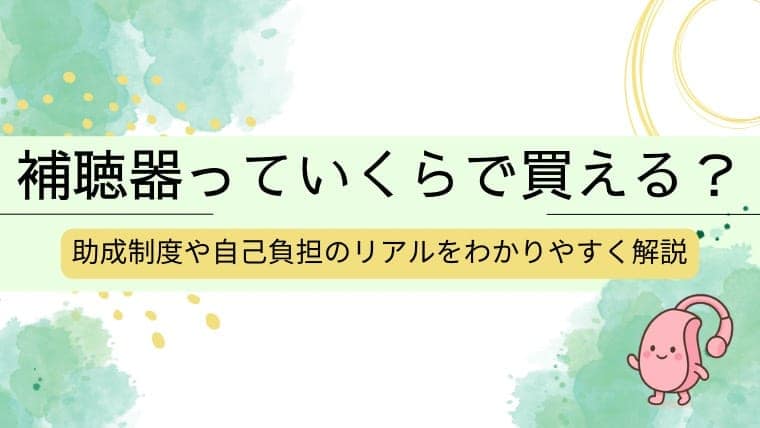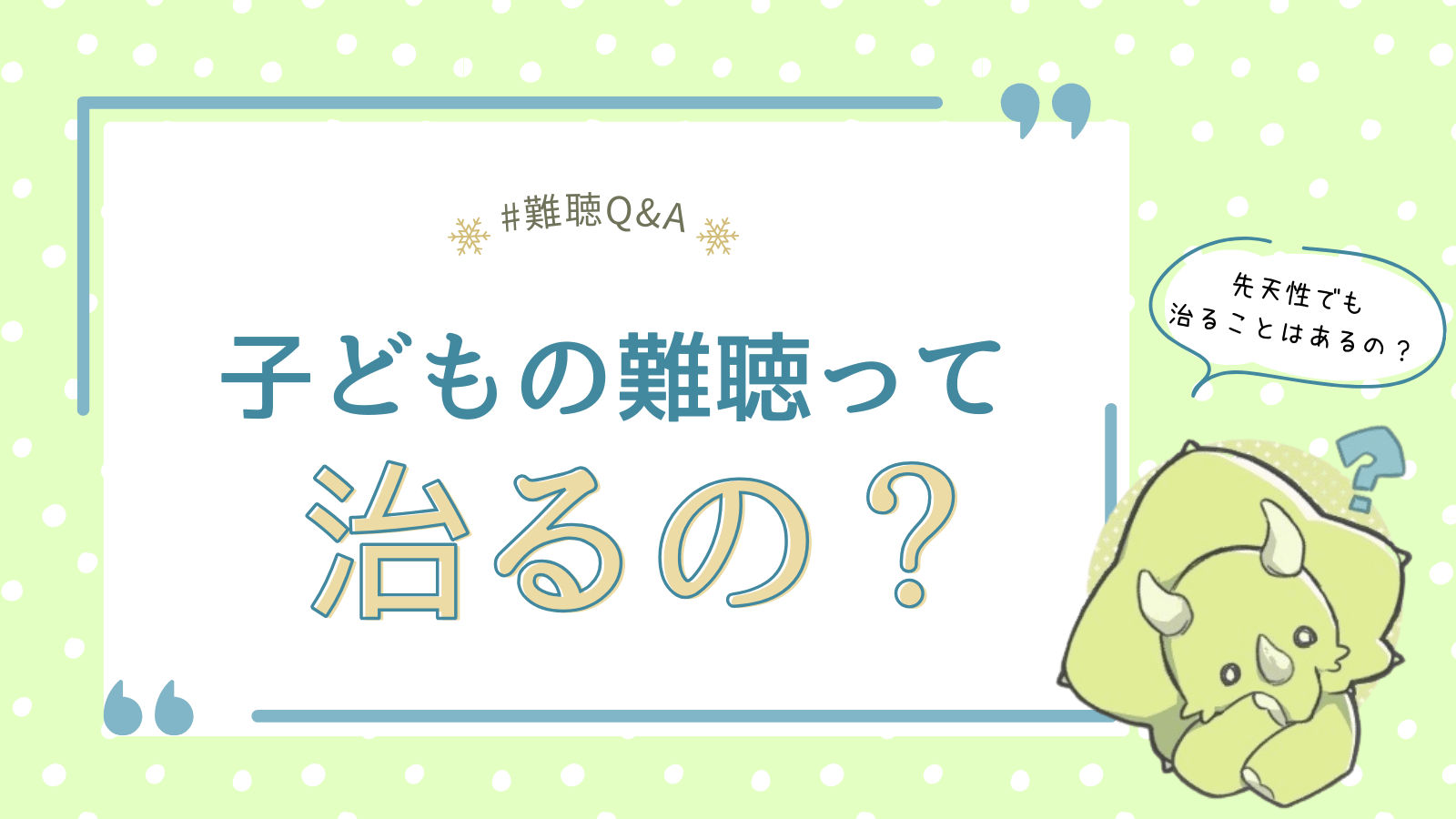難聴児って喋れるの?難聴児ママ目線でやさしく解説
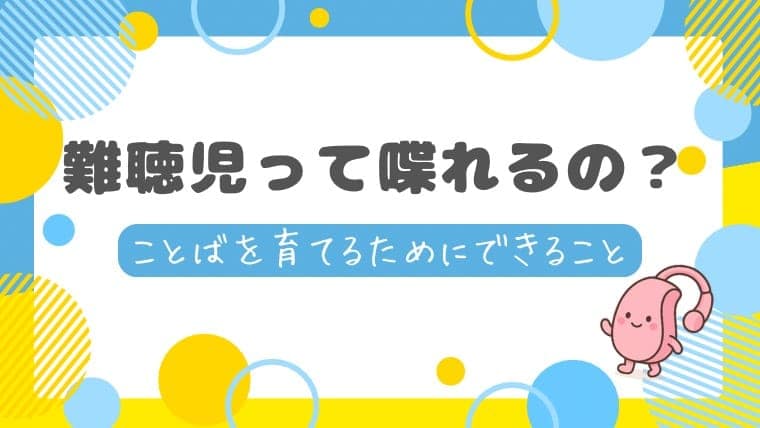
「難聴があると、ことばの発達は遅れるの?」
「この子も、いつかおしゃべりできるようになるのかな?」
そんな不安を感じたことはありませんか?
わたしも、長女の難聴がわかったばかりの頃は同じ気持ちでした。
恥ずかしながら、長女を産むまで難聴の方と接したことがなく、
『難聴のある子どもは喋れるのか?』
『どんなふうに成長していくのか?』
まったくイメージが湧きませんでした。
それでも少しずつ勉強しながら、試行錯誤の毎日を過ごしてきました。
気づけば、あの小さかった長女も今では小学生。
ことばも心も、ちゃんと育っていました。
- 難聴があっても、生後なるべく早く音を届けてあげることで『ことば』はしっかり育ち、喋れるようになる
- オノマトペを活用しながらたくさん話しかけよう!
- 家庭での声かけ・工夫・関わりが『ことば』の力を育てていく
私の経験を通してお伝えしたいのは、難聴があっても『ことば』はしっかり育つということ。
今回は、難聴児がどのように言葉を覚えていくのか、そして難聴児の言語獲得のために私たち親にできるサポートについてお話しします。
「聞くこと」から始まる『ことば』の発達
赤ちゃんは、生まれたときから耳で周りの音を聞きながら、少しずつ「ことばの世界」を感じ取っています。
そうした“聞こえの経験”が、言葉を育てる第一歩になります。
でも、難聴があると、その音の情報が脳にうまく届かないことがあります。
だからこそ、「早い時期に音を届けること」がとても大切です。
「1-3-6ルール」って知っていますか?
難聴の早期発見・早期支援を進めるために、アメリカの JCIH(Joint Committee on Infant Hearing) が提唱しているのが『1-3-6ルール』です。
- 生後1ヶ月までに: 新生児聴覚スクリーニング検査を受ける
- 生後3ヶ月までに: 難聴の確定診断を受ける
- 生後6ヶ月までに: 補聴器装用や療育などの支援を始める
このルールは、発達の早い時期から“音の経験”を積み重ねることを目的としています。
新生児聴覚スクリーニング検査については、こちらの記事で解説しています。
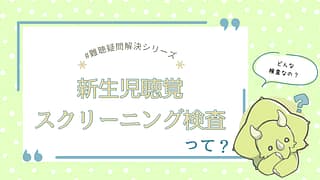
専門家の意見
研究や専門家の報告では、
「6ヶ月までに補聴器などを装用して音を届け始めた子どもは、言語発達がより良好である」
という結果が多く示されています。
アメリカのCDC(疾病対策センター)においても次のように示しています。
聴覚スクリーニング検査で異常が見つかった乳児は、生後6ヶ月までに介入サービスを開始することが望ましい
引用:https://www.cdc.gov/hearing-loss-children-guide/parents-guide/newborn-hearing-screening.html
このように、赤ちゃんには生後なるべく早く音を届けてあげることが、ことばの芽を育てる第一歩になります。
ことばを育てる家庭での工夫
難聴がある子どもの「ことばの発達」を支えるのは、補聴器や療育だけではありません。
家庭での関わり方も、とても大きな力になります。
① たくさん“話しかける”
生後6ヶ月までに補聴器や人工内耳をつけ始めた子どもにとって、「聞こえる世界」はまだ新しいもの。
ママやパパの生の声で語りかけることがいちばんの刺激になります。
「お皿洗うね」「お外明るいね」「お花きれいだね」
今見ていること・していることをそのまま言葉にするだけでOK。
これは「モデリング(言葉のモデルを見せる)」という支援の基本です。
『ことばのシャワー』をたくさん降らせてあげましょう!
② “音”に気づく場面を増やす
「ピンポン鳴ったね」「雨の音がするね」「わんわん吠えてるね」など、音に言葉を添えて知らせることで、「聞こえ」と「意味」を結びつけます。
このとき意識したいのがオノマトペ。
擬音語や擬態語(ピンポン、コロコロ、ペタッなど)を使うことで、音とことばのつながりがより分かりやすくなります。
③ ジェスチャーや表情もセットで
声・表情・動きをセットにして伝えると、子どもが理解しやすくなります。
「そうそう!」「聞こえたね!」と反応を喜ぶ声かけも大切です。
このとき、手話や指文字、ベビーサインなども一緒に使ってあげると、より赤ちゃんの言語獲得につながります。
④ 静かな環境をつくる
話しかけるときは、なるべく静かな場所で、顔を見ながら。
小さな工夫でも、聞き取りやすさがぐんと変わります。
私は、なるべくテレビをつけないようにすることも意識していました。
家事などでどうしても一人で遊んでいてほしいときにはテレビに頼ることもありますが、一緒に遊んだり、ご飯を食べたり、お絵描きをしているときは、テレビを消して雑音を減らし、私の声だけが届く環境をつくるようにしていました。
こうすることで、とうこが「言葉」と「音」をしっかり結びつけられる時間が増えたように思います。
⑤ “ことば”の成長を焦らない
すぐに話し出さなくても大丈夫。
少しずつ声掛けに反応したり、まねをしたりすることが確実な成長のサイン。
「ことばを育てる時間」そのものを一緒に楽しんでいきましょう!
家庭でできる声かけの工夫については、こちらの記事でも解説しています。
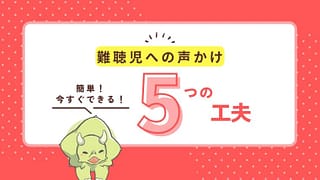
トリケラ家・長女とうこの場合
とうこが補聴器をつけ始めたのは、生後5か月20日。
着けた瞬間から大号泣で、初めて聞こえるたくさんの音に戸惑い、驚き、怖がっていました。
「泣いて嫌がっているのに補聴器をつけていいのかな…」
毎日が不安の連続でしたが、毎日朝起きたら補聴器をつけてたくさん遊び、いろいろな所にお出かけしてたくさん外の音を聞かせ、お風呂の前にまた補聴器を外す、という生活を続けました。
すると、ある日――
うつ伏せで遊んでいるとうこの名前を呼んだら、こちらを振り向いたんです。
その瞬間、「あ、聞こえてるんだ」と実感して涙が出ました。
初めて喋ったのは8か月頃、最初のことばは「パパ」。
そのあと「ママ」、そして飼い猫の「ニャンニャン」。
そこから少しずつ、「バイバイ」や「いただきます」といった動作をまねるように。
とうこのことばがどんどん“育っていく”のを肌で感じました。
家では、ST(言語聴覚士)の先生と相談しながら、「たくさん話しかける」「オノマトペを意識する」「言い換えを使う」などを実践。
発語が出てきたことで、「このままでいいんだ」と自信が持てました。
今では、学校で友だちとおしゃべりしたり、自分の気持ちを言葉で伝えたりできるようになりました。
もちろん聞き逃すこともありますが、とうこは毎日、「難聴があってもちゃんと話せるようになる」ということを教えてくれています。
まとめ
難聴があっても、ことばはちゃんと育ちます。
そのために大切なのは、「早く音を届けること」と、「聞こえを言葉に結びつける環境をつくること」。
補聴器や人工内耳で音の世界を広げたら、あとは家庭の中での声・まなざし・やり取りがことばの力を育てていきます。
うまくいかない日があっても大丈夫。
「今日も聞こえる世界を一緒に楽しもう!」
その気持ちが、いちばんのことばの栄養になります。

喋れていても、喋れていなくても…
その子の中に『ことば』はちゃんと育っているよ!