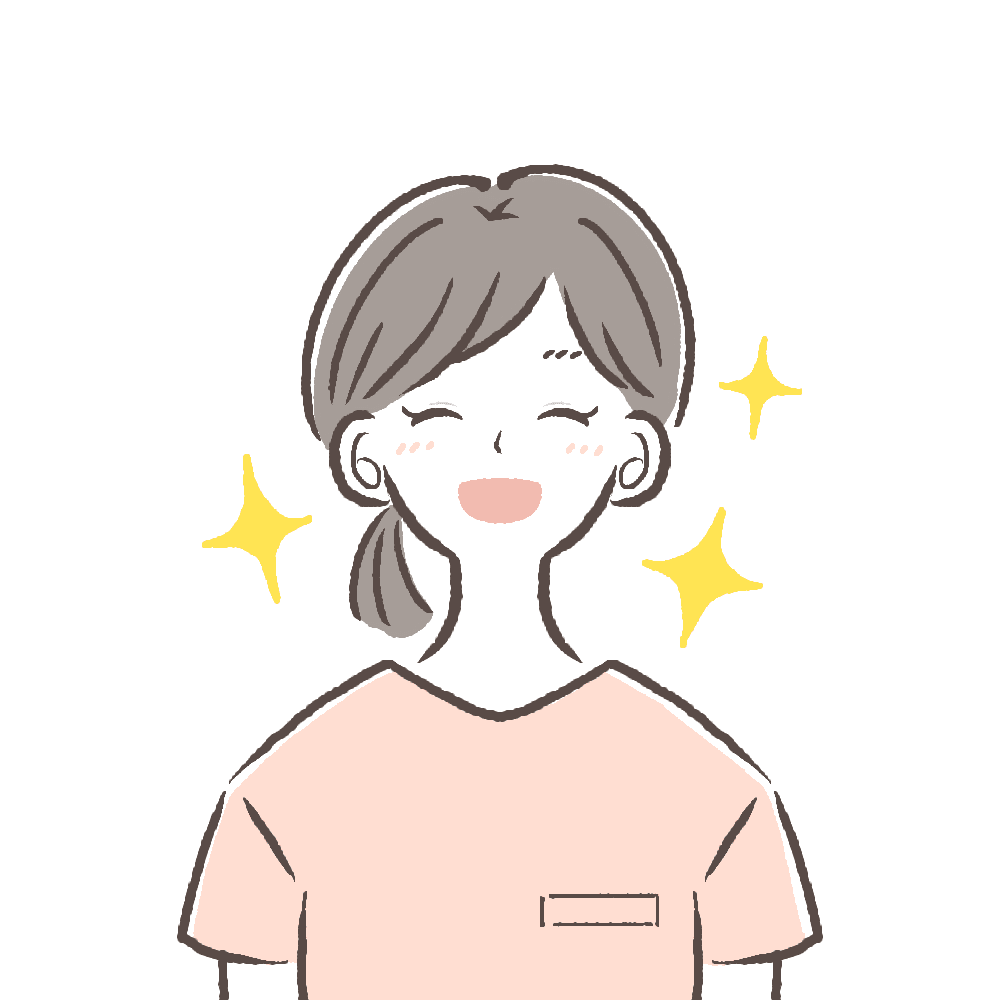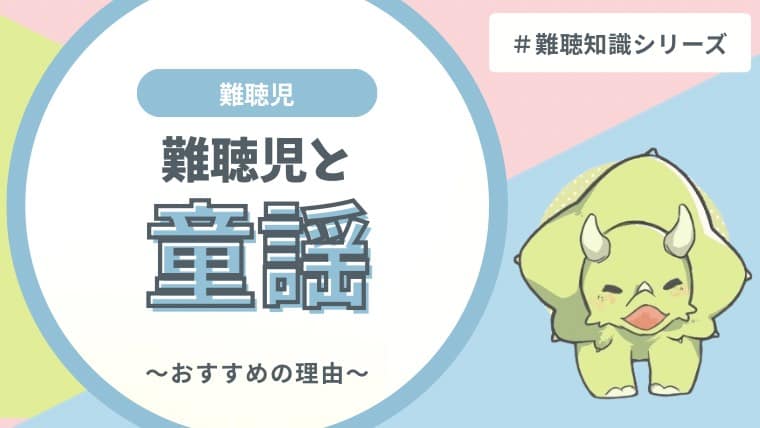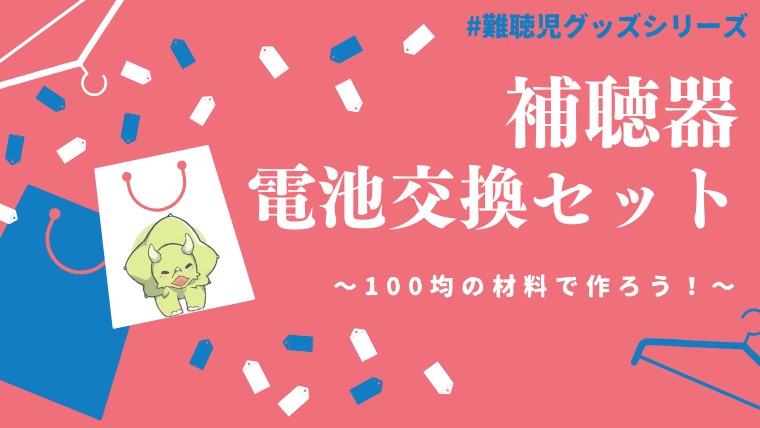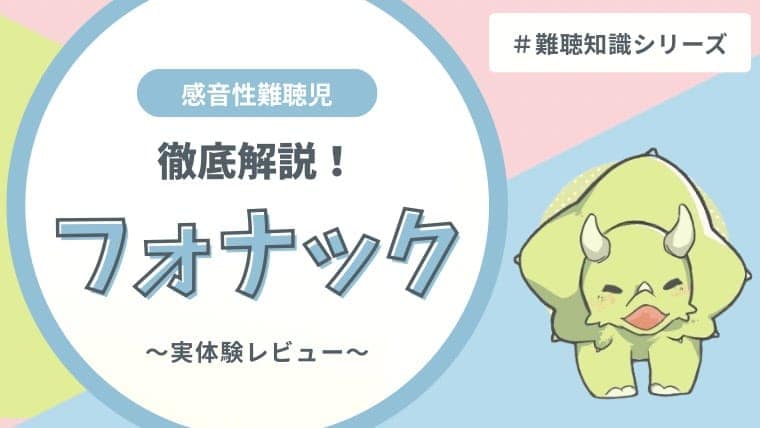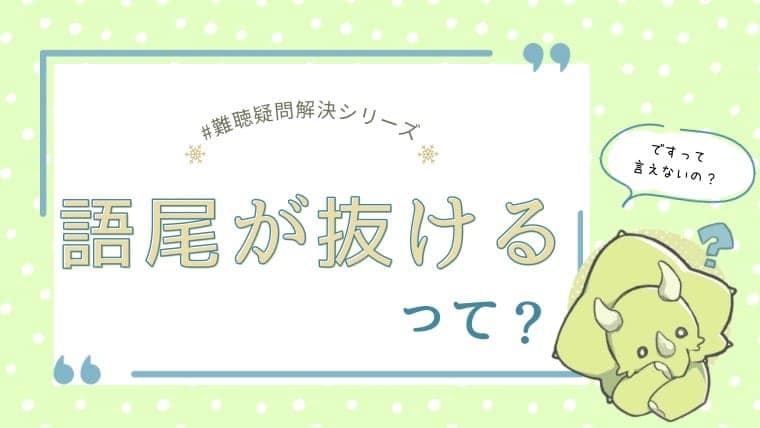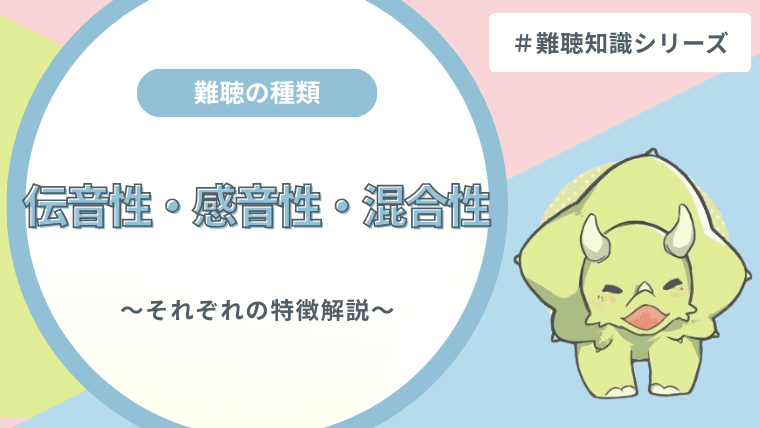療育とは?内容・対象・始め方をわかりやすく解説【体験談あり】
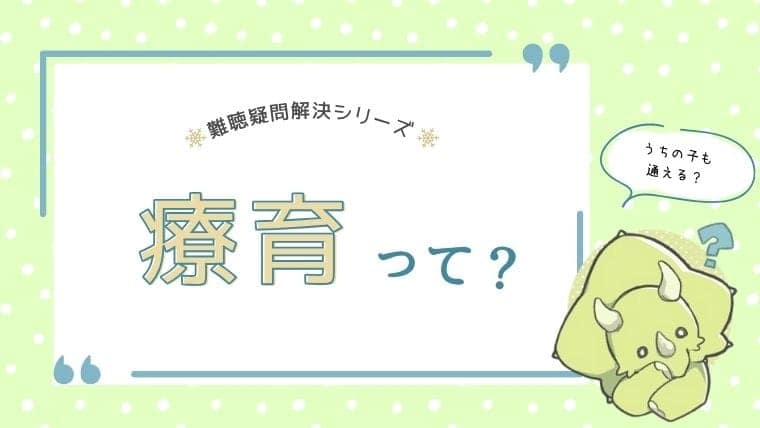
療育(りょういく)って何だろう?
療育(りょういく)とは、子どもの発達をサポートするための“練習と環境づくり”です。
医療と教育の中間のような支援で、専門家が一人ひとりの特性に合わせた関わりをしてくれます。
「発達がゆっくりかも」「ことばが少し遅れているかも」そんなときに紹介されることが多い“療育”。
でも、初めて聞くと「どんなことをするの?」「うちの子も受けられるの?」と不安になりますよね。
わたしも、長女とうこの難聴の確定診断が下りたときに“療育”という言葉を初めて知りました。
最初はよくわからなくて戸惑ったけれど、今振り返ると、療育があったからこそ安心して子どもたちの成長を見守れたと感じています。
- 療育とは、子どもの発達をサポートするための“練習と環境づくり”
- 難聴児も対象で、聞こえ方や発達に合わせた支援が受けられる
- 早く始めることよりも、安心して続けられる環境づくりが大切
この記事では、療育の意味と目的どんな子が対象なのか実際の内容や始め方を、ママ目線でやさしく紹介します。
療育とは?
「療育(りょういく)」という言葉は、“治療”と“教育”を組み合わせた言葉です。
病気を治すことが目的ではなく、子どもの発達をサポートし、その子が自分らしく生活できるようにするための“支援”を指します。
療育は、医療と教育の中間のような位置づけ。
言葉や身体の発達、社会性や感情のコントロールなど、成長の中で少しサポートが必要な部分を、専門家が一緒に育てていくイメージです。
わたしが最初に“療育”という言葉を聞いたときは、発達障害の子が通うところというイメージがありました。
だから正直、「難聴の子も通えるの?」と驚いたのを覚えています。
でも実際は、難聴児も療育を受けることができます。
音の聞こえ方に合わせてことばを育てたり、生活や学習の中で工夫をしたりと、“聞こえ”を中心にした発達支援が行われているんです。
担当する専門職もさまざまで、
- 言語聴覚士(ことばの発達を支援)
- 作業療法士(身体や感覚の発達をサポート)
- 保育士・臨床心理士(遊びや関わりを通して支援)など、子どもの状況に応じてチームで関わります。
“できないことを無理に教える”のではなく、できることを増やしていくための関わり。
それが療育の基本的な考え方です。
どんな子が対象?
療育の対象は、「発達に少し気になるところがある子ども」全般です。
たとえば、
- 言葉がゆっくり
- 集団行動が苦手
- 感覚の過敏さや鈍さがある
- コミュニケーションの取り方に特徴があるなど、診断の有無に関わらず、“困りごとがある子”が対象になります。
そして、難聴児も療育の対象に含まれます。
聞こえにくさがあることで、言葉の発達や他者との関わり方にサポートが必要な場合、言語聴覚士(ST)や発達支援センターの先生が、ひとりひとりに合わせた支援をしてくれます。
実際にとうこの場合も、難聴がわかった当初は発達全体の様子を見ながら、「聞こえをどう補い、言葉をどう育てていくか」という視点で療育を受けました。
“難聴=聞こえだけの問題”ではなく、“聞こえにくさが発達全体にどう影響しているか”を見てもらえるのが、療育の大きな特徴です。
つまり、障害者手帳の所持の有無は、療育の受給資格とは関係ありませんので安心してください。
難聴児の障害者手帳については、こちらの記事で解説しています。
[jin_icon_arrowdouble]子どもの難聴と障害者手帳|交付の基準・必要書類・支援内容をわかりやすく解説
https://www.triceratops-family.com/hearing-loss-disability-certificate/858/何歳から何歳まで通えるの?
療育は、0歳から18歳まで(自治体によっては就学前・小学生まで)を対象としています。
特に、早期のサポートが大切とされるため、0〜6歳ごろの未就学児期にスタートする子が多いです。
赤ちゃんのうちは「児童発達支援」という枠組みで、就学後は「放課後等デイサービス(放デイ)」として支援が続きます。
年齢が上がっても、その子の成長に合わせて内容を変えながら継続できるのが特徴です。
放課後等デイサービスについては、こちらの記事で解説しています。
https://www.triceratops-family.com/after-school-daycare-2/374/ https://www.triceratops-family.com/after-school-daycare/360/療育につながるタイミングのちがい
発達障害の場合は、特徴がはっきりするまで時間がかかることもあり、診断や療育まで少し時間がかかるケースもあります。
一方、難聴のように早く診断が下りる身体障害では、医療機関から発達支援センターなどへスムーズに紹介がつながるため、早い段階で療育が始められることもあります。
とうこは生後4ヶ月から、そらは生後3ヶ月から療育を始めることができました。
どんなことをするの?
療育で行う内容は、子どもの特性や発達段階によってさまざまです。
一人ひとりに合わせて、「できることを増やしていく」「自信をつけていく」ことを目的に、遊びや生活の中で自然に学べるよう工夫されています。
主なプログラムには、次のようなものがあります。
- 言語訓練(ことばの練習)
- 感覚統合・運動あそび
- コミュニケーション・社会性の練習
とうことそらが通っていた所も、最初は同じ年頃の子たちとの遊びが中心の内容でした。
「お集まりをしてお名前を呼ばれたら手を挙げる」「音の鳴るおもちゃで遊ぶ」など、一見シンプルな活動の中に、“聞く・見る・反応する”の練習がたくさん詰まっていました。
療育の先生たちは、子どもが楽しく取り組めるように声かけやペースを調整してくれます。
「できた!」という小さな成功体験を積み重ねて、療育に通うことを楽しみ、少しずつ自信を育てていく——
それが、療育のいちばん大切なポイントです。
どうやって始めるの?
療育を始めるには、まず「相談」からスタートします。
ステップ①:相談
まずはお住いの市町村の子育て支援課・障がい福祉課・発達支援センターなどに「療育を受けたい」と相談をしてみてください。
ステップ②:受給者証の申請
療育には「通所受給者証」が必要な場合があります。
家庭の自己負担は原則1割(上限あり)です。
2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」により、3歳〜5歳で児童発達支援を利用する子どもは、利用料が無償になります。
ただし、自治体によって対象や開始時期が少し異なるため、詳細はお住まいの市町村に確認をしてください。
ステップ③:見学・体験して選ぶ
とうこのときは、難聴に特化した療育施設が県内にひとつしかないため、そこに見学に行きました。
とてもあたたかい雰囲気で、「ここなら安心して通えそう」と感じ、早くとうこをサポートしてあげたいと思ったことを今でも覚えています。
ステップ④:利用開始手続き
通う施設が決まったら、いよいよ利用開始の準備です。
といっても、難しいことはほとんどありません。
施設のスタッフさんが丁寧に説明してくださいますので、流れに沿って進めていけば大丈夫です!
療育を受けるまでの詳しい流れについては、また別の記事で解説します。
家庭でできること
家庭では、安心できる環境づくりがいちばん大切。
- 短く・ゆっくり・目を見て話す
- できた!をすぐに褒める
- がんばりすぎない
そして、とうこの療育の先生が言っていた言葉が、今でも心に残っています。
療育は、家とも保育園・幼稚園とも違う場所。
通うだけで、子どもたちはドキドキしているんです。
だから、療育の場でできなかったことがあっても責めないで、“今日もがんばったね”って、いっぱい褒めてあげてくださいね。
その言葉を思い出すたびに、「がんばったね」と伝えることの大切さを感じます。
子どもが安心できる“おうち時間”こそが、いちばんの支えになるんだと思います。
他にも家庭でできる声かけの工夫などについては、こちらの記事をご覧ください。
[jin_icon_arrowdouble]難聴児への声かけの工夫5選|家庭でできる“伝わる”コミュニケーション
https://www.triceratops-family.com/communication/456/まとめ
療育とは、子どもの発達をサポートするための“練習と環境づくり”。
難聴のある子も対象で、聞こえ方に合わせた関わりを通して、言葉や社会性をゆっくり育てていくことができます。
大切なのは、“早く始めること”よりも、“安心して続けられること”。
家庭でも「できたね」「今日もがんばったね」と声をかけて、子どもの小さな成長を一緒に喜んでいけたら十分です。
実際にとうこ・そらが受けてきた療育の内容については、また別の記事でご紹介します。
楽しく通える施設が見つかるとといいね!