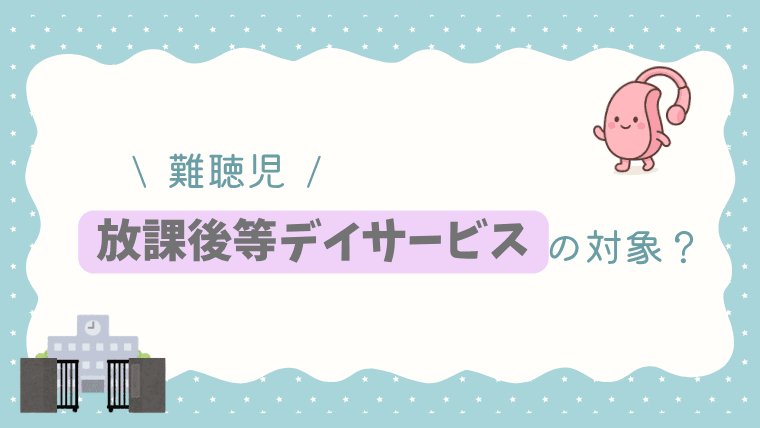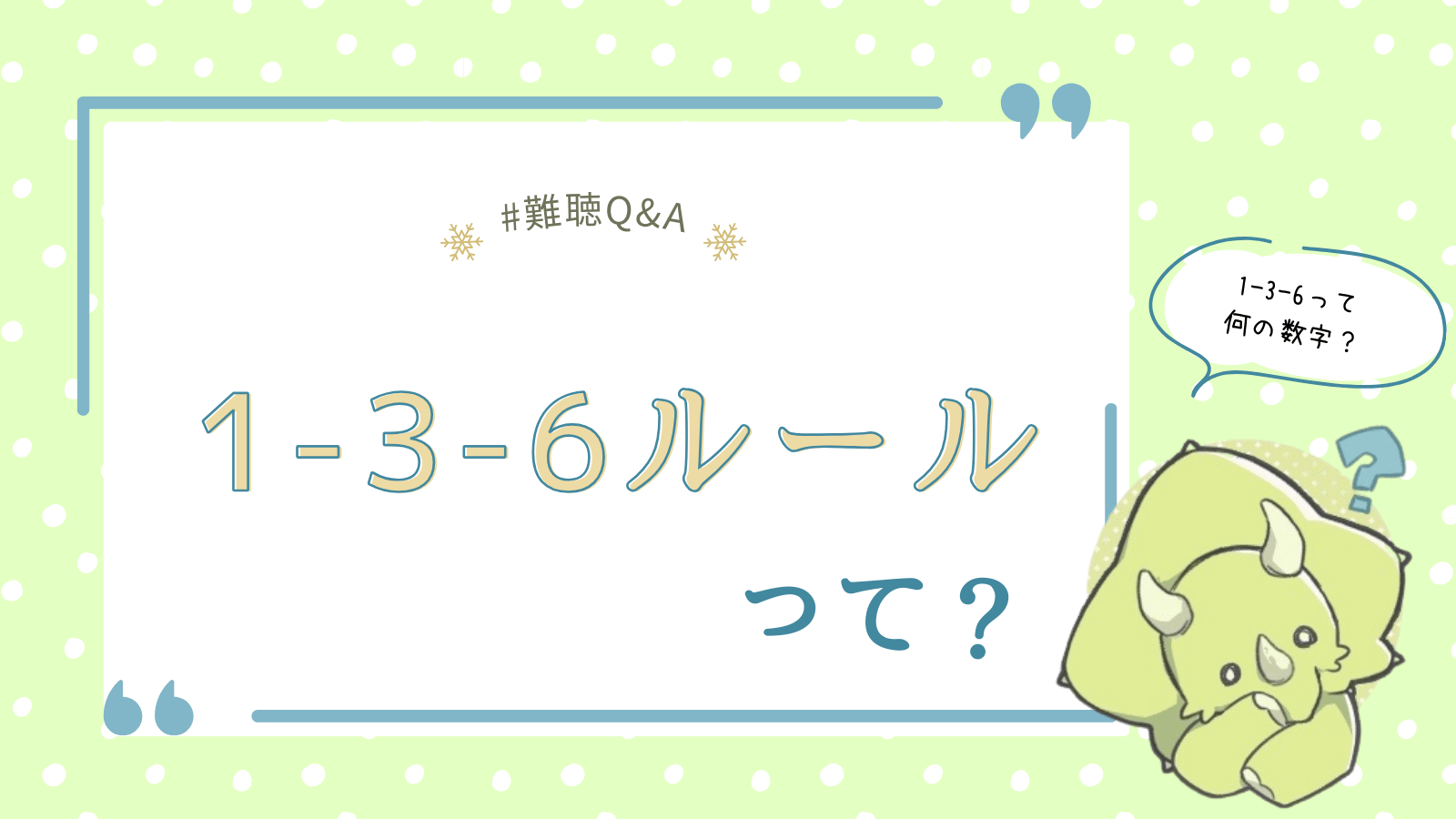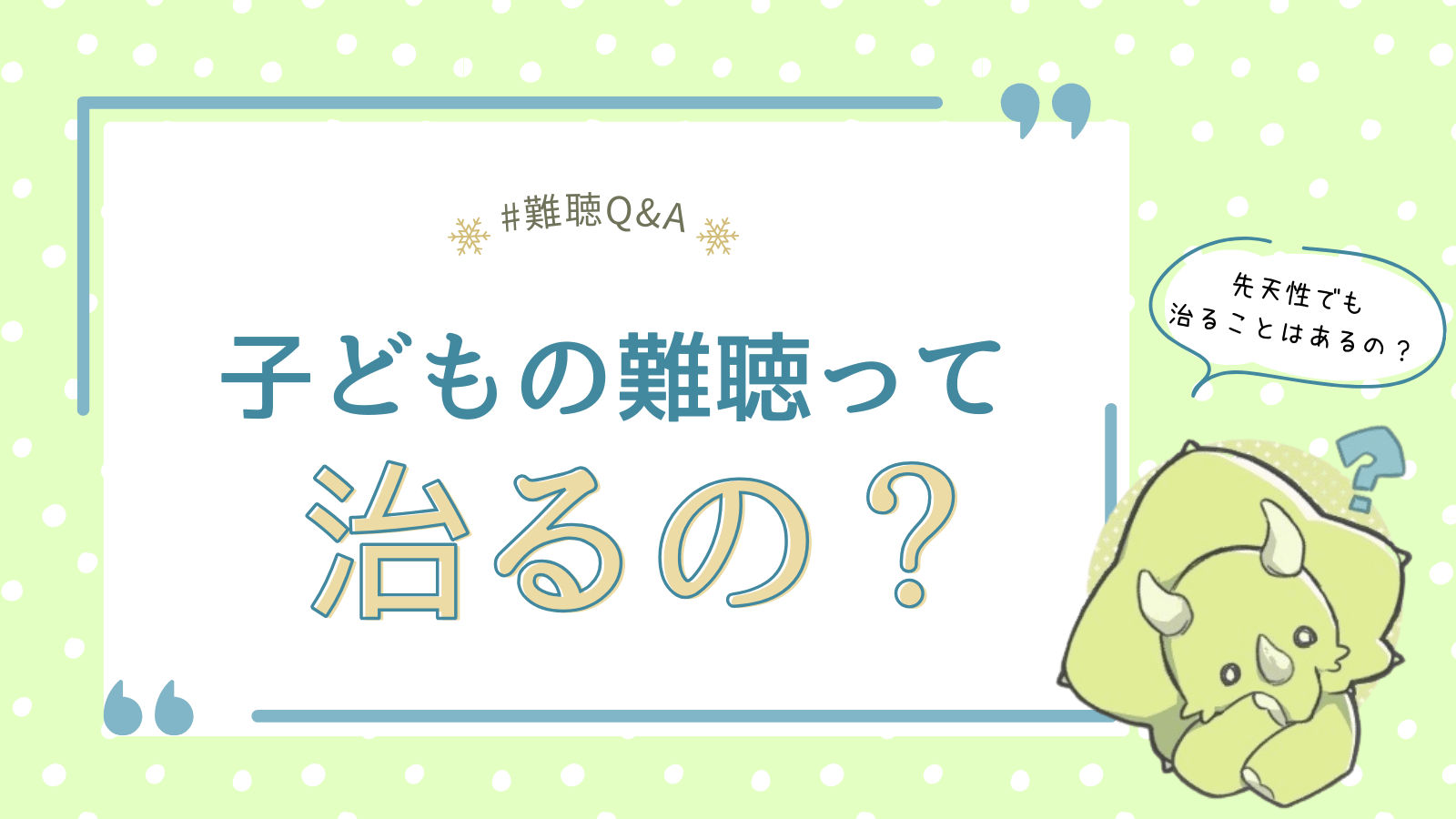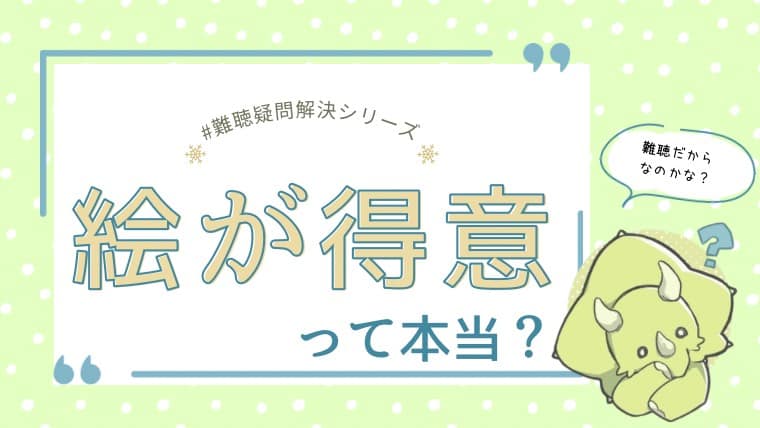聴力の単位dB(デシベル)とは?数値の意味と聞こえの目安をわかりやすく解説
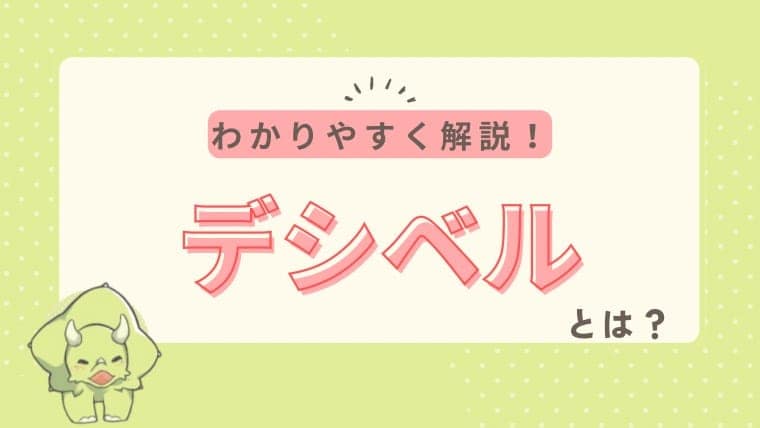
娘の聴力検査の結果を見たとき、「右耳40dB、左耳45dB」と書かれていて、正直どういうことなのか分かりませんでした。
“dB(デシベル)”というのは、音の大きさを表す単位のようで、でも実際には“どれだけ小さな音まで聞き取れるか”を示す数値なんです。
この記事では、聴力検査でよく見る「dB(デシベル)」の意味や、数値の違いがどのように“聞こえ”の差につながるのかを、日常の音を例にしながらわかりやすく解説します。
- dB(デシベル)は、「音の聞こえやすさ」を数値で表す単位
- 数値が大きいほど、大きな音でないと聞こえにくい
- 日常の音と比べると、聞こえの状態をイメージしやすくなる
dB(デシベル)とは?
聴力検査で使われる「dB(デシベル)」とは、音の大きさを表す単位です。
ただし、ここでの“音の大きさ”は、単純に「音量」を指すのではなく、人がどれくらい小さな音まで聞き取れるかを示す目安のようなものです。
たとえば、正常な聴力を持つ人が「やっと聞こえるくらいに小さな音」を0dBとします。
つまり、0dBより大きい数値になるほど「より大きな音でないと聞こえにくい」ということになります。
聴力検査でのdBの見方
聴力検査では、「どのくらいの音の大きさで聞こえるか」を数値で表します。
検査結果は、オージオグラム(聴力図)というグラフにまとめられ、横軸が音の高さ(周波数)、縦軸が音の大きさ(dB)を示します。
数値が小さいほど小さな音でも聞こえる=よく聞こえている状態、逆に数値が大きいほど大きな音でないと聞こえにくい状態を意味します。
聴力と聞こえの状態などをまとめたものが次の表です。
| 聴力(dB) | 聞こえの状態 | 聞こえの特徴 |
|---|---|---|
| 0~25dB | 正常 | 小さな声やささやき声も聞き取れる |
| 26~40dB | 軽度難聴 | 少し離れると会話が聞き取りづらい |
| 41~70dB | 中度難聴 | 普通の会話が聞き取りづらい |
| 71~90dB | 高度難聴 | 大きな声でも聞こえにくい |
| 91dB以上 | 重度難聴 | ほとんどの音が聞こえない |
この表を見ると、たとえば「40dB」と書かれていた場合は、日常会話の声より少し大きめの音でやっと聞こえる、というイメージになります。
聴力検査には、ABR検査やASSR検査など様々な検査方法があり、詳しくはこちらの記事で解説しています。


日常生活の音と比較してみよう
「◯dB」と言われても、実際どのくらいの音なのかはイメージしづらいですよね。そこで、日常生活でよく聞く音とdBの目安を表にしてみました。
| 音の種類 | おおよその大きさ(dB) | 聞こえのイメージ |
|---|---|---|
| ささやき声 | 約30dB | 耳の近くで話しかける程度 |
| 普通の会話 | 約60dB | 家族や先生との会話程度 |
| 掃除機の音 | 約70dB | 少し離れていても聞こえる程度 |
| ピアノの演奏 | 約80dB | 音楽室での演奏程度 |
| 電車の音 | 約90dB | 大きな声を出さないと会話が難しい程度 |
| 工事現場の音 | 約100dB | 耳をふさぎたくなる程度 |
| 飛行機のエンジン音 | 約110dB | すぐそばにいると耳が痛くなる程度 |
学校や職場での聴力検査で、ヘッドホンを着けて音を聞き、「聞こえたらボタンを押す」という検査を受けたことがある方も多いと思います。
あの機械こそが、聴力を測る装置(オージオメータ)で、その結果をまとめたグラフが「オージオグラム」と呼ばれます。
検査で流れる、聞こえるか聞こえないかギリギリの小さな“ピッ”という音。あの音は、およそ20〜25dB前後の、とても小さな音なんです。
つまり、検査の中で「ボタンを押せた音」は、「これくらいの小さな音まで聞き取れている」という目安になります。
この表と照らし合わせてみると、「40dBくらいの音でやっと聞こえる」というのは、ささやき声は聞こえにくいけれど、普通の会話なら届く、というイメージになります。
ちなみに、トリケラ家の長女とうこ・次女そらの新生児聴覚スクリーニング検査の結果による聴力は40〜60dB程度。医療的には「中等度の難聴」にあたります。
補聴器を装用すると、聴こえる範囲はおよそ20〜40dB程度まで改善しますが、それ以上すべての音が聞こえるようになるわけではありません。補聴器は音を“大きくする”道具であって、“完全に元の聴力に戻す”ものではないのです。
それでも、適切な調整やサポートがあれば、子どもたちは必要な音をしっかりキャッチしながら、日々の生活を楽しんでいます。
補聴器の限界については、こちらの記事をご覧ください。
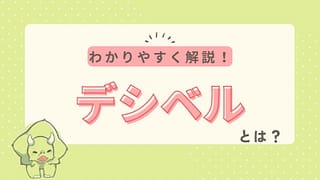
まとめ
dB(デシベル)は、「音の聞こえやすさ」や「どれだけ小さな音まで聞こえるか」を表す単位です。数値が大きいほど、大きな音でないと聞こえにくいことを意味します。
聴力検査の結果で出てくる数値を、日常の音や検査での“ピッ”という音と照らし合わせてみると、お子さんやご自身の「聞こえの状態」がより具体的にイメージできるようになります。
数値はただの結果ではなく、「聞こえ方を知るための手がかり」。検査のたびに変化を見ながら、耳の状態をやさしく見守っていきましょう。

一歩ずつお子さんの聞こえについて学んでいこうね!